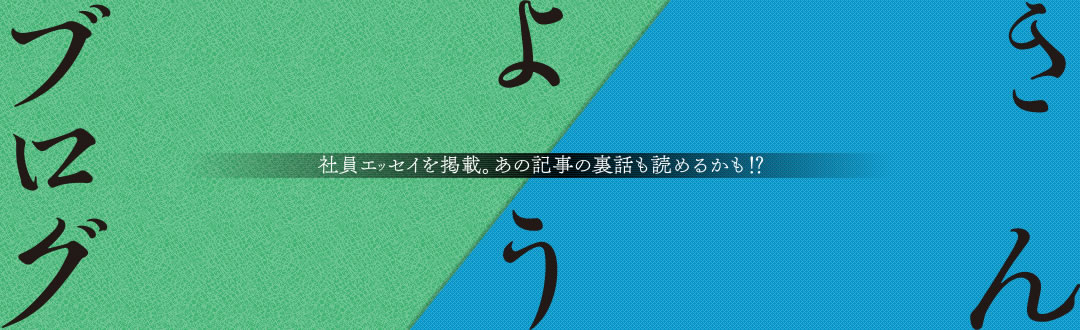本当は恐ろしい『源氏物語』(1)
2008年12月11日5:03PM|カテゴリー:そぞろ歩きはナンパ|madao
2008年は『源氏物語』が書かれてジャスト1000年なので、テレビや出版など色々なイベントがありましたが、大長編でもあり、このサイトを読んでいる人でも(原文はもちろん現代語訳でも)読み通した人は少ないかもしれません。
でも、『源氏物語』を単にイケメン・プレイボーイの恋愛遍歴物語だと思って(そう思っている人が多いらしい)、読んでないとしたらとってももったいない話です。
1000年も読みつがれるにはそれなりのワケがあります。
今回ご紹介するのは、『源氏物語』には幾重にもはりめぐらされた「仕掛け」があるというお話。
仕掛けと言ってもミステリーのトリックのような仕掛けではなくて、虚構の物語なのに、現実を変えてしまうという「呪い」か「予言」のような仕掛けです。
とりあえず、私が気づいたところを、3つほどご紹介します。
1つ目は、同時代の権力に対する仕掛け。
この仕掛けは1000年ではなく200年ぐらいで作動しました。
物語では主人公の光源氏は、天皇の子どもとして生まれながら、母親がセレブな出自でないという理由で臣下に降格、陰謀で左遷までさせられますが、徐々に権力を手中にし、ついにはときの天皇をも超える地位にまで上りつめます。
キーポイントは、書かれた時代が「藤原氏」全盛期だったのに、物語では藤原氏を思わせる一族を押しのけて、「源氏」姓の光源氏が立場逆転で栄華を極める筋立てであること。
史実では、藤原一族は、数々の陰謀によって源高明・源融といった「源氏」姓の政敵を葬ることによって権力を奪っていますから、物語は、明らさまにこれを転覆しているのです。
SF作家P.K.ディックの『高い城の男』は、第二次世界大戦で「日独伊同盟側が勝利した」という設定でストーリーが展開しますが、現実と反転した物語の構造はよく似ています。
多くの人が学生時代に習った冒頭の「いづれの御時にか」(どの御代のことであったか)という書き出しが、実際にどの時代を暗示しているのか(「準拠」と呼ぶそうです)は諸説紛々で、というのも物語中の数人の天皇の名前が実在の天皇の名前と一致するからで、余計にこの歴史物語の「真意」への穿鑿が当時から現代まで絶えないというわけです。
もちろん、このような反転構造の物語を許容した藤原一族に「余裕」があったとみることもできますが、物語から、およそ200年後に、ご存知のように実際に「源氏」姓の一族が、権力を掌握したのですから、結果として現実が物語をなぞってしまったのです。
2つ目は、古代から現代まで、1000年をはるかに超える「万世一系」の天皇制に対する仕掛けです。
源氏千年紀の今年ですが、あまり語られないのは、戦時中、『源氏物語』は「大不敬の書」とみなされたという事実です。実際、有名な谷崎潤一郎訳の『源氏物語』の戦前版は、このためにいくつかのアブナイ箇所が改変させられています。
なぜでしょうか?
「2千円札」が消えたこととも何か関係があるのでしょうか?
答えは、本誌12月12日号所収の「逆光の源氏物語千年紀」に詳しく書かれています。
というわけで、ごめんなさい、こちらは本誌を読んでください。
3つ目の仕掛けは・・・・・・次回に続きます。
(まだお)