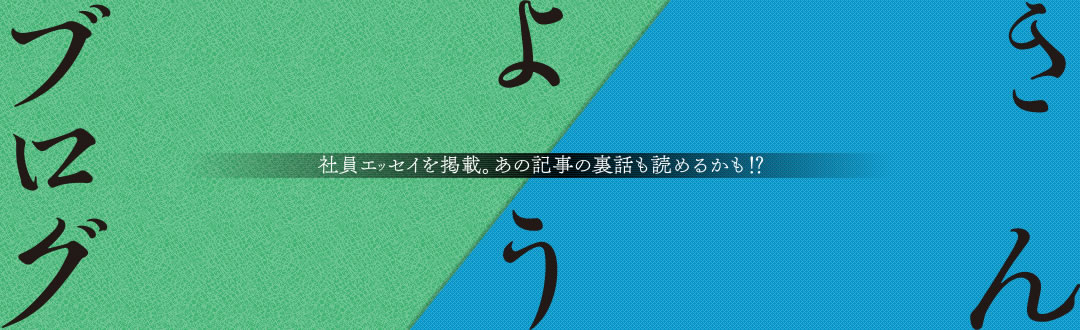大逆事件100年で、いま考える「国家の欲望」
2011年1月27日6:28PM|カテゴリー:多角多面(発行人コラム)|北村 肇
<北村肇の「多角多面」(15)>
幸徳秋水ら11人がでっちあげの「明治天皇暗殺計画」により処刑されたのは、100年前の1911年1月24日。翌日、管野スガ(須賀子)も死刑台の露と消えた。大日本帝国憲法下では、大逆罪の裁判は非公開が原則。だが、幸徳秋水ら26人に判決(24人に死刑、2人に有期刑)がおりた同月18日の公判は公開だった。桂太郎内閣にはみせしめの意図があったのだろう。本誌今週号から始まった連載「残夢 大逆事件を生き抜いた男 坂本清馬の一生」で、著者の鎌田慧さんもそう指摘している。
この1世紀前の事件が語りかけてくるものは何か。私は、「国家の欲望」と「個人の欲望」がシンクロしたときのおぞましさを強烈に感じる。明治維新後、日本は異常な速度で帝国主義国家の仲間入りを目指す。そのために欠かせない「戦争」と「侵略」を遂行するには強圧的な国民統合が不可欠。時の政府は「天皇制」を不可侵とすることで、「反国家主義」勢力を弾圧した。まさに「国家の欲望」のもとで、市民の人権や自由を踏みにじったのだ。
しかし、現実に政策を推し進めるのは「個人」である。その「個人の欲望」は「国家の欲望を実現する」ことで充足する。カネや地位、名誉が中心になるのは言うまでもない。歴史は単純に繰り返さないが、こうした「国家の欲望」と「個人の欲望」のシンクロはいつでも起こりうる。本質的には大逆事件と同様の国家犯罪が絶えることはないのだ。
さて、2011年のいま、国家が不可侵としているのは「日米同盟」である。米国との連帯を損なうことは、一種の不敬罪なのだ。そう考えれば、鳩山由紀夫首相の退陣も、小沢一郎氏の失脚も背景がぼんやり浮かんでくる。強引すぎることは承知の上だが、私には形を変えた大逆事件に見えてしまう。
ただし、100年前と決定的に異なるのは、明治時代の「国家」は大日本帝国であり、21世紀の「国家」は米国属国の日本ということだ。つまり、「国家の欲望」とは「米国の欲望」にほかならない。米国に尽くすことで「日本としての国家の欲望」を充足するという二重構造になっているのだ。当然、政治家、官僚、財界人の「個人の欲望」も複雑に歪んでいる。ただ、こちらはつまるところ「カネ、地位、名誉」に行き着く。
そして、一向に変わらないのがマスコミだ。「小沢報道」も「普天間基地報道」も大逆事件報道に通底する。「権力の意向を忖度する」姿勢が垣間見られるからだ。大逆事件判決後、法廷では多くの被告が「無政府党万歳」と叫んだ。『朝日新聞』は翌日の紙面で、「何処までも不謹慎な彼等かな」と報じたという。(2011/1/28)