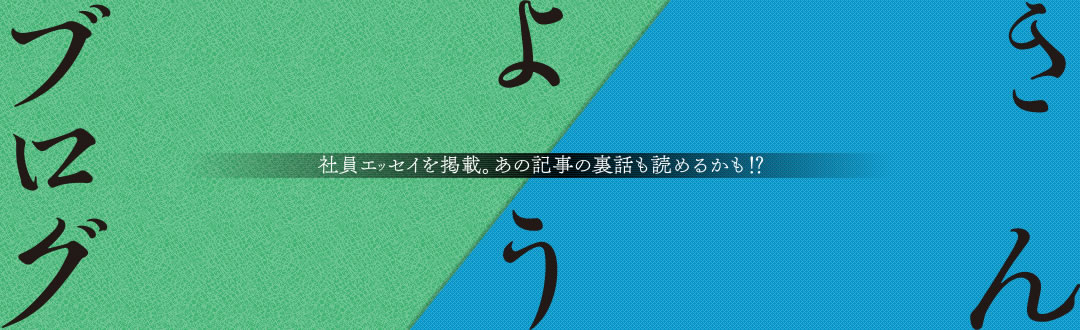大学の同期会に初めて出席した理由
2012年8月22日5:27PM|カテゴリー:多角多面(発行人コラム)|北村 肇
<北村肇の「多角多面」(90)>
オリンピックイヤーに開かれる同期会に出席した。大学を卒業して38年。これまで一度も参加したことがない。でも分かっていた。会うなり「やあやあ」となることを。みんな還暦を超えている。見た目は変わっている。それでも顔をあわせた瞬間、38年程度の時間は一気に縮まる。
同窓会や同期会から足が遠のく理由は、そこにあったのかもしれない。「昨日のことのように」触れあうのが苦手なのだ。お互いの間にある空白の時間を埋めるため、ついつい「何をしていた。何をしている」と語り合うことになる。そして酒が入るにつれ「あのころ」のエピソードをつまみにする。
それはそれで楽しい。だが、この空間が明日につながることはほとんどない。翌日には、38年前とおなじくらいに「過去」のことになっている。現実に引き戻されるのもまた一気だからだ。その現実には多くの知人・友人がいる。こちらは「やあやあ」とばかりにはいかない。もろもろのしがらみや利害関係が微妙にからみあう。
20代のころ、先輩諸氏から同じ事を聞かされた。「中学校より高校、高校より大学、何より社会人になってからの友人が一番、濃い付き合いになる」。確かにそうだ。その理由は、秤にかけたとき「思い出」より「現実空間」のほうが圧倒的に重いからだと思う。きれいごとではないから濃い。
55年体制へのノスタルジーを語る人が増えた。70年代の「熱い時代」で話が盛り上がる。その中に私もいる。どんなに自分に言い聞かせても「あのころのほうが、まだ良かった」と口走ってしまう。過去を引きずったり、思い出に逃げ込むようになったら終わりだと、しっかり腹に据えていたはずなのに。
一個人としては、「未来」が「過去」より大きい年齢はすでに過ぎた。しかし、社会にとって「未来」は常に無限大だ。その社会に存している限り、「私」は無限の可能性に向かって自己を飛翔させなくてはならない。重油の海を泳ぐような感覚にぐったりすることもある。だが、「過去」を積み重ねた人間にとり、それは責務であろう。
同期会では「紫陽花革命」が話題になった。そのからみで意見交換を続けることにもなった。数日して、はたと気づいた。初めて出席した理由についてだ。日本は明らかに変わりつつある。このことを70年代の友人と確認したかったのだ。(2012/8/20)