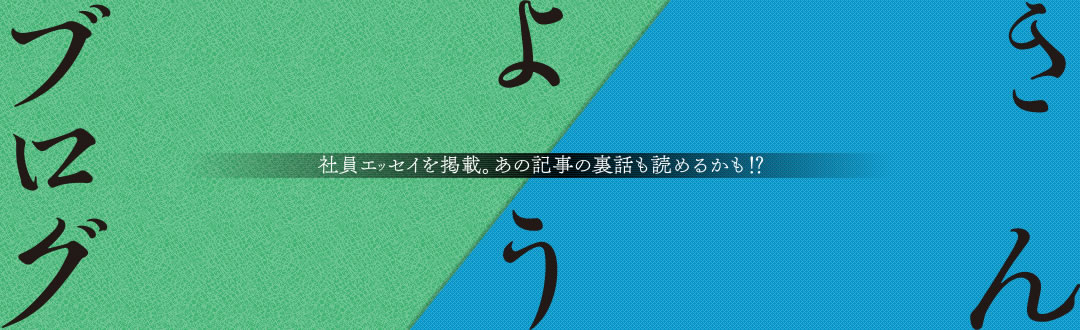なぜ原発を題材にした劇映画が『希望の国』だけなのか
2012年11月14日4:40PM|カテゴリー:多角多面(発行人コラム)|北村 肇
<北村肇の「多角多面」(102)>
黒澤明監督の『影武者』だったか、無数の馬が戦(いくさ)で傷つき、川の中に次々と倒れていく場面が延々と続いた。冗長なラストシーンだという批判が飛び交い、そのことが話題になった。私のような素人目からも首をひねる終わり方だった。だが、何年か後、唐突にその場面を思い出し、黒澤氏の意図が読み取れた(気がした)。戦国時代に限らず、人類は繰り返し繰り返し、戦に手を染めてきた。この愚かな、あまりにも愚かな戦乱の歴史に対する怒りが、あのラストに込められていたのだろう。
話題の映画『希望の国』には三つのエンディングが用意されている。原発事故で強制退去を迫られた酪農夫婦の心中、生まれてくる子どものために避難した若夫婦を襲う再びの被曝、そして結婚を決めた恋人同士が、津波で破壊された街を「一歩、一歩」と歩くシーン。最後の場面にわずかな希望を見る観客はいるかもしれない。しかし、私には、とりわけ残酷で救いようのない未来を象徴するように感じ取れた。「一歩、一歩」と進む先には、人っ子一人いない瓦礫が延々と続き、そこには絶望しか存在しない――。
本誌10月19日号のインタビューで「日本の劇映画で、作品世界に原発を取り入れようという動きはあまりなかったですね」と聞かれた園子温監督は次のように答えた。
今回も取材で一番多い質問が「なぜ原発の映画を撮ったのか?」なんですよ。海外では、そんな質問出ないですよ。こないだカナダ・トロントの映画祭で会見やったときもそんな質問一つも出なかった。なぜ撮ったか?なんておかしいでしょ。そりゃ、目の前で原発爆発したんだからさ、撮らないほうが変でしょ。まるで僕の頭おかしいみたいに言われて。聞くなら「なぜ(他の人たちは)撮らないのか?」でしょ。
その通りだ。原発事故の本質を抉る芸術作品が出てこないのは、「昭和天皇タブー」にどこかで通じる気がする。あれだけの事故が起きてなお、原発は触れてはいけない存在なのだ。かくして、戦争責任問題がついにあいまいな霧に覆われたまま終わったように、福島原発事故の責任問題はあってなかったものになる。園監督の「絶望」の大本はそこにあるのではないか。
『週刊金曜日』は「あらゆるタブーを排する」ことを礎に誕生した。タブーは報道を歪め、ジャーナリズムを堕落させ、結果として読者を裏切ることになるからだ。一方、芸術におけるタブーは、自由な創造性を喪わせ、文化的に貧しい社会を生む。傍若無人の石原慎太郎さん、余生は原発タブーに斬り込む小説を書いてはいかが。(2012/11/16)