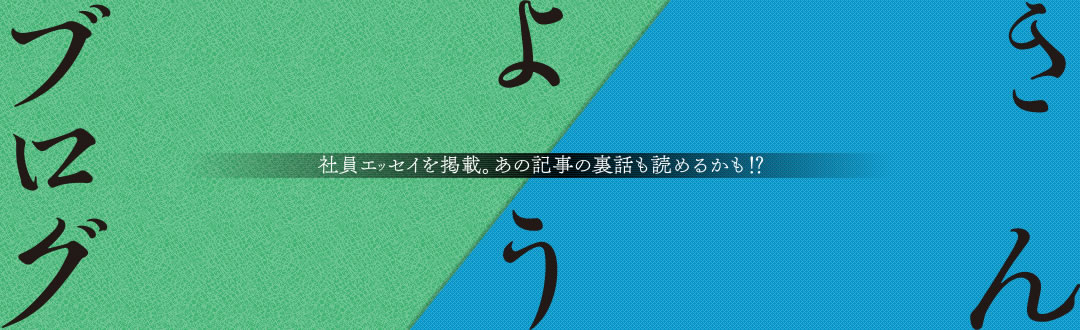カミュの「あいまいさ」が不条理を乗りこえるための道
2012年11月20日5:41PM|カテゴリー:多角多面(発行人コラム)|北村 肇
<北村肇の「多角多面」(103)>
カミュの「あいまいさ」が不条理を乗りこえるための道
まだ昼下がりというのに、あけっぴろげの田園は薄墨色の空に覆われていた。地平線上にギザギザを描く山並みの上に、わずかばかりの光が恥ずかしげに見え隠れするばかりだ。秋田を出発した「こまち号」は岩手にさしかかっていた。ふいに、福島原発から流れ込んだ黒雲が哄笑しているような錯覚に陥った。アルベール・カミュの小説を読んでいたからかもしれない。こんな一節に出会ったとき、たまたま車窓に目をやったのだ。
「私のなかには恐ろしい虚無が、私を苦しめる無関心がある」(『最初の人間』新潮文庫)
人間の不条理を突き詰めたカミュは、若くしてノーベル文学賞をとりながらも、自己に巣くう虚無にさいなまれ続けていたように思う。ただし、その虚無は決して「無」を意味しない。真空が実は「無」ではないように、彼の虚無は膨大なエネルギーに埋め尽くされていた。人間とは何か、生とは何か、死とは何か。これらの問いを自己に投げかければ投げかけるほど、目指す「解」は遠のく。つまり、虚無の密度は果てしなく濃くなるのだ。
現代社会は閉塞状況といわれる。虚無感が漂っているかのように表されることもある。だがそれは、カミュの虚無とは異質なものであり、スカスカの軽石のようだ。何のために生きているのか自問自答することはなく、孤島に流れ着き助けを求めようにも大海原には一隻の船も見えない中で不条理さを嘆く。要は不運を恨んでいるにすぎない。
もちろん、個々の人間に責めを負わせてすむ話しではない。少なくとも70年代半ば以降、市民は「考える」ことを奪われてきた。政治家も、官僚も、マスメディアも「目の前の利益だけを見なさい」と仕向けてきたのだ。いま社会を覆っているのは、「権力者」によって意図的につくられた、のっぺらぼうの虚無である。
カミュは文学的なあいまいさをサルトルに激しく断罪された。しかし、私はこのあいまいさこそが不条理を乗りこえる一つの道のように思う。たとえば「人間とは何か」や「革命とは何か」に対する絶対的な解答はない。深海に小石を落とすかのごとく、ひょっとしたら無意味な行為なのかと思えるほどの自問自答を繰り返し、時に、あいまいな解答に出会ったような錯覚に陥る。これこそが実は「生きる」ことではないのか。
何よりも重要なのは、自分の言葉で、自分の頭で考えることだ。悩み続けることだ。政治が混迷を極めるいまこそ、不条理から目を背けてはならない。迂遠のようだが、ひとり一人が自らの存在を突き詰めるところからすべては始まる。(2012/11/23)