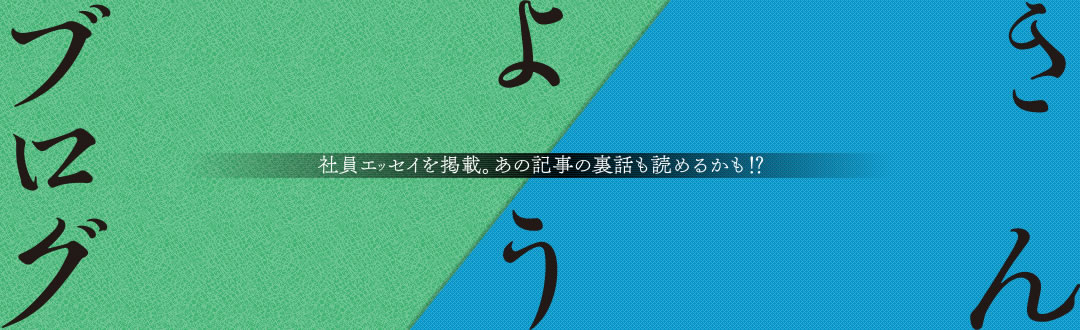◆村上春樹人気と安倍政権支持率の相関関係◆
2013年6月12日2:21PM|カテゴリー:多角多面(発行人コラム)|北村 肇
〈北村肇の「多角多面」129〉
どうしようかと逡巡したけれど、やはり書いておくことにした。これほどの駄作が100万部も売れてしまう、そのことが示す危機的状況は相当に深刻と考えるからだ。言うまでもなく『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(村上春樹著)のことである。
ためらった理由を先に明らかにする。こんなことを考えたからだ。
――ひょっとしたら、わざと愚にもつかない作品を書いたのではないか。つまり、文化的に質の低い書籍、歌、ドラマなどが流行してしまう時代への痛烈な皮肉。たとえば「AKB」とかお笑い芸人とか。とするなら、単純に駄作としての批判はあたらない――
ハルキストとまでは言えないまでも、それなりに私は村上春樹のファンだった。『海辺のカフカ』を読んだとき、いよいよ「生と死のあわい」にぎりぎりと迫っていくのかと興奮した。『アフターダーク』をはさみ、満を持して登場した『1Q84』。読み進めるうち「直感」がキーワードであることはわかった。あの世とこの世を結びつける「直感」。さてどうなるのかと心臓を高鳴らせたのも束の間、あれよあれよという間に作品は破綻した。
それだけに、今作は失地回復を狙ったはずだから斬新な村上ワールドが展開されるのではないかと淡い期待を抱いた。ところが、結果は目を覆うような作品。ストーリーも人物設定も表現も、何もかもが街場の文章スクールに通い始めたばかりの大学生が書いたような代物だ。あまりのことに、「痛烈な皮肉」ではないかという発想が浮かんだのだ。
冷静に考えれば、ノーベル文学賞に最も近いとされる作家がそんな冒険をするはずはない。まことに残念だが、どんな経緯があったかは不明ながら、駄作がそのまま単行本化され、しかも超ベストセラーになってしまったというのが真実なのだろう。
『週刊金曜日』書評欄で、対馬亘さんが同書についてこう書いていた。
〈ここにあるのはメッセージではない。ただのマッサージだ〉
なるほどと膝を打った。メッセージがないから、ただのマッサージだから100万部売れたのだ。「AKB」人気も納得がいく。さらにそこを延長していけば、小泉純一郎、石原慎太郎、安倍晋三と続く“人気”政治家たちの謎が解明される。彼らにメッセージはなく、持っているのはただ、市民を解きほぐすマッサージの技術だけなのだ。(2013/6/14)