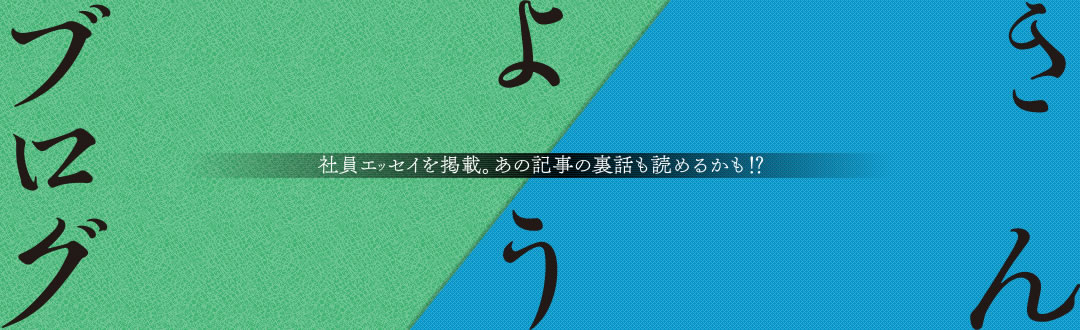[この国のゆくえ20……福島の子どもたちを救えなければ、この国に未来はない]
2011年7月21日5:52PM|カテゴリー:多角多面(発行人コラム)|北村 肇
〈北村肇の多角多面(39)〉
福島県の小さな子どもを持つ女性がこんな話をしていた。
「子どもたちは福島出身ということを隠しながら生きるしかないのかもしれません。結婚にも支障が出るでしょう」
チェルノブイリ事故の後、障がい児・者は一層の差別に襲われた。「放射性物質の影響で障がい児が生まれる」といった、人間に対する愛もデリカシーもない報道が平然と垂れ流されたのだ。なぜ、いつも「弱い者」が犠牲にならなくてはならないのか。冒頭の「お母さん」の話を聞きながら、“原子力村の住民”に対する怒りが改めて沸き上がってきた。
ある出来事を思い出す。
その中学校は合唱がうまいと評判だった。地域の合唱コンクールを間近にした日、A子さんのお母さんが担任に呼ばれた。「お子さんをコンクールの日に休ませてくれませんか」。A子さんはダウン症だった。言葉は話せない。歌は歌えない。でも音楽は好きで、ピアノが鳴ると、笑いながら手をたたいたりリズムをとったりする。コンクールに出れば“足を引っ張る”と考えた担任が自主休校を頼んだのだ。
お母さんは泣きながら了承した。普通学級に入れる運動を長年、続け、ようやく実現したばかりだ。学校とのトラブルはなるべく避けたかった。
クラスメートがこの話を知ることになった。ある日、みんなは職員室に行き、担任に迫った。「A子さんをコンクールに出して。いままで一緒に練習してきたのだから」。子どもたちの熱意に担任は折れた。A子さんは級友と一緒にコンクールに参加、楽しそうに手をたたき、体を揺すっていたという。
差別構造をつくるのはいつも大人だ。子どもたちは翻弄され、悩む。それでも、子どもたちは、友だちを包み込む愛情を心一杯に持っている。
市民団体が、福島市内に住む子ども10人の尿をフランスの検査機関に送り調べたところ、全員から放射性セシウムが検出された。内部被曝の危険性が現実のものとなっている。しかし、文部科学省はこの問題に対する危機感が薄い。これ以上、小さい魂を踏みつけたり、ないがしろにすることがあったら、この国に未来はない。(2011/7/22)