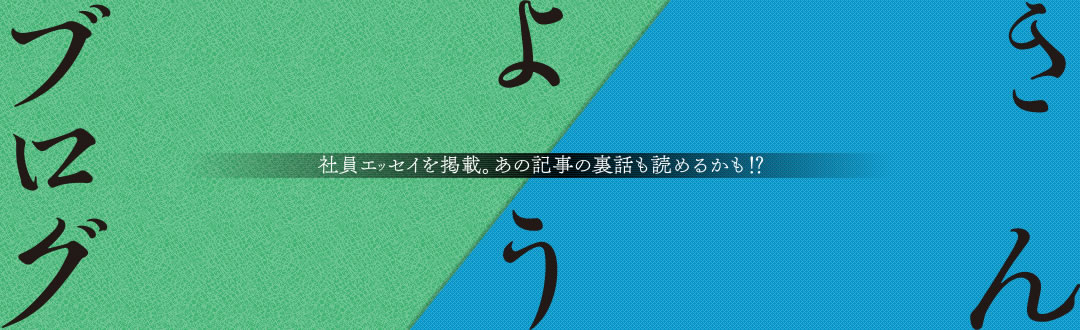所沢市まちづくりセンター設置条例についての法律関係有志の意見
2025年4月22日5:52PM|カテゴリー:風に吹かれて|admin
『週刊金曜日』2025年5月2日号に掲載した対談「よみがえれ公民館」の参考資料として、「所沢市まちづくりセンター設置条例についての法律関係有志の意見」を掲載します。
編集部 伊田浩之
所沢市まちづくりセンター設置条例についての法律関係有志の意見
2024年12月23日
所沢市長 小野塚勝俊 殿
所沢市市議会議長および所沢市市議会議員 殿
田島泰彦(元上智大学教授)
大久保賢一(弁護士)
小林善亮(弁護士)
田中重仁(弁護士)
Ⅰ 意見の趣旨
本意見は、本年9月13日制定の所沢市まちづくりセンター設置条例(以下、本条例とする)について、所沢市在住の法律関係の研究者・弁護士有志の立場から、特に、市民の自由と権利に深くかかわる公民館の使用制限をめぐって意見を申し述べ、必要な措置を求めるものである。
Ⅱ 意見の理由
1 本条例における公民館と市民の施設利用
本条例は、従来のまちづくりセンター(所沢市まちづくりセンター条例で設置)と公民館(所沢市立公民館設置及び管理条例で設置)をまちづくりセンター(以下、センターとする)として一元的に統合し、公民館については教育委員会が設置する従来の公民館ではなく、市長が設置する公民館とされ(社会教育法5条3項上の「特定公民館」)、センターはそうした公民館の機能を有する機関とも位置付けられている(2条2項)。なお、本条例の制定に伴い、既存のまちづくりセンター条例と公民館設置・管理条例は廃止される。
本条例では、センターは公民館事業も行うとともに(4条5号)、市長はセンターの施設を「市民の集会その他の公共的利用に供することができる」とされ(6条1項)、施設の使用者は市長の許可を受けなければならないと定められている(同条2項)。さらに、施設の使用制限について、市長は以下の五つの場合には、施設の使用を許可しないと定めている(7条)。
1号「公の秩序を乱すおそれがあるとき。」
2号「政治的活動又は宗教的活動に使用するおそれがあるとき。」
3号「営利を目的として使用するおそれがあるとき。」
4号「施設又は付属設備を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。」
5号「各前号に定めるもののほか、センターの管理上特に支障があるとき。」
2 住民の集会・公共利用の位置づけと意義
公民館について基本的な枠組みを定めた社会教育法は、その事業として公民館が主体となる定期講座の開設をはじめ社会教育目的での諸種の会合などを開催することなども記すとともに(22条1~5号)、公民館を「住民の集会やその他の公共的利用」に供することも示している(同条6号)。ここでは、集会はもちろん「その他の公共的利用」として住民の諸活動が幅広く捉えられており、そこには学習・教育活動や文化的活動はもとより、政治的・経済的・宗教的活動も含まれるし、少なくとも「公共的利用」の枠内であれば特定の活動分野や領域を抜き出して排除するような扱いはされていない。
こうした住民による公民館での集会や公共的利用は何よりも、憲法上主権者としての国民や住民の集会の自由(21条)や思想・表現の自由(19条、21条)、学習の自由や教育の権利(23条、26条)、政治・経済・宗教の自由(21条、22条、20条)、また憲法・社会教育法上の社会教育の自由と権利などの保障が及ぶべきものであり、また地方自治法上も、住民は正当な理由がない限り、公民館の利用を拒まれてはならず、利用につき不当な差別的取扱いもされてはならない(244条2項、3項)。したがって、住民の集会や公共的利用への不当な侵害や制限がある場合には違憲、違法のそしりを免れない。
なお、社会教育法は住民の公民館での集会や公共的利用を認める一方で、住民の公民館利用への使用制限自体を設けることは明示していない。
3 本条例における施設使用制限の問題点
これまでの検討から、公民館での集会や公共的利用は、社会教育法や地方自治法だけでなく憲法上のさまざまな人権に裏付けられ、支えられる住民の重要な自由と権利にほかならないので、その規制や制限は必要不可欠でかつ最小限に限られるべきである。これも踏まえて、本条例の施設使用制限をめぐり問題点を記したい。
(1) 本条例では施設使用について、利用者はあらかじめ「市長の許可を受けなければなら」ず(6条2項)、市長は所定の項目に該当すると認めるときは、「施設の使用を許可しない」とされている(7条)。こうした施設使用の許可制は表現行為への事前規制にあたり、憲法上、検閲(21条2項)や事前抑制(同条1項)の禁止に触れるおそれがある。許可制自体の問題性は置くとしても、許可制を前提とする場合には、少なくとも、3の冒頭で示した(「必要不可欠でかつ最小限」)よりもさらに、使用制限の要件を厳格に絞り、限定することにより、住民や利用者の集会や公共的利用の自由をできる限り広く認め、保障する必要がある。
(2) 本条例は、不許可の対象となる使用制限として、五つの場合を列記しているが(7条1号~5号。規定の全文は1の末尾参照)、全体として、3の冒頭や(1)での要請を満たすものとは言い難く、市民の集会や公共的利用の自由を不当、過剰に侵害する危険が高く、違憲・違法の疑いが強いものが少なくない。
使用制限の目的の観点から見ると、第一に、管理的規定と分類される1号、4号、5号の三つがある。そのうち、施設・設備の毀損、滅失のおそれを定める4号には、施設等の損害の程度・規模など限定する余地はあり得るものの、施設の物理的管理の観点から使用制限の目的は明らかで合理性も認められよう。
これに対し、「公の秩序を乱すおそれ」を定める1号とセンターの管理上の支障を定める5号には問題がある。1号は憲法の「公共の福祉」とも異なり、戦前の治安的な警察規制の発想が窺え、市民や住民の正当な活動への抑圧に向かう危険があるだけではない。現に、抽象的で広漠とした文言の故に制限の範囲が不明確で無限定であり、また「秩序を乱す」支障や「おそれ」の程度も問うことなく許容しているため、市民の集会や公共的利用の自由への制限を広げ、重大な脅威を与えかねない規定である。
また、センター(公民館)の管理上の支障を定める5号は、管理規定としての目的には沿うものの、条文上「前各号に定めるもののほか、センターの管理上特に支障があるとき」との文言はあまりに包括的であって、管理の支障内容と範囲も特定、限定していないため、規制が無限に広がる余地を残し、利用者の集会や公共的利用を制約する危険がある。
第二に、利用者の活動制限を目的とする規定として、「政治的活動又は宗教的活動に使用するおそれがあるとき」(2号)と「営利を目的として使用するおそれがあるとき」(3号)が本条例7条に記されている。
同種の規定は廃止された公民館設置・管理条例9条3号(営利目的行為)および同5号(法における使用制限)にもあり、小野塚市長は5号における「法」とは社会教育法23条を指しており、今回の条例では「『社会教育法』を参照する表記を分かりやすくするため、他の自治体を参考に改めた」と回答し(「所沢市小野塚勝俊市長への公開質問状について(回答)」2024年9月13日配信。なお、同回答は9月5日付「所沢の公民館を考える市民の会」からの公開質問状への返答である)、同じく市当局者も同法23条の趣旨を盛り込んだ旨説明している(東京新聞2024年9月12日付、毎日新聞同年9月14日付けなど)。
この社会教育法23条は、「公民館の運営方針」の見出しのもと以下のように記している。「公民館は、次の行為を行ってはならない。(1)もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。(2)特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すこと。 2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない」。
この条文上明らかなことは、あくまでも所定の営利的、政治的、宗教的諸行為を公民館が行うことを禁じているのであって、住民の公民館の使用や利用それ自体を禁止、制限する文言でも趣旨でもないことであり、現に、社会教育法のどこにも住民の公民館利用を制限する条文は見られないことに留意が求められる。住民のため公共的な活動を提供する公民館を維持するうえで、営利追求の自制と特定の営利事業への援助禁止や政治的・宗教的中立性確保のための政治的、宗教的活動の禁止を公民館に課した同法23条には理由がある。
他方で、集会や公共的利用の自由と権利の担い手である住民への使用制限は正当な人権規制として許される仕組みかどうかを別途吟味し、規定を設けるべきであって、同法23条が禁ずる公民館の行為をそのまま住民の利用制限の適用対象とし、その制限の根拠に据え、その制限に準用、拡張するのは妥当ではない。したがって、社会教育法をそのまま適用する前公民館設置・管理条例9条5号や、同法23条の趣旨とは異なる前提のもと立法化された本条例7条2号は、規定の正当な根拠や合理的な説明が難しいと指摘せざるを得ない。
なお、同法23条をめぐっては、文部省や文科省からその解釈について回答や事務連絡が公表されてきたが(昭和30年2月10日文部省社会教育局長回答、平成30年12月21日文科省総合教育政策局地域学習推進課(依頼)、平成27年6月19日公民館を政党・政治家に貸し出すことに関する福田昭夫衆院議員の質問への政府の答弁書)、いずれも社会教育法23条所定の公民館の行為禁止をより具体化するために作成された文書と考えられるので、同条と同様に、住民の使用制限の根拠やルールのため安易にこれらに依拠することは避ける必要がある。
以上のような社会教育法23条との関りは別としても、政治的・宗教的活動の使用制限(7条2号)と営利目的行為の使用制限(同条3号)自体が、そもそも使用制限規定として妥当か否か、人権への制約の観点も踏まえ、慎重な吟味が求められる。
政治的活動は言論・表現の自由や思想の自由、また宗教的活動は信教の自由、さらに営利活動は経済的自由のそれぞれ憲法上保障の対象となる市民の重要な行為に他ならない。政治活動はもとより宗教活動や営利活動も含め、人権や民主主義に欠かせないものであるので、住民の集会や公共的利用にとってそうした諸活動はまずもってその自由の確保が優先され、重視されるべきであるにもかかわらず、規制目的のためにあまたある使用制限事由の中から自由と人権に支えられる政治的、宗教的、営利的活動をあえて抜き出し、制限の対象に据える本条例の制度設計そのものに違和感を覚えるし、これが正当な使用制限目的に適うと言えるのか、説得的な説明が求められる。
仮に規制目的がクリアーされるとしても、制限の対象が憲法上の自由と人権の保障を受ける政治活動や宗教活動、営利活動である以上、それらへの規制は無条件で無限に許されるわけではもとよりなく、妥当な範囲や程度の枠内で認められる規制でなければならない。特に、政治活動や宗教活動に深く関わる表現の自由や信教の自由を含む精神的自由への規制に対しては厳格な基準とチェックが求められ、やむにやまれぬ必要最小限の規制でなければならないと一般に指摘されてきた。
この点、7条に記されている「政治的活動又は宗教的活動に使用するおそれがあるとき」(2号)と「営利を目的として使用するおそれがあるとき」(3号)の規定内容は、規制対象となっている「政治的活動」や「宗教的活動」および「営利を目的」が包括的で無限定なため、あらゆる政治的、宗教的、営利的諸活動が使用制限の網に収められる可能性があるし、また活動や「おそれ」の程度を問うことなく一律に規制がなされている点も無制限の使用制限の許容に拍車をかけている。先に記したように、営利的、政治的、宗教的諸行為を公民館に禁じている社会教育法23条は(それを具体化した文科省等の通知や政府答弁書も)、規制の範囲を具体的に特定しており、こうした諸行為への公民館の関与を全面的に禁止するものではもちろんなく、むしろ特定の禁止行為を除いて関与の余地を広く是認している。管理・運営する公民館側さえ営利的、政治的、宗教的関与の余地を残しているのに、本条例7条の2号と3号が、公民館を利用し、人権の保障を受ける住民に対して、営利的、政治的、宗教的活動のおそれを理由に集会や公共的利用を幅広く制限でき、そうした活動の余地を狭める危険が否定できないのは、不合理であり、説得性を欠くと言わざるを得ない。
いずにしても、7条2号と3号の使用制限規定は、集会や公共的利用を著しく侵害する危険があり、憲法の集会の自由をはじめ表現、学習、思想信条、信教、営利にわたる諸自由を深刻に脅かし、地方自治法が定める公の施設利用の拒否や差別的待遇の禁止にも触れる危険がある。
(3) 前記(1)で述べたたように、本条例では、使用制限規定を適用して住民の集会・公共的利用を不許可とするのは市長である(7条)。1で記したように、本条例の制定により教育委員会が設置・管理する従来の公民館から市長が設置・管理する公民館(特定公民館)へと変わることに伴って、許可権限行使者も教育委員会から市長へと変更になったからである。
公民館をはじめ社会教育施設を教育委員会が所管することの意義や特性については、かねてより、首長からの独立性と政治的中立性の確保、合議による中立的な意思決定、地域住民の意向の反映と意思決定などの重要性が指摘されてきた(例えば、文部科学省HP参照)。この点は、使用制限許可についても当てはまる。市の政策への批判的な意見表明も含め、集会の自由や教育・学習の自由など住民の権利を確実に保障し、施設での住民の集会や公共的利用をより広く確保するという視角からは、許可権限を行使するのは市長より教育委員会のほうが相応しく、望ましいからである。したがって、施設の使用制限につき市長に許可権限を与えた本条例7条には住民の集会や公共利用の自由と権利への制限を強める可能性があり、その前提となっている特定公民館への移行・制度化自体も、住民の自由や権利保障の観点からその必要性の再検討を求めたい。
なお、首長が設置・管理する公民館(特定公民館)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条1項や社会教育法5条3項にもとづいているが、もとよりその設置自体は自治体の判断に委ねられており、自治体は従来どおり教育委員会が設置・管理する公民館を維持できるのは言うまでもない。
4 必要な措置の要請
以上から、本条例7条が定める使用制限規定は、4号を除き、1号、2号、3号、5号の各号とも住民の集会や公共的利用の自由を不当に侵害し、憲法の人権諸規定や地方自治法の公の施設ルールに違反する危険があり、とりわけ政治活動を理由とする使用制限規定は違法性、違憲性が顕著であり、特定公民館に伴う教育委員会から市長への許可権限の移行は、集会や公共的利用の制限を強める可能性があると指摘してきた。
したがって、少なくとも先に指摘した使用制限の諸規定と市長の許可権限行使規定(前提となる特定公民館への移行も含め)部分については、そのままで本条例を施行するのはもとより到底許されない。また、本条例の規定をそのまま存置した上で内部的な運用や規則でカバーする手法も十分とは言い難く、事柄の性格上簡単な語句修正や部分的な改善で済ませられるべきでもない。憲法や法律に裏打ちされた集会や公共的利用の自由の観点から正面から使用制限項目自体の削除や抜本的な改善にもとづく再制定化が不可避である。
市長と市議会議長および議員諸氏には以上の点をご検討いただき、適切な措置を取られるよう要請する。