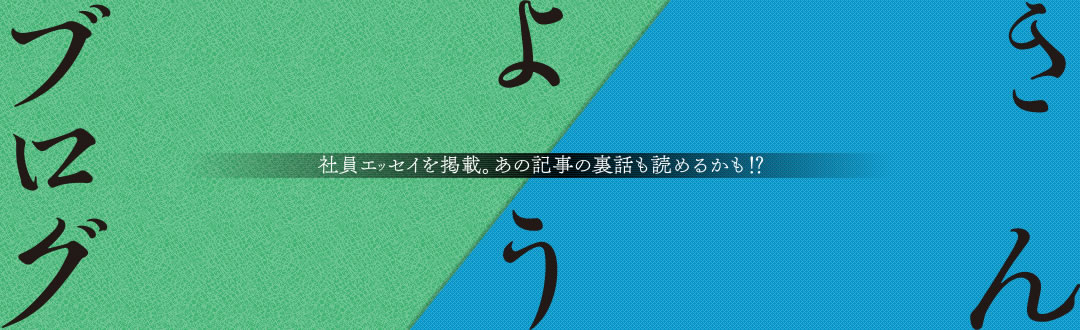格闘する“格闘する思想”
2009年11月5日4:49PM|カテゴリー:からみ|Karami
久々の掲載になった「格闘する思想」
今回は現代アラブ文学研究者の岡真理さん。(『週刊金曜日』773(2009年10月30日)号)
今回も読みごたえのある6ページ掲載です。
(担当によると、「それでも全然収まりきっていない」らしい。)
読み終わった感想は、「一度、カナファーニー読んでみるか。」
(カナファーニーは岡真理さんが、アラブ文学との運命的な出会いを果たしたという作家。)
「大学一年の時に出会ったカナファーニーの衝撃でこの三○年近くずっとやっている」
というほどのすごさに興味がわきます。
岡さんの文学に対する、また、アラブ世界に対する思いがじんわりと伝わって、読書の秋にまた文学の力を感じたくなる対談でした。内容については、原文を読んでいただくに限りますが、この文章の題名の“格闘する”の一部に含まれる、ロケ場所探しに格闘する担当の苦労話。
このシリーズはいつも屋外でのゲストの方の写真が載っていますが、この撮影がかなり大変なようで、公園などでも許可が必要だったり、許可を取っているのににらまれたり、有名な場所だと撮影料がかかったりと、少ない予算の中、自転車でロケハンに走り回っているそうです。いい場所ご存じの方は、ぜひ教えてあげてください。
(カナファーニーの今に手に入る著作
「ハイファに戻って/太陽の男たち (単行本) 」河出書房新社 ISBN-13: 978-4309205182 )
これまでの“格闘する思想”リスト
格闘する思想 萱野稔人(上) いま、考えるべきは「暴力の運動」だ(『週刊金曜日』637(2007年1月12日)号)
格闘する思想 萱野稔人(下) 国家の暴力にいかにリアリティをもてるか(『週刊金曜日』638(2007年1月19日)号)
格闘する思想 海妻径子(上) 国家・産業とジェンダーとの随伴関係を問う(『週刊金曜日』655(2007年5月25日)号)
格闘する思想 海妻径子(下) 〈やりがい〉や〈自由さ〉が搾取される労働の場でいかにたたかうか(『週刊金曜日』656(2007年6月1日)号)
格闘する思想 廣瀬純 闘争性を発動させるために(『週刊金曜日』684(2007年6月1日)号)
格闘する思想 本田由紀 階層的エゴと資本の放恣が渦巻く社会を打開するすべは(『週刊金曜日』702(2008年5月16日)号)
格闘する思想 白石嘉治 交換のロジックを断ち切り世界の無償性を拡大せよ(『週刊金曜日』732(2008年12月19日)号)