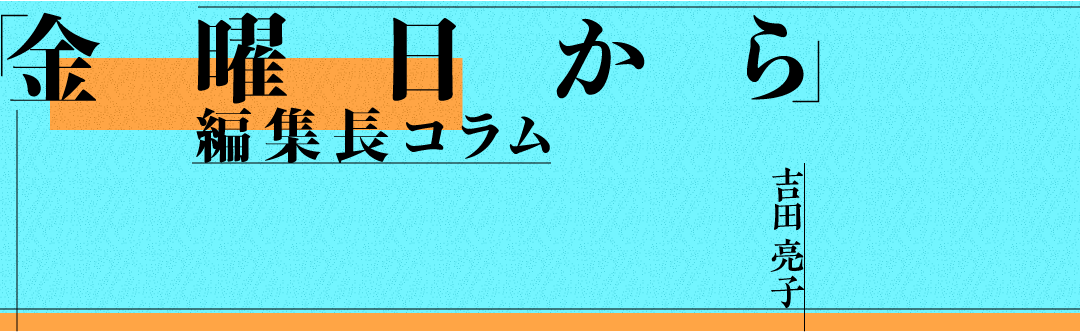故郷は他にない
2025年2月21日7:00AM|カテゴリー:一筆不乱|admin
今号で取り上げたドキュメンタリー映画『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』。ヨルダン川西岸の南端、マサーフェル・ヤッタではイスラエル軍が1週間に1軒の割合で村人の家を壊していく。しかし負けてはいない。村人は夜のうちにまた家を建てる。
はじめはそんなことを繰り返していたが、そのうち軍は大工道具を取り上げ、学校を壊し、鶏小屋や井戸を壊し、日常を壊して、この地で生きていけなくなるような仕打ちを続ける。先祖代々ここで生きてきた村人たちが、いったい何をしたというのか……。
映画の出演者で撮影者で監督の若者たちが「もっと撮らなきゃ」「書かなきゃ」と焦る場面がある。報道しなければなかったことにされると。一方で、これ以上活動を続けたら逮捕・拷問されるかもしれないという恐怖とも闘う。
以前「君が代不起立」で東京都教委に抵抗する都立学校の元教師、根津公子さんが、今の日本で抵抗しても命までとられるわけじゃないから、と言っていたのを思い出す。(吉田亮子)