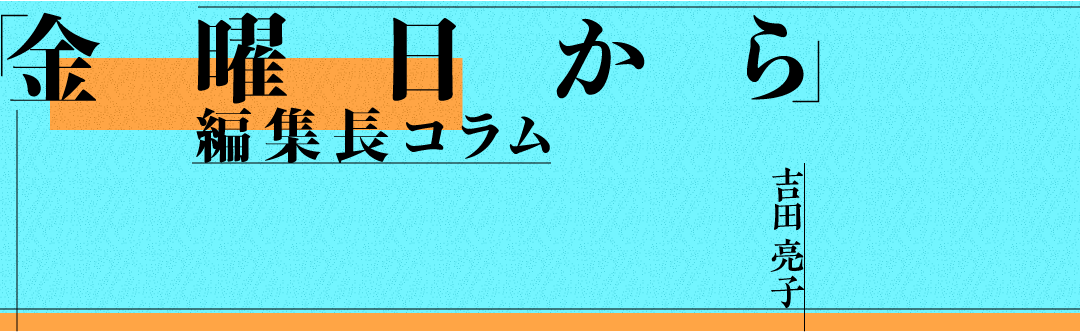今年も憲法大集会に出店
2025年5月2日7:00AM|カテゴリー:一筆不乱|admin
「子ども・男子を産まないことが、これほどまでのバッシングを許すこの天皇制社会を、皇太子夫妻を擁護する立場からではなく、どのようにきちんと批判できるのか」
当時の騒動に対する桜井大子さんのこの問いは自らの問題としてきたからこそ出てきた言葉だろう。「天皇制」は引き続き次週も取り上げる。
憲法特集では「前文」を中心に平和的生存権や国際協調主義について植野妙実子さん(中央大学名誉教授)に語っていただいた。その植野さんが登壇する集会がある。
5月3日(土・休)11時~/パレード14時半~、東京・有明防災公園(りんかい線国際展示場駅4分、ゆりかもめ有明駅2分)で行なわれる「未来は変えられる!戦争ではなく平和なくらし!2025憲法大集会」(平和といのちと人権を!5・3憲法集会実行委員会主催)。今年も金曜日はブースを出店するので、ご来場の際はぜひお立ち寄りください。(吉田亮子)