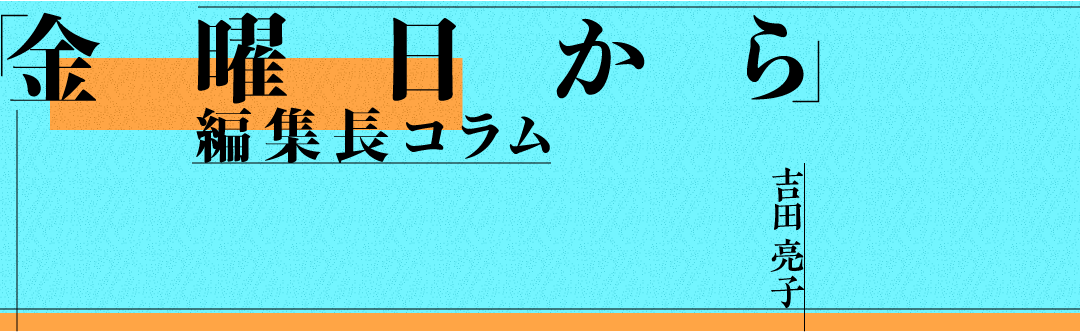この欄で多用している言葉の一つは「既視感」。既視感自体が既視感のようで、不感症になっていくのが怖いほどだ。自民党の派閥抗争が永田町をびっくり箱にしてしまい、それへの憤懣と怒りが生み出した民主党政権。それが一年もたたないうちに、またまた玩具箱をひっくり返してくれるとは――言葉もなし。
いつから政治闘争の原動力が利権と怨恨だけになったのだろう。「だけ」と強調したのは、人間社会に利権や怨恨はつきものだから、それらがまったくない永田町を夢想したって始まらないからだ。でも、甘いと言われるかもしれないが、少しは理想や理念が闘争の原動力となる時代があったような気がする。
田中角栄、福田赳夫、大平正芳――こういった政治家には野太いものを感じた。言わずもがなだが、彼らの思想や政策に賛同するものではない。ただ、私=常人とは違う「何か」を持っている。その規格外の存在感こそが一流の政治家たる所以だった。
「三角大福」の争いは現ナマの飛び交う生臭いもので、純然たる政策闘争ではなかった。しかし、それでもここ四半世紀のぶよぶよしたナマコのような戦いとは違い、どこかしら、腹の据わった武将同士のぶつかりあいという風情があったのだ。とともにというか、だからこそというか、派閥選挙に対する野党の批判も迫力があった。
一連の「菅直人対小沢一郎」騒動は、自民党与党時代に何度も繰り返された学芸会と何一つ変わらない。貧困格差時代に円高、株安が加わり、市民・国民の不安は高まるばかりなのに、そんなことは二の次とばかりに代表選に走り回る。学芸会ではなく、ハツカミズミの運動会か。
一方、政権奪取の好機であるはずの自民党は、かつての社会党や野党時代の民主党に比べても情けない限り。遠くから「民主党のバカ」と叫んでいるだけで、一向に動きだそうとしない。本来なら、今こそ「我が党の経済政策はこうだ。民主党に任せていては日本が滅びる」と立ち上がるときだろう。
それにしても破天荒な政治家が減ったなとしみじみ思う。枠にはまりこじんまりとしたセンセイ同士が湿り気のある視線を投げかけ合う。いよいよこらえきれなくなると、徒党を組んで「敵」をつぶしにかかる。小物なのだ。「小・鳩・菅」みんな大差ない。嫉妬と私怨がオーラになってまとわりついている。気色悪い。(北村肇)