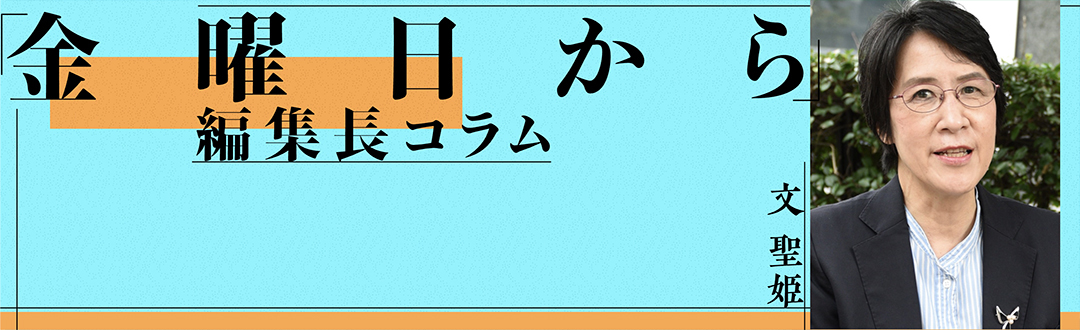市民が求めるのは、いざというときに安心して頼れる、心も度量も「大きな政府」だ
2005年9月30日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
日本は世界で5番目に貧困率(国民平均の半額以下の所得しかない家計の率)の高い国だ。15・3%というのは、10年前の約2倍という。OECD(経済協力開発機構)の調査によるもので、ちなみに上位(下位?)の4カ国はメキシコ、米国、トルコ、アイルランド。もっとも貧困率が低いのはデンマークで4・3%となっている。
また厚生労働省によると、日本の世帯別所得水準は、80年代前半は上位2割と下位2割の差が10倍以内だった。それが90年代後半から急激に広がり、02年には168倍に達したとされる。一方、メリルリンチ日本証券の調査では、資産が100万ドル以上ある世界の億万長者の約6人に1人は日本人だという。日本が「一億総中流」というのは、遠い遠い昔の話。今や、米国並に「貧富の差の激しい国」なのである。
だが、政府が貧困率を下げようと努力している様子はまったく感じられない。むしろ、「稼げないのは自己責任」とばかりに、低所得層を切り捨てようとしている。定率減税の廃止、所得税アップ、年金改悪等々、あげたらきりがない。
錦の御旗は財政再建だ。日本の赤字は800兆円に近づき、このままでは「倒産」しかねない、だから痛みは我慢してほしい――。冗談ではない。
赤字国債発行は抑えるとの公約を平気で破り、「大したことはない」と開き直ったのは誰か。その張本人が、「郵政民営化で経済は活性化」という錬金術まがいのデマで国会を略奪した。今週号で特集したように、郵政を民営化すれば市場に大量の資金が市中に流れ、結果として経済成長が高まるなどというのは、何一つ根拠のない絵空事だ。
そもそも郵貯のカネを担保に借金を重ね、国家財政を破綻した責任はどうなる。市民が郵便局に預けたお金を運用しなければ国家の運営ができない、そんな歪んだ財政構造にしてしまったことを反省し、それこそ「抜本的な改革」をしない限り、「倒産」は防げないはずだ。
しかも、郵政民営化は米国の後押しで進められたものであり、郵貯マネーに触手を伸ばしている米国企業が背景に潜んでいることは自明になりつつある。財政破綻のツケは国民に回したうえ、米国だけを潤すというのなら、永田町も霞ヶ関もいらない。市民が求めるのは、「小さな政府」でも「効率的政府」でもなく、いざというときに安心して頼れる、公正で、心も度量も「大きな政府」なのである。(北村肇)