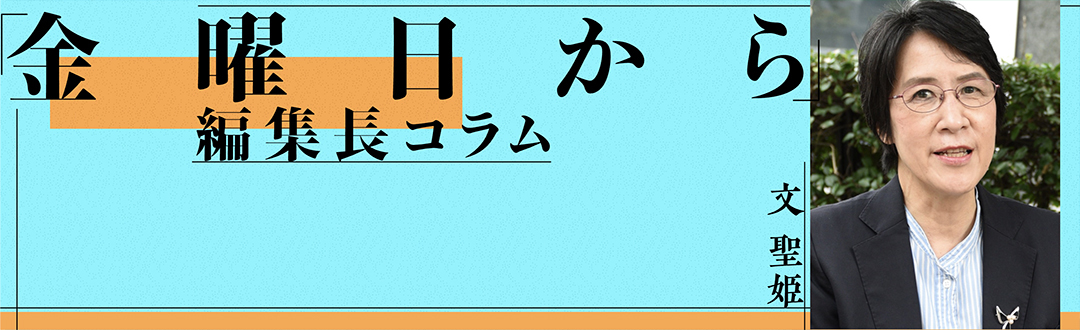世界には、「老老介護」という言葉すらない国もある
2009年6月26日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
病室からツバメの親子が見える。末期ガンの母親は死の間際、それが楽しみだと話していた。後で気づいた。ベッドからのぞける外の世界はごく限られている。病院の壁にわずかな空。ツバメは、生きとし生けるものの象徴だったのだろう。考えてみると、母親、養父、祖父母、みんな病院のベッドで最後を迎えた。
ぎりぎりまで医療を続けたいという思いはあった。だが、その前提に、自宅介護をしたくても現実には無理というあきらめがある。「部屋がない、人手がない、周到なケアができない」のないないづくし。では、もし十分な資産があったらどうなのか。あるいは可能かもしれない。絵空事をいえば、医師を雇い自宅を病院化することもできる。
高齢化社会に老老介護の問題は避けられない。しかも、大家族制や地域ネットワークの崩壊が重なり、孤老が孤老を支えざるをえないケースは激増する。介護には気力と体力が必要だ。どちらも欠けつつある高齢者にそんな重労働を求めるのは酷である。厚生労働省の調査によれば、07年度、介護者による殺人は13件、介護者と被介護者の自殺は4件を数える。老老介護の事例も含まれている。介護疲れによる事件という悲劇は、これからも絶えることはないだろう。
妻で女優の南田洋子さんが認知症となった長門裕之さんの本が話題になっている。『待ってくれ、洋子』。多くの感動を呼ぶとともに痛烈な批判にさらされる。「認知症の妻をさらし者にした」「裕福だから自宅介護ができるのであり、庶民には手の届かない話」……。
本誌今週号「老老介護」の特集で、中山千夏さんが長門さんにインタビューした。その中で、長門さんはこう語る。
「(講演会では)いつも最初に『僕と皆さんの介護の仕方は違います』と。『僕は役者だし、収入があなた方とは少し違う』と言うことにしている。だけど、介護で実感した体力の消耗などについて話す意味はあるわけで」
確かに、「1人月20万円で3人のお手伝いさん」を使っての介護は、一般の市民にとって高嶺の花である。しかし、真に批判されるべきは、長門さんではない。「安穏たる死」をすべての市民に保証できない、日本という国家だ。虫の目で現実を見れば、病院で看取られるのは、むしろ幸せとさえいえる。一方で、世界には、老老介護という言葉すらないデンマークのような国もある。憲法25条を絵空事にしてしまったのは誰か。(北村肇)