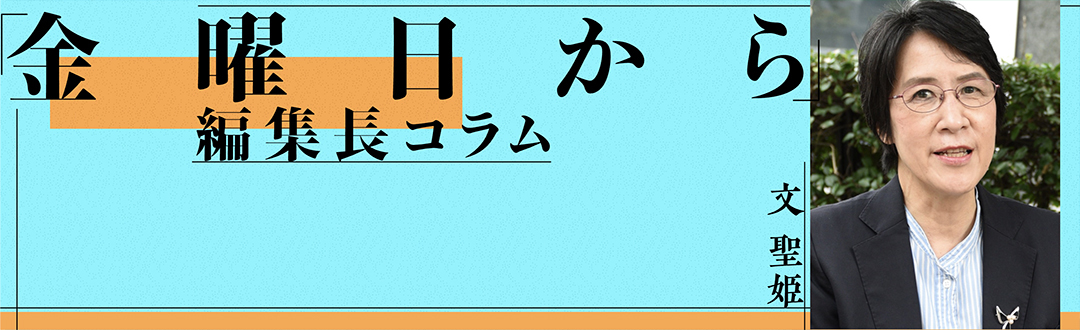「死刑」に市民を関与させる残忍無比な裁判員制度
2010年5月14日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
袴田事件を題材にした映画『BOX 袴田事件 命とは』を観た裁判員は、果たして死刑判決に関与できるだろうか。1966年に静岡県で起きた強盗殺人放火事件の”犯人”とされた袴田巌さんは一貫して無実を訴えている。だが80年に死刑判決が確定。弁護団は再審請求したが08年に最高裁は棄却。直ちに第二次再審請求が静岡地裁に出された。
本誌も典型的な冤罪として何度か取り上げてきた。死刑判決に関わり、判決言い渡しの7ヶ月後に辞職した熊本典道元裁判官が07年、「彼は無罪だ」と表明し、話題にもなった。作品では、いい加減な捜査や自白の強要ぶりが、袴田さんと熊本さんを軸に克明に描かれている。冤罪どころか警察による意図的なでっち上げではないか、という疑いも暗示される。死刑という制度の危うさが、くっきりと浮かび上がる映画だ。
「足利事件」の冤罪被害者、菅家利和さんは無期懲役刑から生還した。もし死刑判決が出され執行されていたら、と考えると身の毛がよだつ。92年に発生した「飯塚女児2人誘拐殺人事件」で、やはりDNA鑑定をもとに逮捕され死刑判決を受けた久間三千年さんは、「足利事件」が問題になっているさなかに刑場の露と消えた。冤罪を主張してきた弁護団がDNA再鑑定を求めていたにもかかわらずだ。
人は人を裁けるのか――。答えのない煩悶の中から人類がつくりだしたのは、人を裁くための「法」だった。だが「法」を扱うのは人であり、「法」は人によっても、人を支配する権力によっても、ぬえのような存在を余儀なくされる。かくして「人は人を裁けるのか」という難問はちゅうぶらりんのままとなる。
そこで、「法」を不動のものとするため、裁判官は「人ではない」ことを要請された。週刊誌は読まず、ワイドショーは見ず、ということを実践している裁判官もいるという。血や涙とは肉とは無縁の「裁判機械」として「法」を解釈するためだ。
死刑判決を出した裁判官が、なぜ精神の均衡を保てるのか。それは「機械」に徹するからだ。逆に言えば、そのような人間にしか務まらない。だが、たまたま抽選に当たった裁判員は血も涙もある人間だ。彼や、彼女が、人一人の命を奪う、しかも常に冤罪の危険性を包含する死刑に関与したとき、どれだけの精神的負荷を負うことか計り知れない。そしてそのケアは一体、だれがしてくれるのか。この観点も忘れられたまま、制度は始まった。
死刑と同様、裁判員制度もまた残忍無比な制度である。(北村肇)