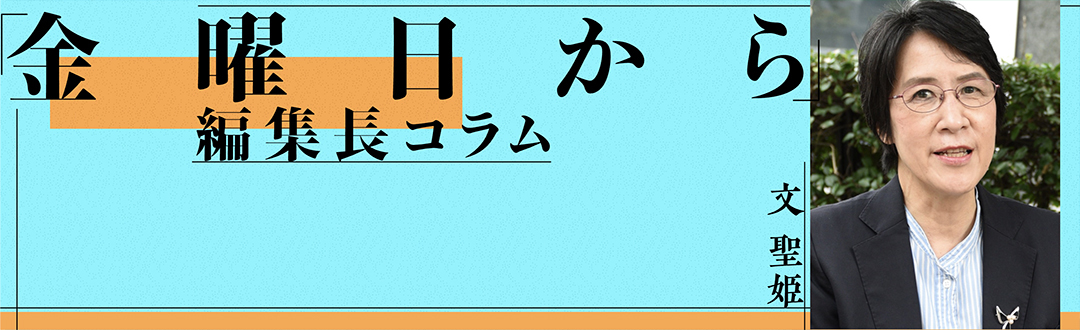「巨大な国家が小さな生活を踏みにじる」が暴力ダムの本質
2008年12月12日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
三峡ダムを舞台にした映画『長江哀歌』をご覧になった方も多いだろう。30代の巨匠、ジャン・ジャンクー監督が、ダム底に社会そのものが沈んでいくかのような、陰鬱で出口のない世界を精緻な演出で描いた。ダム計画は孫文の時代からあったといわれる。百万人以上の住民が強制移住させられ、完成は来年の予定だ。
日本のダム映画では、『黒部の太陽』が別の意味で印象に残る。石原裕次郎と三船敏郎の共同制作で話題になった。「青少年必見の映画」とされ、校庭に幕を張っての上映会も全国で開かれた。公開は東京五輪から4年後の1968年。「世紀の難工事に取り組む男たちのドラマ」は巨大開発への賛歌でもあった。
最大の国家事業である戦争への反省から始まった戦後。だが大規模な公共事業は、再び市民の「小さな生活」を国家の名のもとに奪い続けた。ダム、道路、空港……。しかも、その多くは、“賛歌”の陰で大企業や政治家の利益を生む仕掛けだった。
官僚の責任も大きい。一度決めた計画は絶対に見直そうとしない。不都合が起きたり、計画の瑕疵が見つかると、誤魔化しに誤魔化しを重ねていく。本誌今週号で特集した八ツ場(やんば)ダムしかり、川辺川ダムしかり。そこには「市民の利益」という発想はない。自らの保身がすべてに優先するのだ。
30数年前、埼玉県・秩父で自宅をダム底に沈めたお年寄りに取材した。「お国のすることだから、仕方ないよねえ」。あきらめとも寂しさともつかない表情が印象的だった。そのとき私の頭をかすめたのは「まだこの国は戦争を引きずっている」という事実だった。国家は依然として市民に優先し、お上に楯突くことは許されない――。
だが、ダムをめぐる闘いは、全国各地で火を絶やすことなく続いた。そして今年、熊本県知事に就任した蒲島郁夫氏は川辺川ダムに「ノー」を宣言した。大阪、京都、滋賀の各知事は淀川水系ダムの一部をめぐり、「国の言うことは聞かない」と共同歩調をとった。八ツ場ダムを訪れた鳩山由紀夫民主党幹事長は「政権をとったら計画を見直す」と明言した。不確実性をはらみながらも事態は動き始めている。
市民を踏みつけにする暴力ダムは、「太陽」ではなく「哀歌」を生む。計画を破棄し、自然を守り、「歓喜の歌」を歌うためには、市民の覚悟が必要だ。「巨大な国家の前に、小さな生活を優先する」社会を、自分たちの手で作り上げるという覚悟が。(北村肇)