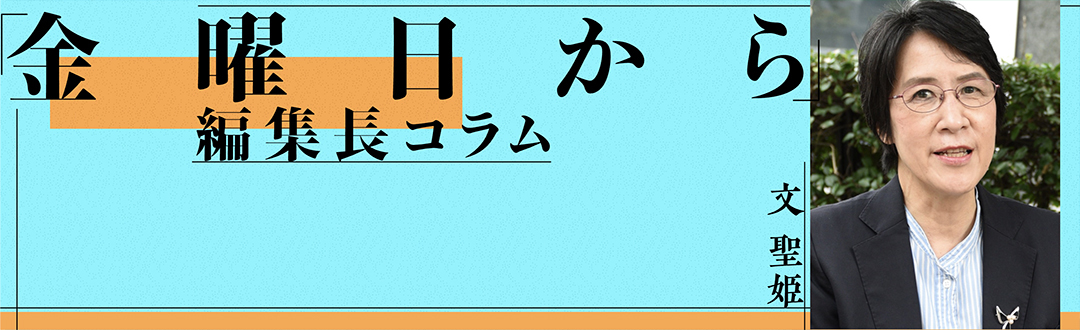新自由主義崩壊を前に15周年を迎えた本誌。「人間へのやさしさ」を基盤にしたい
2008年11月7日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
「ミーイズム」とか「自己中」といった言葉をあまり見かけなくなった。風潮が消えたのではなく、殊更とりあげるまでもないほど、社会に定着してしまったからだ。だが一方で、「自分を愛せない」「自分の存在証明ができない」という人が増えている。若者だけではない。身近にいる中高年にも目立ってきた。
「菅井きん初めての主役」というキャッチに引かれて、「ぼくのおばあちゃん」を試写会で観た。特筆すべきものはない。やさしいおばあちゃん、若くして亡くなる父親、しっかり者の母親……。テーマもストーリーもありきたりだ。でも、監督も演技者もそれなりに泣かせるツボは心得ているから、会場からはすすり泣きが聞こえた。
「菅井きんはやはり、小意地の悪い役の方がいいな」と思いつつ、私の関心は別の所にあった。映画自体より、なぜこうした筋書きが受けるのかという点だ。「三丁目の夕日」はもろに昭和30年代だが、リリーフランキーがタイトルにした「東京タワー」もその年代の象徴である。一体、30年代にあって、いまは消え去ったものとは何なのか。
印象的には、「無償の愛」のように思う。恋愛は多くが「見返り」を求める。だが肉親の愛は、本来、無条件の愛である。とともに、「ぼくのおばあちゃん」に出てくる近所のおじさん、おばさんも「一方的に愛してくれる存在」だ。だから、安心してよりかかれる。
このような「愛」が喪失した原因はいくつもあるだろう。綿密な分析はできない。ただし、ここ数年、裸の資本主義が持ち込まれた結果、事態が悪化したことは間違いない。自分の利益しか考えない――他人が信用できない――常に疑心暗鬼に陥る――無償の愛が欲しいのに、自分にはその資格がないと思いこむ。そして、最後は「自己責任」にさいなまれ、行き場を失ってしまう。「自己中」から「存在証明のできないつらさ」への道筋だ。それこそ「本人の問題だ」と切ってしまうのは簡単である。しかし、「犯人」は別にいる。
新自由主義の信奉者はこう叫んだ。「貧しいのも、もてないのも、能力がないから、努力してないから」。違うだろう。努力してもムダなシステム、一種の奴隷制を作ったのはあなたたちではないか。「自己中」の傾向はあったにしても、最大の問題が制度にあることを隠蔽し、「お前たちがわがままだったから負け組になった」と思いこませようとしたのである。
そこに対抗するには「やさしさ」しかない。今月、15周年を迎えた本誌は、これからも「人間へのやさしさ」を基盤に置きたい。 (北村肇)