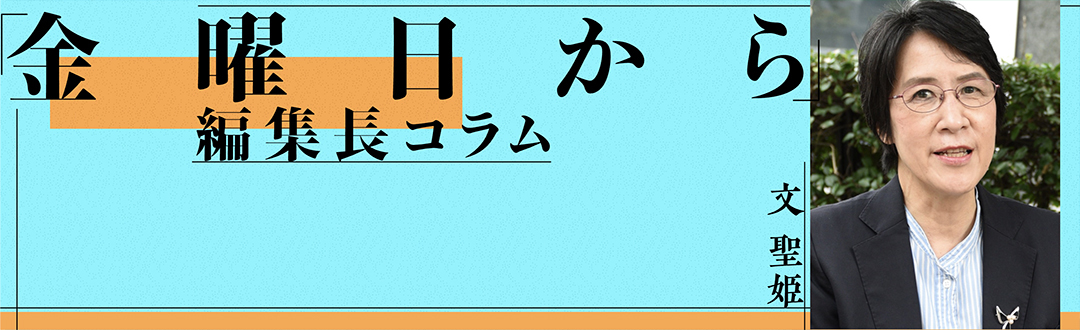ヤマ場を迎えた国鉄闘争の帰趨は、明日の日本を占う
2008年5月23日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
平日の午後でも乗客の絶えることがない、あるJR駅。たまたまホームの乗降口に近い車両に乗っていたので、降りる人のため、いったん車外に出た。さて乗り込もうとしたところ、ドアが突然、閉まりだした。あわてて両腕を差し込み、何とか滑り込んだ。私以外にも何人かが”被害”に遭いそうになった。運転手さんがほんの10秒もまってくれればすむ話しだった。
10年以上前だが、初めてソウルの地下鉄を利用してびっくりした。何人ホームに並んでいようが、時間がきたらとにかくドアを閉めてしまうのだ。「いやはや忙しい国だ」と思ったが、そのころのソウルに負けず劣らず、今の東京もせわしない。いや、東京には限らないのかもしれない。
知り合いのJR職員が尼崎事故の後、ぽつりと呟いた。「少しでも運行が遅れたら、直ちに減点ですから……」。これを聞いたとき、改めて国鉄が私企業になったことを実感した。企業論理からいえば、効率化とそれによる利益拡大がすべてに優先する。JRにとっては「時刻表通りの運行」が大前提であり、機械的に「正常運行」を遵守することがすべての職員に強制される。
国鉄民営化の一断面は、職員の機械化だ。確かに公務員はさまざまな意味で「守られている」。中には、それをいいことにさぼる人間もいるだろう。しかし、かような人間は多数ではない。21年前、産経新聞や読売新聞は「国労組合員がいかに堕落しているか」を徹底的にキャンペーンした。だが、ほとんどがデマと歪曲だったことは、本誌今週号で山口正紀氏が指摘している通りだ。
そもそも「守られている」からこそ、効率化を考えず、乗客を思いやるゆとりが生まれるのも現実である。国鉄時代には、そうした安心感があった。ラッシュ時でもないのに、乗客を置き去りにしてドアを閉めるような職員はいなかったはずだ。機械ではなく、心ある人間が運転をしていたのだから。
今週号で特集したように、国鉄闘争はヤマ場を迎えている。どういう結末を迎えるかは、日本社会の今後に大きな意味を持つ。民営化の名のもとに社会全体の「工場化」「企業化」がさらに進むのか、何よりも「人間」「命」を大切にする時代を引き寄せることができるのか。国鉄闘争の原点が「人間の尊厳」を守ることにあった事実を、もう一度、噛みしめてみたい。(北村肇)