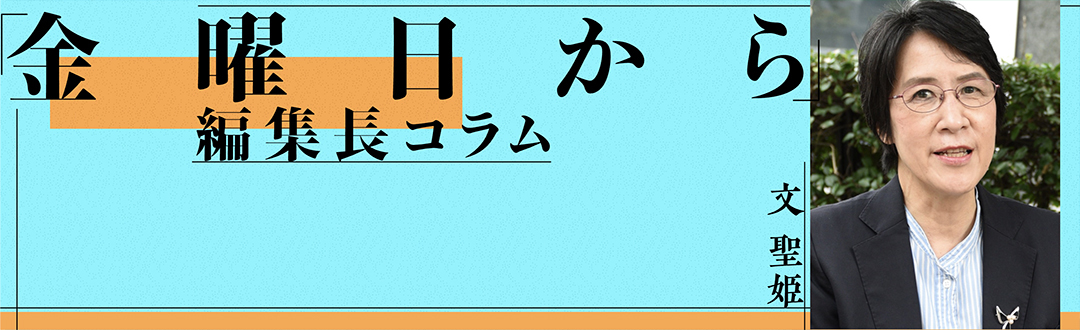和歌山カレー事件は冤罪の可能性が高い。犯人視報道のマスコミは自己批判できるか
2009年2月13日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
NHKラジオのニュースを聞いていて、何となく違和感があった。改めて注意深く耳を傾け、はっきりした。事件記事で「警察への取材でわかった」という、新しい表現が使われていたのだ。これまでは「警察への取材」と断りを入れることはなかった。発表や夜回りで聞いたことを、そのまま「事実」として垂れ流していた。新聞も微妙に書き方を変えている。いずれも、裁判員制度の導入を控え「取材源を極力、明示する」「警察べったりではありません」という姿勢を見せたいのだろう。
それがまずいとは言わない。だが、事件報道の本質は何ら変わっていない。むしろ、ひどくなる一方だ。いわゆる「犯人視報道」の人権無視ぶりは目にあまる。表現を変えた程度ですむと思ったら大間違いだ。「警察は正しい」「容疑者は一方的にたたいていい」という、ジャーナリストにあるまじき発想こそが問題であり、捜査当局から“自立”しない限りは、市民に受け入れられる報道はありえない。
「人権と報道」が社会問題化した80年代半ば、報道機関はこぞって容疑者呼称に踏み切った。「推定無罪」の原則からすれば遅すぎる感はあったが、前進には違いなかった。その後、被害者はもちろん容疑者の写真についても「極力、使わない」という方針を出す新聞社も出てきた。このような傾向が進めば、匿名報道も実現するのではないかとの期待も高まった。
しかし、オウム事件が、一瞬にしてそうした流れを断ち切った。微罪逮捕だろうが別件逮捕だろうが、「オウムでは仕方ない」が免罪符となり、平然とまかりとおった。マスコミは、捜査の行き過ぎを批判するどころか、躊躇無く、容疑者の顔写真や引き回し写真を掲載した。「犯人視報道」時代に先祖返りしたのだ。
その後は、「冷静な報道に努めよう」といった態度は雲散霧消し、メディアスクラムが新たな問題として浮上するにいたった。本誌今週号で特集した「和歌山カレー事件」も、滅茶苦茶な報道がされた典型的事件だ。幾度か報じてきたが、裁判が進むにつれ、冤罪の可能性が高まっている。しかも、ここまで捜査への疑問が明るみになっているにもかかわらず、それを追及する報道はほとんどない。そのくせ、仮に無罪判決が出れば、自分たちの責任は棚に上げ、「捜査に問題」というキャンペーンをはるのだろう。
マスコミがこんな状態で、裁判員制度が実現したらどうなるのか。裁判の場が情緒に流される「お白州」と化したら――考えただけでぞっとする。(北村肇)