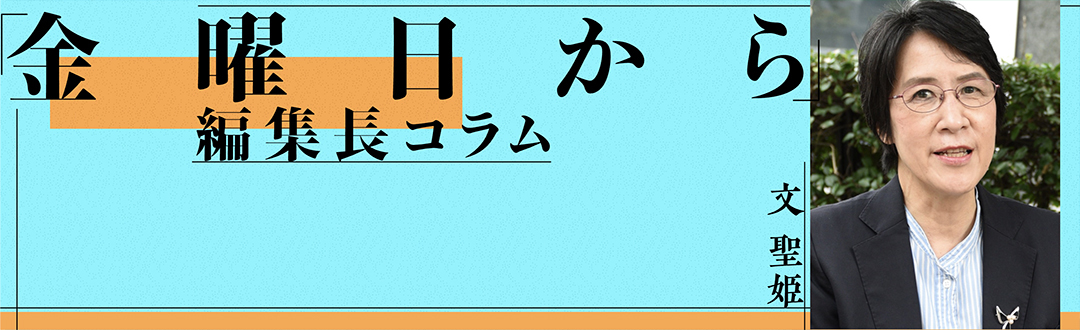非現実的でバーチャルな感じを漂わせる東京地検の捜査
2009年4月3日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
そこに沈丁花が咲いていれば、つい鼻を近付けたくなる。そこに日だまりでうたた寝する子猫がいれば、ふと撫でたくなる。嗅ぐ、触るという行為は、特に頭で考えることもなく自然のふるまいとして表れる。それはまた、視覚・聴覚の点では限りなく現実に接近するテレビやパソコンには求められない感覚である。
昔話や童話に出てくるごうつくばりは、金貨を眺めるだけでは飽きたらず、手で愛撫したり頬ずりしたりする。「血も涙もない」人間として描かれる彼らはしかし、五感をもって財宝を慈しむことで、極めて人間的存在とも言えるのだ。さて、現代、パソコンを駆使してマネーゲームに興じる現代の大金持ちが、触覚で財を愛でることはない。その代わり、液晶画面における数字やグラフの変動を目で見て、一喜一憂するのだろう。
こうなると、カネはカネであってカネではない。当然、カネをめぐる犯罪も変化する。インサイダー取引、M&Aにからんだ事件が、どこか非現実的でバーチャルな感じなのはそのためだ。
ライブドア事件や村上ファンド事件には生々しいカネのにおいがなかった。摘発した地検は、さまざまな要素・変数を組み込み、パソコン上で計算し結果を出しているようにみえた。そして、問題はこの「変数」だ。ここに何を入れるかで、犯罪が成立するかどうかという、最も基本的なことが変わってしまう。言い換えれば、検事の頭の中だけで、犯行が構成される危険があるのだ。それはつまり、犯罪をなきものにすることも可能ということである。国策捜査や冤罪の頻発は必然とも言えよう。
小沢一郎氏の秘書が起訴された事件は、マネーゲームとは直接、関連しない。だが当初から、地検の筋立てには非現実的でバーチャルな感じがした。パソコン上で、「容疑者・小沢一郎」との解を導き出すために、さまざまな「変数」を入れて計算した。そんな雰囲気が否応なく漂っていたのである。
本来、罪を裁くとは人を救うことである。被害者、関係者、市民、場合によっては、加害者さえも救済する。だが、時に国家は「体制を救う」との大義名分で無実の市民を牢につないできた。
知的エリート集団・地検は、その「血も涙もない」国家を守る風を装いながら、自らの力の誇示に汲々としているようにみえる。(北村肇)