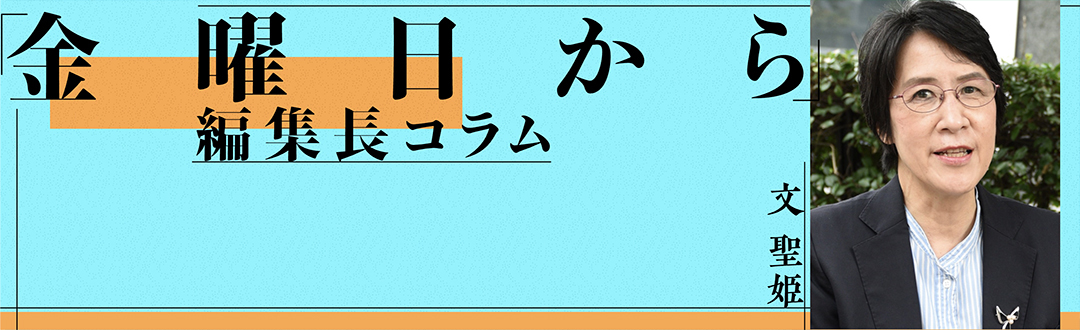『蟹工船』を読み、カネまみれになったカーテンの汚れを落とす
2008年7月25日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
編集長としての懺悔を告白したい。昨年後半、「『蟹工船』の大特集をしよう」という企画案が編集部員から出た。これを受け、本誌主催の「多喜二祭」ツアーも行なった。だが「テーマとしては地味だな」と思い、誌面での大展開はしなかった。「蟹工船」がブームになる状況を完全に見誤っていたのだ。
この不死鳥のような作品を読み、現代社会が蟹工船の「糞壺」そのものであることを実感し、総毛立つ思いだ。「丸の内」のソファーに座る一部の権力者は、労働者が「糞壺」からはい上がれないようにあらゆる策を弄し、自らの懐だけを温める。常に命の危機にさらされる労働者は、逃げたくとも、荒れた海に囲まれて行く場がない。
同じ頃、堤未果さんの「貧困大国アメリカ」を読み、感性の鈍磨ぶりをますます痛感した。米国では、「社会的弱者」の立場に追い詰められている若者を甘言で誘い、軍隊にたたき込むことが日常化している。また、少なくない中高年の経済的弱者が、イラクで職を求めるしかなくなっている。実質的な「傭兵」化である。今や、日本に限らず、世界そのものが蟹工船となっていたのだ。
戦前は、資本主義の対抗軸として社会主義・共産主義があった。旧ソ連や中国のそれが真の意味での共産主義であったかどうかは別にして、資本主義の暴走を抑止する役割を担っていたことは確かだ。『蟹工船』はそうした時代状況の下で生まれた。
だが、21世紀の資本主義は20世紀とは大きく異なっている。国民国家の枠を超えた地球レベルの資本主義である。「富める者」と「富めない者」に二極化した社会が世界を覆っているのだ。この傾向が収まる気配はない。であるなら、プロレタリア文学の再評価はさらに高まるだろう。資本主義やマルクシズムの現代的分析もますます、盛んになるはずだ。
それはまた、戦後60余年、カネまみれになったカーテンを洗う作業でもある。まっさらになったカーテンを通して、どんな光が差し込むのか。魂をとぎすまして、その瞬間を待ちたい。
遅ればせながら、今週号でプロレタリア文学の特集をした。井上ひさしさんと雨宮処凛さんの対談をぜひ読んでいただきたい。また、詳細な註をつけて『蟹工船』を復刻した。こちらも書店に並び始めたころなので、手にとっていただけたらと思う。(北村肇)