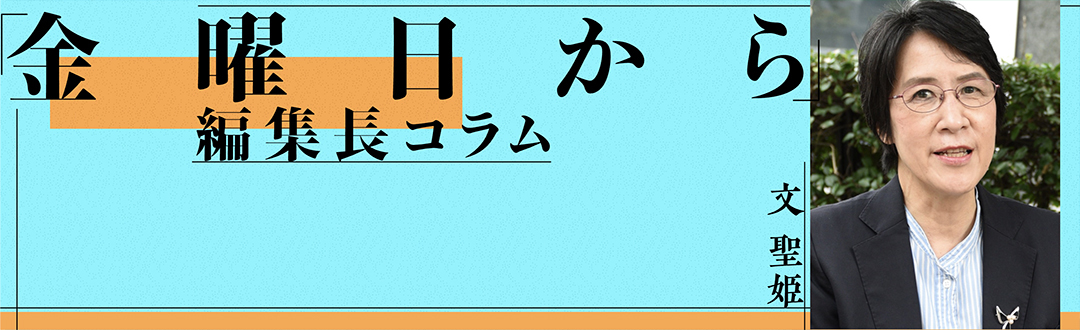課長にもなれなかった福田康夫氏
2008年9月5日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
器ではなかった、としか言いようがない。福田康夫氏はどこからみても係長タイプだった。与えられた仕事はそこそこ、ソツなくこなす。数人の部下なら使えないこともない。だが、組織の10年後を見据えたグランドデザインを描き、実行する能力はない。トップの座に就いたときから、「途中降板」は想定内だった。
福田氏の不幸は父親が「社長」だったことだ。周囲からは二世と持ち上げられ、いつしか自分も力があると勘違いしたのだろう。まだ係長の器でもなかった安倍晋三氏同様、典型的なお坊ちゃんである。それにしても自民党の人材不足には目を覆う。平社員と係長を相次いで「社長」にするしかなかったのだから。
つまり、自民党自体が与党の器ではないということだ。だれが総裁になろうと、支持率が急騰するとは思えない。有権者は福田氏を見限る以前に、自民党に愛想をつかしている。このことにも気づかないのだから、末期症状だ。
話は変わるが、高田渡、吉田拓郎、岡林信康――60年代後半から70年代初頭に跳躍した歌手が、なぜかいま、脚光を浴びている。プロテストソング、メッセージソングの復活とも言われる。だが、そうしたジャンルなら、尾崎豊やミスチルなど、その後の世代だって負けてはいない。いつの時代でも、時代や社会に抵抗する音楽は存在してきたのだ。
では、例えば本誌今週号で特集した高田渡と、桜井和寿との決定的な違いは何か。それは、高田は決してメジャーにはなれなかった、という点にある。むろん、桜井はリスナーや音楽関係者に擦り寄ったからメジャーになれたという意味ではない。そんな失礼な言葉を尾崎や桜井に投げかけるほど間抜けではない。
重要なのは、高田も岡林も素っ裸の本能をさらしていたことにある。フォークブーム時代の合い言葉は、「自分たちの歌を歌おう」だった。それにはまず、自らをむき出しにしなくてはならない。想像していただければおわかりだろうが、服を着ていない本能は、時として凶器になる。高田や岡林は、存在自体が放送禁止歌だったのである。
政治家には「自分の言葉」がなくてはならない。だれが何を言おうと、政治家としての本能で突き進まねばならないときがある。メジャー(人気者)になろうと考えることもない。むろん、市民・国民のために身を捨てる覚悟があってのことだ。たらたらと、みじめなグチを言う前に解散していれば、福田氏も課長まではなれただろうに。(北村肇)