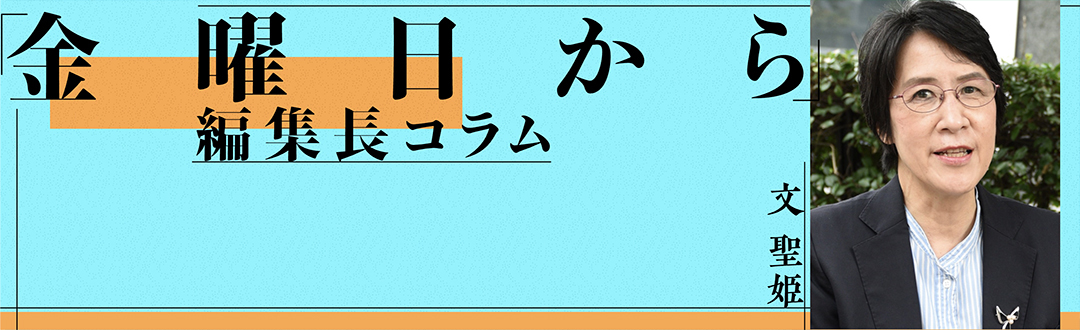「老成化」した政治家・辻元清美氏をしばらく凝視したい
2010年8月20日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
98歳の詩人、柴田トヨさんの作品集『くじけないで』がベストセラーになっている。詩集としては異例のヒットだ。生きることのしんどさは十分、わかっている、でも生きることはすばらしいのよと、無意味な飾りを施さない言葉で、淡々とおだやかに語りかける。しかも、浮世離れすることなく、常に「社会」を真っ直ぐに見据えている。世代を超えて人々の胸をうつのは肯ける。
歳をとるのも悪くないなと実感したのは50歳を過ぎてからだ。柴田さんの詩に触れ、さらに一歩進んで、歳をとることの幸せを感じるようになった。窓から入る陽の光やそよ風を手ですくいとるなどの芸当は、若いころにはとてもできなかった。確執の対象でしかなかった親に素直になれるのも「老い」のおかげだ。
本誌今週号で登場願った辻元清美さんに初めて会ったのは20年以上前。若さが全身を覆っていた。土井たか子さんの勧めで政治家になり、根っからの努力家ということもあり、めきめきと頭角を表す。だが、逮捕、議員辞職と奈落の底に。さまざまなデコボコ道を歩んだ末、連立政権では国交省副大臣という要職に就く。インタビューの中で「私は調整型」と幾度も繰り返した。確かに、激動の永田町を生き抜いたいまは、良きにつけ悪しきにつけ老成化したようにみえる。「社民党離脱」も、本人なりにしっかりした計算に基づいての行動なのだろう。
当然、賛否両論ある。現時点では、私も納得のできないことが多い。社民党の古色蒼然とした労組頼りの体質には違和感がある。しかし、それを打ち破ろうとした土井さんに請われて旧社会党に入ったのではなかったか。辻元さんに対する周辺の期待もそこにあった。野党では現実を動かせないという考え方にも賛同しかねる。政治の役割とは、現実を理想に引き上げることにある。浅薄な現実主義がマイノリティの排除につながりかねないことは、誰よりも辻元さんが知っているはずだ。
とはいっても、彼女を孤軍奮闘の立場に追い込んでしまった責任は多くの人間にある。市民運動的立場で動いていた議員はひとりふたりと社民党を去った。体質を変えようにも、現実を理想に引き上げようにも、一人ではどうしようもない。その苦境を乗り越える絶好の機会が連立政権発足でもあったのだ。
老成化が「命」への感度を高めることにつながるのか、単なる根回し上手にとどまるのか、しばらくは政治家・辻元清美を凝視したい。(北村肇)