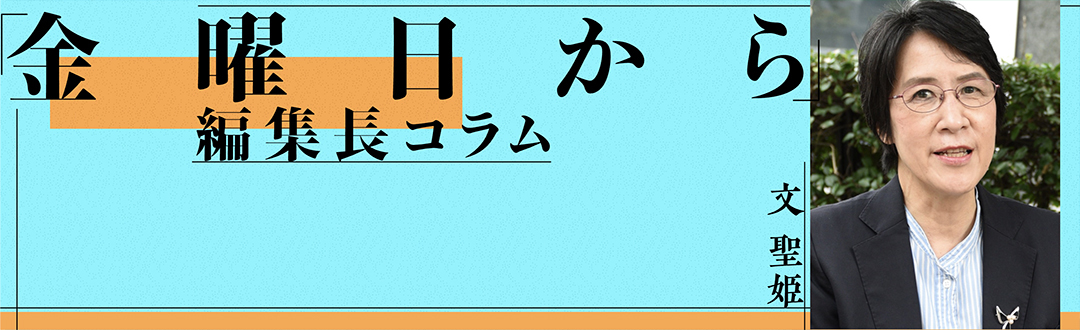薬害肝炎を放置し続けた厚生労働省の罪は「過失」ではない
2008年2月22日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
さすらい人のように見知らぬ土地をめぐってきた風が、ふと鼻腔に春を運んでくる。しっかり確かめようとしたときにはもう、気まぐれな風は冴えわたった冷気に溶け込み、あっかんべをしている。何度かこんなたわむれをしているうちに、モモやサクラが色づいてくることだろう。いつもながら春は待ち遠しい。
満開とはいかないまでも、薬害肝炎の闘いは、多くの支援者に支えられ花開いた。「よかった」という思いとともに、極寒の地に被害者を追いやり、なおかつ放置した厚労省への憤りはやまない。闘いに勝ったからといって被害者の過去が返ってくるわけではなく、厚労省の責任が溶けて消えることはありえないのだ。
本誌は一貫してこの問題を追い続けた。今週号の特集で経緯を書いている編集部員、大西史恵が、長い間、被害者や弁護団に密着取材してきた。その間、大手メディアはほとんど取り上げることはなかった。もし全国紙やテレビが徹底的に厚労省批判を展開していれば、あるいは解決が早まったかもしれない。
報道が盛り上がらないのをいいことに、厚労省は逃げ回った。いや、開き直ったといったほうが正しい。「政治判断」で事態が動きそうになったときも、「裁判の決着を待つべき」「感染者の治療費をすべて国がまかなったら、とんでもない金額になる」などと、永田町で言いふらし続けた。
まさにデジャブ(既視感)だった。エイズ問題を取材していたころ、当時の厚生省は、あることないこと言い訳を繰り返しては逃避し、救えたはずの被害者を見殺しにした。『毎日新聞』が単独でキャンペーンをはっていたときは、傲慢な態度に終始したのに、被害者の運動が高まり、すべてのメディアが報道し始めた結果、最後は非を認めた。
薬害の歴史を追うと、厚労省の“犯罪”は単なる過失とは思えない。被害が発生するたびに隠蔽、自己保身に走る。故意犯であることが露見するのを恐れるからとしか思えない。そして逃げ場が無くなると、形式的謝罪と解決金でお茶をにごす。何より、そこには、深い反省も再発防止への強い意志も感じられない。
2月27日(水)の夜、東京・阿佐ヶ谷の「Asagaya/LoftA」で、「薬害肝炎」「タミフル」をテーマにした本誌主催の講演会を開きます。関心のある方はぜひ、ご来場ください。(北村肇)