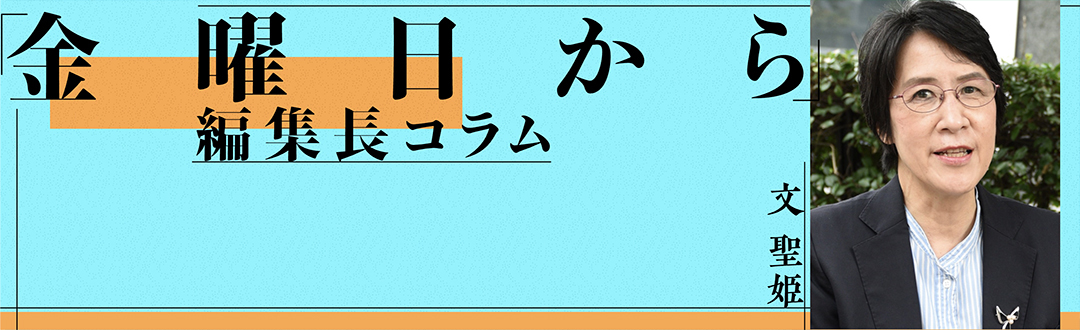『週刊金曜日』の創刊14年に誓う「言葉探し」
2007年11月2日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
「言葉」を探してきた。いまも探し続けている。「平和、自由、人権のかけがえのなさ」を伝える言葉。だれの心にも届く、やさしく、気取らず、実感のある言葉。むずかしい。一瞬、辿り着いたと思っても、するりと抜けてしまう。力のなさ、感性のなさに愕然とする。でも、あきらめない。その思いだけが支え。
創刊14年。『週刊金曜日』は、そろそろ高校生になろうという年頃に達した。だが、まだまだ成長途上。日々、編集しつつ煩悶する。「上からの言葉になっていないか」「空虚な言葉に堕していないか」「独りよがりの言葉ではないか」。突き詰めれば突き詰めるほど、「満足」は遠のく。反省とやり直しの連続。
小泉純一郎元首相の「ワンフレーズ」戦略は的中した。この事実は認めなくてはならない。「中身がない」といくら反対しても、引かれ者の小唄にすぎない。何だかんだいっても、民主主義は「数」の勝負。「護憲」は「改革」に負けたのである。
だが考えてみれば、「護憲」も「平和」もワンフレーズ。しかも「平和」に魅力がないわけはない。「平和」が嫌いという人は、そうはいないはずだ。にもかかわらず、最近の国政選挙や首長選挙で、「平和」が「票」に結びついたことはない。有権者を引きつけたのは、小泉選挙では「郵政改革」、先の参議院選挙では「年金」だった。
結局、「平和」や「護憲」の意味を伝える言葉の力が弱かったと自省するしかないのだ。とりわけ、ジャーナリズムに携わる人間は、事態を深刻に見つめなくてはならない。たとえば、「正しいこと」を伝えれば、それでこと足りたと考えることはなかったか。
いや、実は、そうした反省は、これまでもさんざんしてきたのだ。有り体に言ってしまえば、その「反省」もまたポーズの面が強かったのである。自分で振り返り、自分で赤面する。
若いころ「敗北の美学」に傾倒した。言葉をこねくり回し、醜悪な「現実」をせせら笑い、「敗者こそ勝者」と虚勢を張った。だが、客観的に戦後史を眺めてみれば、自民党のほうがはるかに、生活者へ届く言葉を持っていた。
平和や人権は勝ち取るもの、負けては意味がないのだ。だから地を這う言葉探しはやめない。改めて誓う創刊記念の日。(北村肇)