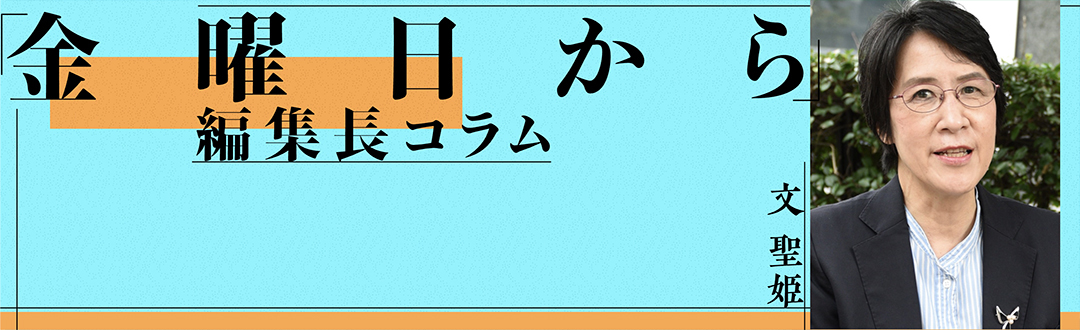警察の闇は暴く。だが、正義感ある現場のお巡りさんとは連携したい
2007年3月9日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
警視庁に勤めていた叔父は、なかなか警部に昇進できなかった。捜査一筋。事件に追われて勉強する時間がなかったからだ。自殺を図った女性を助けようとして電車にはねられた警察官は、巡査部長だった。いわゆる”エリート”ではない。出世より街のお巡りさんの仕事に誇りをもっていたのかもしれない。
事件取材に奔走していたころ、捜査員から何度も同じ愚痴を聞かされた。
「みんなあまり知らないだろうけど、警部になるための試験は難しいんだよ。捜査一課(殺人、放火など凶悪犯罪の捜査担当)なんかにいたら、なかなか勉強ができないから、苦労するよ。公安でデスクワークしている同僚は、参考書を読む時間もあってうらやましい。とにかく警部にならなくては、勲章ももらえないしなあ…」
どうやら、警部補と警部では雲泥の差があるようだ。だが、汗水流して捜査に邁進していると、警部になるための勉強時間がとれない。そんな矛盾があるのだろう。もちろん、国家公務員の「上級職」試験に合格、警察庁に配属となり、若くして幹部になる超エリートには無縁のことだ。
警察の不祥事や弾圧事件を特集する「警察の闇」は7回目を迎えた。「裏金」から始めたが、他にも取り上げるべき問題が次々と起こり、読者からの情報提供や激励も後を絶たない。親切で正義感があり、体を張って市民を守るお巡りさんと、税金を懐に入れたり、思想弾圧に手を染める警察官。特集のたびに、この落差は何だろうと考えてしまう。
メディアの社会にも似たような状況はある。「権力批判」にすべてを賭け、寝るのも惜しみ取材し続ける記者。保身に走り、政治権力や広告主の顔色をうかがうことに汲々とする経営陣。30年の体験から言えば、およそ実力のないジャーナリストが、なぜかトントンと出世したりする。
部長以上になると、それこそ実力は関係ない。上司の覚えが目でたいかどうかが、最も重要なポイントになるのだ。生涯一記者を目指す、尊敬すべきジャーナリストが役員になったことはついぞない。
警察も新聞も、一方的に批判対象とする気はない。正義感とはかけ離れた連中のいる一方で、誠心誠意がんばっている人々がいる。心ある現場の人たちと連携したい。指弾は期待の裏返しでもあるのだ。 (北村肇)