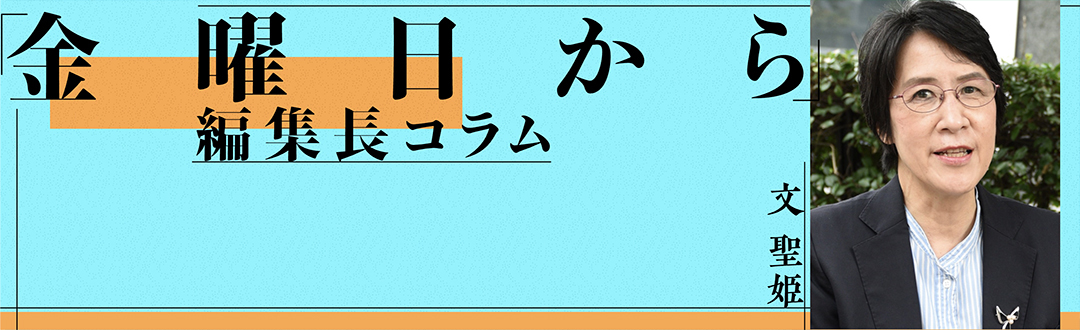年が明けて社会が変わるわけではない。それでも希望をもちたい
2007年1月12日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
何歳のころか、場所がどこか、何一つ覚えていない。ただ記憶に残るのは、地面に何かキラキラ光るものがあることに気づき、瞬間、生きていることをうれしく感じた、その「感じ」だけだ。光っていたものの正体もはっきりしない。なんとなく、砂のようであったか。いや、すべては単なる夢かもしれない。
ささやかな喜びの集積。それが人生なのだろう。悲しみや苦しみを、微細なキラキラが覆いながら、人は生きていく。「新年」に、人類の知恵である「時計」を超えた、人それぞれの意味をもたせるのも、キラキラに包み込んだ苦悩にサヨナラする儀式が必要だからかもしれない。人はそれほど強くはない生き物だ。
とはいえ、時間を切断することはできない。過去があっていまがあり、未来がある。カレンダーが変わったとたん、この国も自分も生まれ変わるわけではない。
長い間、新年のあいさつに違和感をもってきた。
「あけましておめでとうございます」
ひねくれ者と言われればそれまでだが、「どこがめでたいのか」と突っ込んでみたくなる。新年になった途端、驟雨が降り、積もっていたチリがすべて洗い流されることはない。
イラクでは絶えることなく内戦が続き、アフガニスタンやパレスティナの戦火が収まることもない。年末の国会で起きた「教育基本法改悪」の現実が霧散することはなく、格差社会の弊害が消えることもない。
むしろ、悲観的な見通しばかりが頭をよぎる。教育基本法に次いで、憲法改悪がいよいよ政治日程にのぼる。米軍再編成の実体化により、集団的自衛権の封印が解かれる。税制改悪は、ますます市民生活に暗い影を落とす。
あげればきりがない。それでも今年は、矛盾覚悟でこう自分を鼓舞してみる。「絶え間ない歴史の流れはしっかり押さえながら、新しい道を歩むきっかけにしたい」。
希望はある。あまりの弱肉強食政策に対する怒りが、社会の底からふつふつと沸き上がってくるのを感じる。かすかだが、キラキラとしたものが見える。(北村肇)