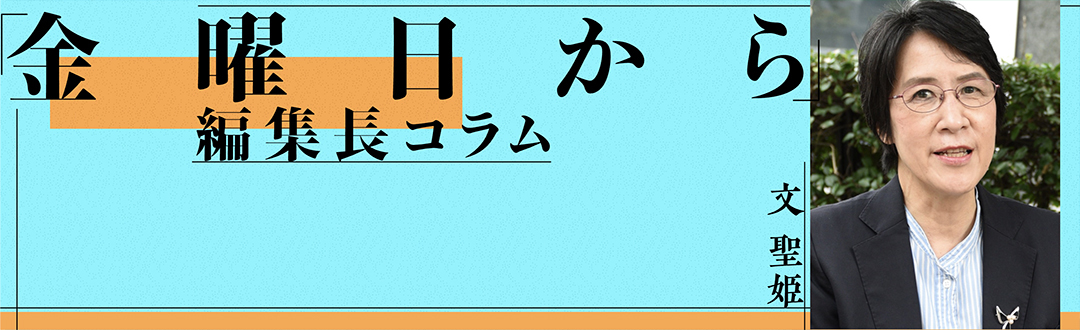松下からパナソニックになっても、マスコミが楯突けない大スポンサーに変わりない
2008年10月10日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
企業城下町はあちこちにある。だが、今の日本は企業城下国だ。さらに、企業城下マスコミも目立つ。新聞記者時代の記憶をたどると、あれこれ“圧力”をかけてくる常連企業があった。トヨタ、東京電力、JR、セブンーイレブン、そして今週号から新連載「パナソニックの正体」で取り上げる松下電器――。もっとも、直接、社会部記者に文句をつけてくるわけではない。
大抵の場合、電通―広告局―社の幹部―編集幹部―現場という流れになる。編集局の中間幹部時代は、広告局から直接、「あの記事は何とかならないか」と頼まれたこともある。さすがに「ボツにしてくれ」まではないが、「小さく扱ってほしい」とか「社名を出さないでくれ」といった類が多い。そんな時、どうするのか。
新聞社も企業だから、有力な広告主をいたずらに刺激するわけにはいかない。それなりに意向を汲み入れるときもある。だが、現場記者はギリギリのところで踏ん張り、絶対に魂を売ることはしない。
時には、「魂を売らなかった」ことに大企業が怒ってくることもある。直接、担当したわけではなく、しかもかなり古い話なので詳細はわからないが、古巣の『毎日新聞』で、松下電器の逆鱗に触れ、社の幹部が“事情説明”に出向いたことがある。欠陥商品の特ダネを大阪社会部がつかみ、大阪版の一面トップ記事にしたときだ。何しろ、松下電器は広告局にとっては、一、二のお得意様である。本社(東京)が上を下への大騒ぎになったため、私の耳にも入ってきた。
ただし、実は、広告局員のほうが、現場記者よりジャーナリスティックだったりする。仕事上、「何とか……」と依頼しつつ、腹の中では「記事を絶対に枉(ま)げるな」と叫ぶのだ。そうなると、こちらもあうんの呼吸で、「じゃあ、少し小さく扱おう」となる。もちろん、本当にするわけではない。初めから二番手扱いの予定だったのを、「トップから二番手にした」と適当にごまかしたりするのだ。
結局、どこのマスコミでも、へなへなとしてしまうのは幹部連中である。広告が入ってこなければ経営に響く、そうなると出世が覚束なくなる。お上(大企業)に盾を突いたらろくなことはない。この際、ジャーナリズムは二の次だ――。地位や報酬に恋々とした途端、「カネがすべて」の資本主義に組み込まれるのである。わかりやすいといえばわかりやすい。ちなみに、本誌今週号の新聞広告も嫌われている。(北村肇)