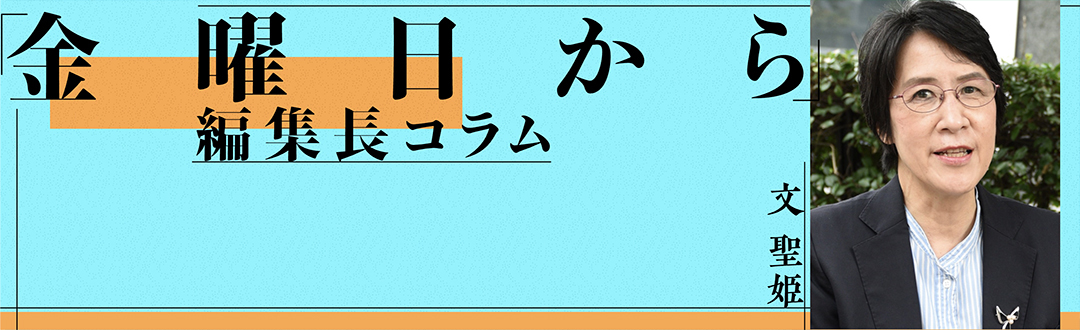「国家」の蛮行に慟哭する地球の心音が聞こえてくる
2006年9月8日9:00AM|カテゴリー:一筆不乱|北村 肇
どくどくと心臓の音が聞こえる。自分の心音ではなく、地球の「それ」だ。しだいに大きく、かつ不整の度合いが深まっている。情緒的たわごと、ジャーナリストにふさわしくないと、切り捨てられても構わない。私にとって重要なのは、まごうことなく私の耳に「それ」が伝わってくる、その事実だ。
国家にとって政治、とりわけ外交が個々の市民の尊厳を超えたものだと、いつ誰が決めたのか。究極の外交たる戦争の大義は、市民の生命を超えたものだと、いつ誰が決めたのか。結果的に市民を救い、市民の幸福につながるなど、おためごかしはやめてほしい。市民は自国だけではなく、敵国にも存在するのだ。
辺見庸氏の近著(『いまここに在る恥』毎日新聞社)で読んだ一節がよみがえる。
「人の生は、いかなる国家にあっても、むろんいかなる民主主義国家であれ、痛々しく剥きだされるときがある。国家および国家幻想こそが人の生の皮をべりべりと剥ぐのだ」
正義の戦争があるのだと居丈高に叫ぶ人たちがいる。正義とは、「他」の人の尊厳を傷つけず、守ることであったはずだ。いわずもがな、生命を奪うのは、もっとも正義とはかけはなれている。よしんば、侵略に抵抗する戦争が存在したとして、かりに避けられないことだったとして、それは「悪」をもって「悪」を制することにほかならない。正義の戦争は存在し得ないのである。
誰かに襲われたら抵抗しないのか、愛する人が襲われたらどうか。そんな愚問に答える必要はない。圧倒的多数の市民を巻き込んだ戦争と個人の暴力を同じ地平でとらえるのは、国家の常道たる欺瞞にすぎないからだ。
イスラエルのレバノン侵攻にいかなる大義があったとしても、市民を国家のはるか下に位置づける発想を許すべきではない。イラクや北朝鮮をならず者国家と糾弾しながら、イスラエルの蛮行を見て見ぬふりする米国を許すべきではない。その米国に隷属し続ける日本の為政者を許すべきではない。
感情的と言われようが、情緒的と言われようが、「生命は地球より重い」。地球が慟哭し身悶えるのは、無駄死にさせられた人間の血と涙が、あまりにも重くのしかかるからだ。(北村肇)