【憲法を求める人々】古川佳子
佐高信|2018年6月23日7:00AM
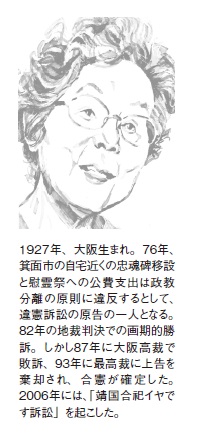 『ドキュメント昭和天皇』(緑風出版)の著者、田中伸尚に『これに増す悲しきことの何かあらん』(七つ森書館)という編著がある。
『ドキュメント昭和天皇』(緑風出版)の著者、田中伸尚に『これに増す悲しきことの何かあらん』(七つ森書館)という編著がある。
この題名は古川の母、小谷和子の「是れに増す悲しき事の何かあらん亡き児二人を返せ此の手に」から採られた。古川は近著『母の憶い、大待宵草』(白澤社発行、現代書館発売)の「はじめに」に、この歌は古川にとっての兄2人を戦死させた国家の暴力を見据えて「天皇の戦争責任を生涯思い続けた母の憤怒であった」と記す。
この本の跋に田中が書いているように古川は「何とも静やかでおっとりした人」だが、1976年に箕面忠魂碑違憲訴訟に踏み切った勁(つよ)さを持つ。それは「手の中の玉と育てし是れの子を弾雨に曝す日は近づきぬ」とも詠んだ母親譲りなのだろう。
この母が息子の啓介と博の戦死の知らせを受けたのは敗戦の1945年8月15日より後だった。46年の6月15日の日記に彼女は「もう啓介、博のことに限り案じなくて済む。これからは常に常に母と共に在る子よ。啓ちゃん、博ちゃん、よい子でした」と記している。
古川は1927年に生まれた。城山三郎や藤沢周平と同い年である。まさに青春の真っ只中に軍国主義の焼印を押されたが故に、精神の支配には全身で抵抗する。古川にとって忠魂碑訴訟は自らの青春を取り戻す闘いでもあった。この運動をリードした神坂哲は、箕面市が忠魂碑を建立するのを許してはならないとして、古川にこう言ったという。
「こんな市の税金の使い途を見逃したら、私たちも軍国主義の共犯者になるではありませんか。私たちはかつて国家に忠誠を誓った果てに裏切られた口惜しさを体験しています。もう二度とダマされたり、ダマしたりしてはいけないんです。私たちの世代はそういう責任をもっているんです」
この訴訟は一審の大阪地裁で勝訴したが、画期的な違憲判決を出した裁判長の古崎慶長は右翼に襲われる。しかし、それに怯まず、「裁判官は、慣行や圧力に屈せず、独自の判断を下すことが、司法における“言論の自由”であり、真の司法の独立だ」と発言した。
古川は、この闘いの過程で、さまざまな人に出会った。たとえば「姉妹以上の親交を得た」伊藤ルイである。松下竜一が『ルイズ』(講談社)に描いた大杉栄と伊藤野枝(共に無政府主義者)の娘のルイは1981年秋の「戦争への道を許さない福岡集会」に古川を招いて、忠魂碑訴訟の話をさせた。
ルイの母、野枝は関東大震災の直後、大杉や甥と共に憲兵隊に虐殺されたが、母親のウメに、
「お母さん、わたしは畳の上では死なれんとよ」
と言っていた。
ルイも古川も、それぞれの母の憶いを胸に生きてきたのだろう。
古川の二男が高校生の頃、70年安保と高校生の政治活動規制に反対して、校門前でハンストをした。学校側は止めさせたいとして、古川に働きかけたが、その時のことを古川は作家の松下竜一宛ての手紙で次のように書いている。
「先生方から、おかあさんの説得でやめさせてくださいといわれたとき、わたしは思わず、それはできませんって、答えてしまいました。不思議ですね。考えて答えたというより、先に言葉が飛び出したみたい……」
言葉少なに静かに言うから迫力がある。そのことを私は古川に教えられる。
(さたか まこと・『週刊金曜日』編集委員、2018年6月8日号。画/いわほり けん)



















