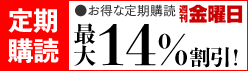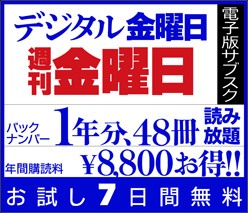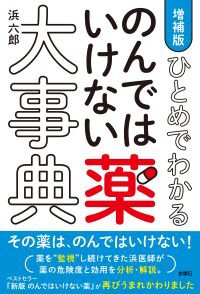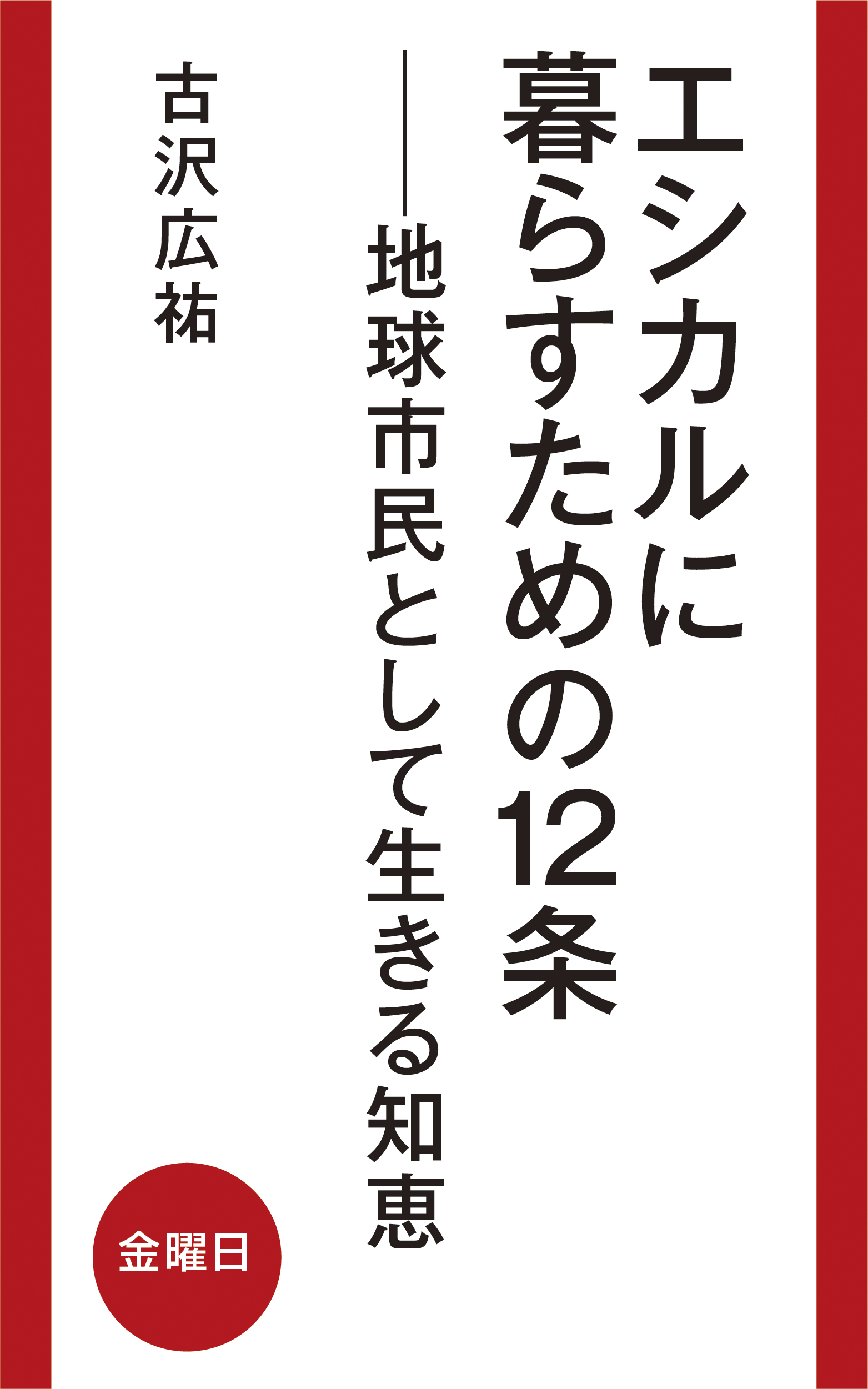「深刻な物価高に対する岸田政権の無策」宇都宮健児
宇都宮健児・『週刊金曜日』編集委員|2024年5月31日7:27PM

厚生労働省が5月9日発表した3月の毎月勤労統計調査(速報)によると、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は前年同月比2・5%減となり、マイナスは24カ月連続で、リーマン・ショックなどにより景気が低迷していた時期を超え、過去最長を更新したということである。物価高騰に賃金上昇が追いつかない状況が2年に及び、家計悪化に歯止めがかからない状態が続いている。今年の春闘では大企業の正規労働者を中心に大幅な賃上げが行なわれたが、この大幅賃上げは全労働者の約4割を占める非正規労働者や全労働者の約7割を占める中小企業で働く労働者には及んでいない。
内閣府が5月16日に発表した2024年1~3月期の国内総生産(GDP)速報値は、物価変動を除く実質で前期比0・5%減、年率換算では2・0%減であった。
GDPの約6割を占める個人消費は前期比0・7%の減少で、リーマン・ショックの影響を受けた2009年1~3月期以来となる4四半期連続の減少であった。個人消費の低迷の背景にはこのところの異常な物価高がある。
政府は物価高対策として6月に1人当たり4万円の定額減税を行なうが、一時的な対症療法にすぎない。減税の実施とほぼ同時期には、電気・ガス料金に対する政府の補助金が終わり、電気・ガス料金が値上がりする。食料品などの値上げもいまだ収束する気配がなく、みずほリサーチ&テクノロジーズの試算によれば、24年度の2人以上世帯の家計支出額が23年度に比べ、10万円余り増える見通しであるということである。このほかにも国民健康保険料や介護保険料の値上げも続いている。
このところの物価高の背景には歴史的な円安がある。円安の主要な原因はアベノミクスの「第1の矢」として行なわれた「異次元の金融緩和」政策である。インフレ対策として金利を引き上げた欧米諸国と超低金利政策をとってきた日本の金利差が円安の大きな要因となっているのである。
4月28日に行なわれた三つの衆院補欠選挙では、自民党は不戦敗も含め全敗した。自民党の敗北は自民党派閥の政治資金パーティの裏金問題に対する有権者の批判が広がった結果であるが、根底には物価高で苦しむ国民生活に対し、何ら有効な対策が打てていない岸田政権の無策に対する有権者の怒りがある。
(『週刊金曜日』2024年5月31日号)