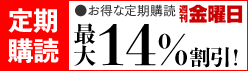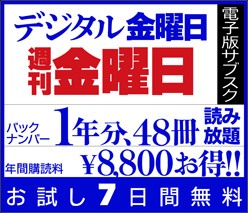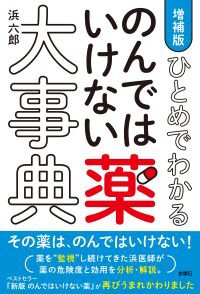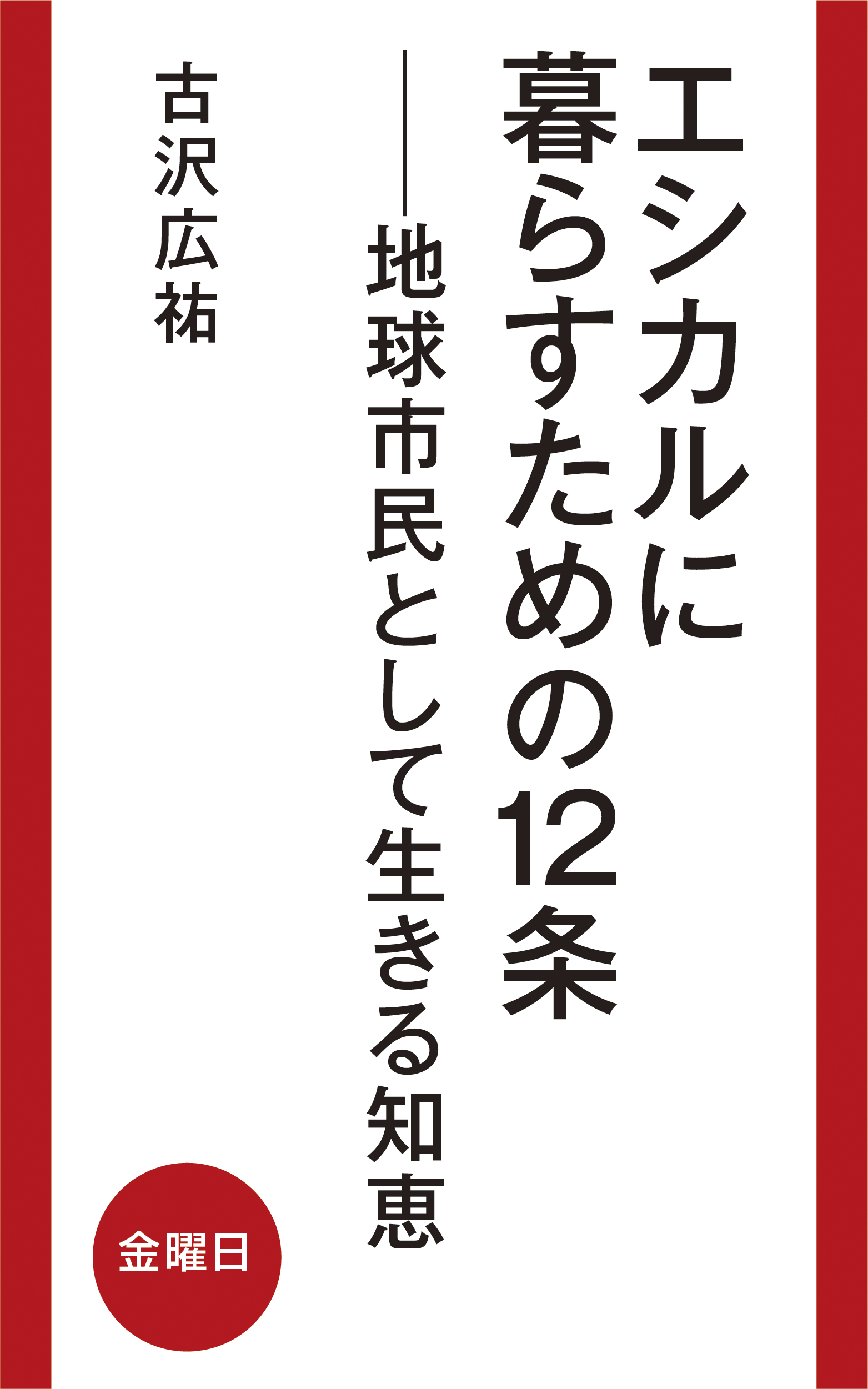都庁前に生活困窮者770人以上 小池都知事は食料配付現場に一度も現れず
竪場 勝司・ライター|2024年6月20日1:55PM
コロナ対応を自画自賛する小池都知事だが、医療崩壊で人が死んでいる時に五輪をやっていた、と雨宮編集委員は批判する。生活困窮者は増加、食料品配布には長い列ができていた。
地下鉄を降り、地上に出ると、そこはゴジラのプロジェクションマッピングが映し出されて話題を集めた、巨大な東京都庁の庁舎がそびえる地帯。
6月1日12時50分、生活困窮者向けの食料品配布が始まるまでには1時間以上あるが、周辺にはすでに多くの人が集まっていた。ここでは毎週土曜日、認定NPO法人「自立生活サポートセンター・もやい」と支援団体「新宿ごはんプラス」が、食料品配布と相談会を開催している。

午後1時、スタッフの声掛けで、食料品配布を受ける人々の列をつくる作業が始まった。都庁近くの広い通路スペースを利用して、スタッフが参加者を誘導し、会場に到着した順に待機場所を指定して、列をつくっていく。スタッフがプラカードを掲げて、「食料品配布の最後尾はこちらです」と繰り返し大きな声で知らせ続ける。
新たに会場に来た人は、このプラカードを目印に列の最後尾に並んでいく。見る見る間に参加者の長い列ができ、スペースの端まで行くと、そこで折り返し、また長い列が。折り返しを何度か繰り返し、何列もの長い行列ができた。
年配の男性が多いが、若者や女性の姿も目立つ。待機場所で配布を待つ間、一人でじっと考え込む人、手にした文庫本を黙々と読み続ける人、仲間と談笑する人など、さまざまだった。
午後2時、食料品の配布が始まった。列に並んだ順に、若いスタッフから食料品の入った袋が参加者に手渡されていく。この日配布された食料品は、レトルトパックのきのこご飯、食パン、トマトなどのセットだった。
用意した食料品がなくなった午後2時30分すぎ、スタッフが「本日の食料品配布は終了です」と大きな声を会場に響かせ、配布が終了。この日、食料品配布を利用した人は770人以上にのぼった。
若者や女性の姿目につく
長い行列の先頭にいて、最初に食料品のセットを受け取った男性は58歳。会場に来たのは前日の5月31日夜の8時半ごろ。「昨日は別の場所で炊き出しがあり、そのついでに、こちらに並んだ。12月ごろから、半年ほど通っている。最初はネットで知ってやってきた」という。
不動産業をやっていたが、4年前に脳梗塞を患い、車が運転できなくなって失業し、現在まで生活保護を受けている。何とか就職を考えているが、脳梗塞の後遺症で厳しい状況だ。「大変ですね」と声を掛けると、「どんな形でも、生きなくちゃならないからね」との答えが。
手押し車を押していた80歳の女性。友だちの紹介で食料品配布に来るようになり、参加は5回目ぐらい。「仲間がいて話もできるし、ここへ来れば、気が晴れるから」としっかりとした口調で話す。
収入は年金だけで、「物価高で生活は大変もいいとこ。電気代が高くなったでしょ。節約でエアコンをつけないことも考えるけど命はカネに代えられないからね」。緑内障と白内障の手術をして、ほとんど失明状態。腰は脊柱管狭窄症で骨が曲がった状態だが、年齢もあり、手術は無理と考えている。
最後に「お体に気を付けて」と声を掛けると、「ありがとう」と優しい言葉が返ってきた。
かなり列の前の方にいた83歳の男性は、今は一人暮らしで、収入は月14万円の年金のみ。
「物価高で生活は苦しいし、厳しいね。不動産業を失敗したから。やくざ者にだまされたり、裁判で負けたりして、母ちゃんと別れて……」とこれまでの人生を振り返り、「食料品の配布は助かるけど、こんなとこ、社会の底辺だからね」とつぶやいた。
それまで隔週で行なわれていた食料品配布が、毎週土曜日開催に拡大されたのはコロナ禍で緊急事態宣言が出た2020年4月。この月の1日あたりの平均利用者は約120人だったが、利用者は回を重ねるたびに増加して、昨年末には700人台に達し、以前は見られなかった若者や女性の姿が目につくようになった。
「もやい」理事長の大西連さんは、「物価高など、暮らし向きが苦しい方が増加している。民間の支援現場で支えていくには限界もある。観光や経済振興などに比べて、弱い立場の方への支援は光が当たりにくいので、所得が低い方への支援について、もうちょっと目を向け、積極的に取り組む都政であってほしい」と話している。
6月1日の食料品配布の現場には、都知事選に立候補を表明している立憲民主党の蓮舫氏も視察に訪れた。スタッフによると、小池百合子知事が配布の現場を訪れたことは、一度もないという。
コロナ対応成功ではない
長年、反貧困の活動に取り組んでいる作家で本誌編集委員の雨宮処凛さんによると、都庁前の食料品配布をめぐっては20年11月から12月にかけて、会場に三角コーンを置いて行列に並ぶ人を排除する東京都の妨害行為が、5週間にわたって繰り返されたという。
「民間団体が都や国の支援を一切受けずに、善意で困窮した人たちを支えていることに対し、東京都は本来、お礼を言うとか、予算をつけたりすべきなのに」と雨宮さんは憤る。
コロナ禍が始まってすぐの20年4月、雨宮さんらは東京都に緊急の申し入れを行なった。この時期、路上に出る人が急増。生活保護を申請すると相部屋の無料低額宿泊所に入れられてしまい、感染リスクが高くなるので、ホテルや公共施設を開放してほしいという要請だった。
その甲斐あってか緊急事態宣言が出た後に、路上の人もホテルに入れるようになった。800人ほどが入ったが、そのまま「入れっ放し」で、多くは生活保護につなぐこともなかった、という。
その後、路上から生活保護を申請した人が、都が借り上げたホテルの部屋に1カ月住みながら、施設を経由せずにアパートに入れるようになり、雨宮さんはこの点は「すごくよかった」と評価。
しかし、ホテルの提供は22年10月に終了してしまった。「旅行支援との兼ね合いで、家がない人の住まいを保障せずに、余裕のある旅行者を支援するという方針転換だったのでは」として、支援者らは提供の継続を東京都に申し入れた。
東京都はネットカフェ難民が都内に約4000人いるという調査結果を、18年に発表している。雨宮さんは「調査をしたのはよかったが、結局、何もせず放置したので、そのままコロナ禍になって大変な状況になってしまった」と批判している。
コロナ禍で困窮している人を対象に、雨宮さんたちは「女性による女性のための相談会」を何回か開催し、小池知事と面会して相談会への来場などを要請したが、小池知事が相談会の現場に来ることはなかった。
小池知事が5月末の都議会で、「1200日、全身全霊で取り組んだ」として、コロナ対応を誇るべき業績として語っていることに対し、雨宮さんは次のように厳しく批判する。
「全然成功ではない。自宅療養者が東京都でもたくさん出ており、第5波や第6波では、東京は医療崩壊していた。『救急車が来ないのが当たり前』の状況が数カ月続いた。それを誇るというのは、おかしい。医療崩壊している最中に、自宅療養者がどんどん死んでいる時に、東京オリンピックなんてことをやっている状況だったのか」
(『週刊金曜日』2024年6月14日号)