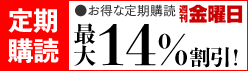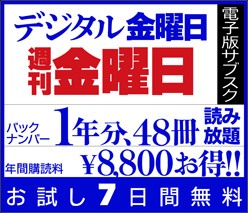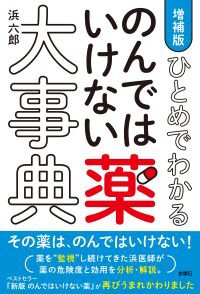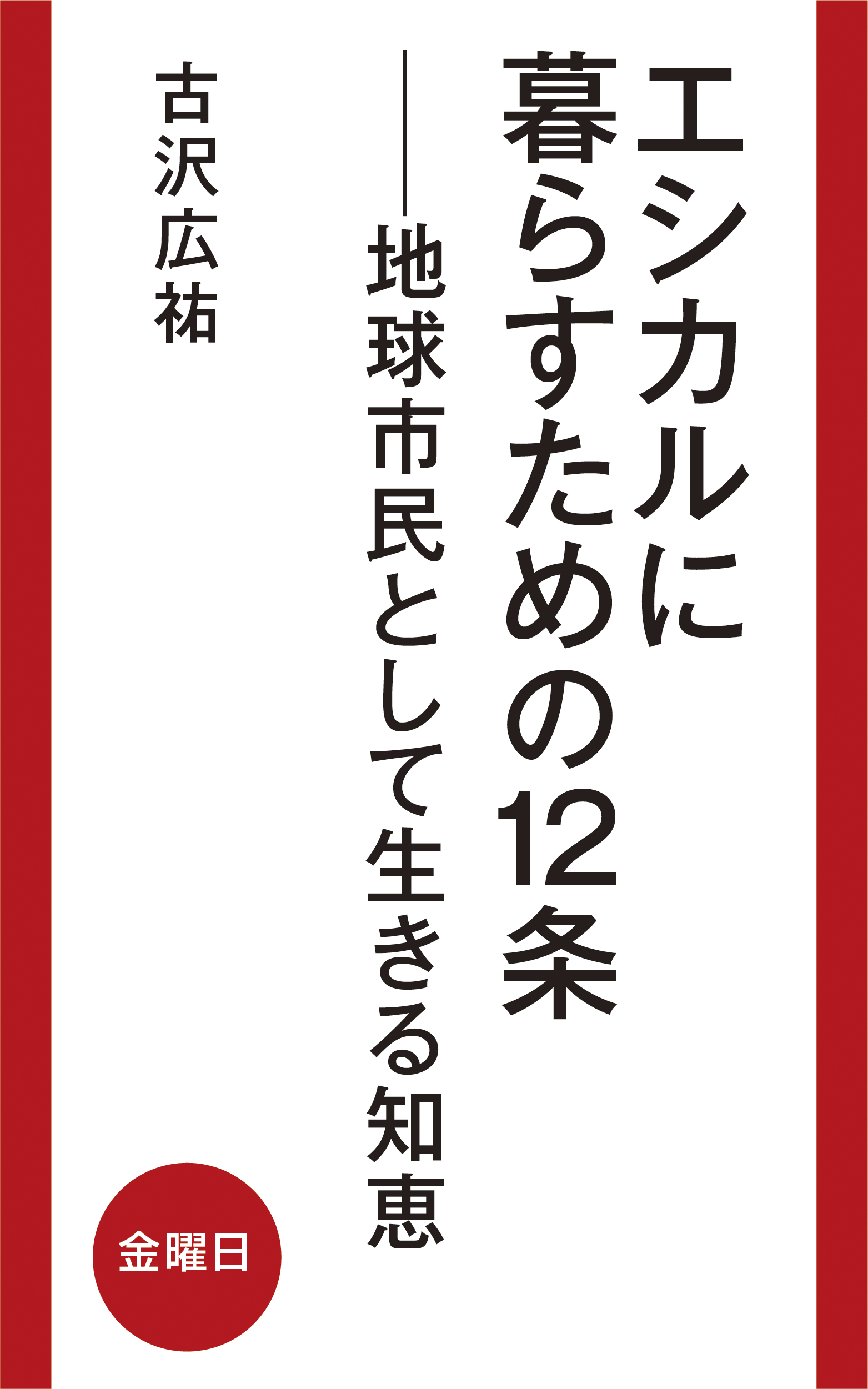8党派女性議員の勉強会実施 選択的夫婦別姓とクオータ制実現向け超党派協力なるか
山田道子・ライター|2025年2月6日6:57PM
2024年10月の総選挙でジェンダー政策に理解のある野党が議席を増やしたことにより、国会内のジェンダー平等を推進する動きも活発化している。12月4日には女性議員を増やすことを目指す8党派女性議員による「クオータ制実現のための勉強会」(長野智子事務局長)が、東京都内で開催された。

テーマは選択的夫婦別姓の法制化。10月には国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)から4度目となる導入の勧告を受け、2年以内の進捗報告も求められている重要事項だ。導入に積極的な勢力の議席が増え、反対を続けてきた自民党が少数になったことで、現実的政治課題として浮上したためだ。
選択的夫婦別姓をめぐっては、法制審議会が1996年に制度導入の民法改正を求める答申を出したが、自民党内の反対で内閣法案としての提出ができないままでいる。別姓制度導入に取り組んできた自民党の野田聖子議員は「自民党が少数与党になり、これまでできなかったことをやっていきたい。党内では『氏制度のあり方に関するワーキングチーム』が夏に再開した。議論を進める努力をしたい」と決意表明。同党内では無関心の議員が多く、世論の動向によって賛成に動く可能性が高いとの見方を示した。
立憲民主党の辻元清美代表代行は「石破茂政権は内閣提出法案として出すのではないか。来年の通常国会に閣法案、公明党案、野党案が出れば修正協議に持ち込み、成立させるのが現実的だ」とし、野田氏に働きかけを求めた。
社民党の福島瑞穂参院議員は「衆院法務委員長は推進派。法相も衆院選時のアンケートでは賛成の立場を示している。野党案を出して審議入りし、参院選前に成立させることを獲得目標にしたい」と訴えた。
日本維新の会の石井苗子参院議員は「結婚後、社会的に旧姓が使えないのは不都合なので、旧姓に法的効力を持たせる形での選択的夫婦別姓の法律構築で考え方が止まっている。『選択的』とは同姓も選択できるということが分かっていない」と党内状況を説明。別姓が基本との誤解を生まないため、「選択的夫婦同姓制度」としたほうが理解を得やすいのではないかと提案した。
現状では「日本沈没」
勉強会には、選択的夫婦別姓実現を目指す一般社団法人「あすには」代表理事の井田奈穂氏が参加。CEDAW勧告の詳細を説明し、「2025年の通常国会で、参院選前に法改正をしてほしい」と求めた。同氏は、クオータ制に関するCEDAWの改善勧告も紹介。クオータ制とは指導的立場の女性を増やすため一定数を割り当てる仕組みのこと。勧告は「政党の努力に任せるのではなく、罰則つきのクオータ制を設けて啓発する。第6次男女共同参画基本計画では指導的地位に占める女性の割合を、(第5次計画の)30%ではなく50%に引き上げよ」との内容だ。
総選挙で女性の当選者は73人、全体の15・7%。女性候補者も314人、23・4%でいずれも過去最高ではあったが、2018年施行の「政治分野における男女共同参画推進法」は候補者数の男女均等という努力義務を課しており、全く及んでいない。井田氏は「女性議員が増えることで、生活や命に関わり、ケア労働をしているからこそわかる政策を進められる」と意義を語り、クオータ制実現のために「クオータを達成できなかった政党には政党助成金を出さないなどの罰則が必要だ」と発言。女性候補者へのハラスメント対策、女性が選挙に出やすくする支援金の必要性なども指摘した。
経済分野のクオータ制とその成果に詳しいジャーナリストの野村浩子氏は、政治分野のクオータ制導入も支持し、「政党に対してクオータの目標と達成のための計画を公表することを義務づけ、“見える化”することが必要だ」と説く。そして、「自民党のように現職優先ではなく、従来の候補者条件を見直すべきだ。出産・育児と両立できるなどの選挙や議会の在り方を変えないと、女性や若者は政治に参入できない。日本は沈没してしまう」と警告する。
指摘の通り、ジェンダー平等は女性のためだけではなく社会全体のために必要なもの。心ある議員らが超党派で協力し、政策実現することを期待する。
(『週刊金曜日』2024年12月20日号)