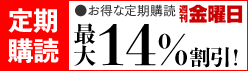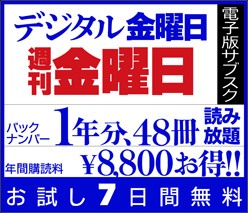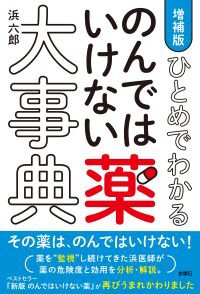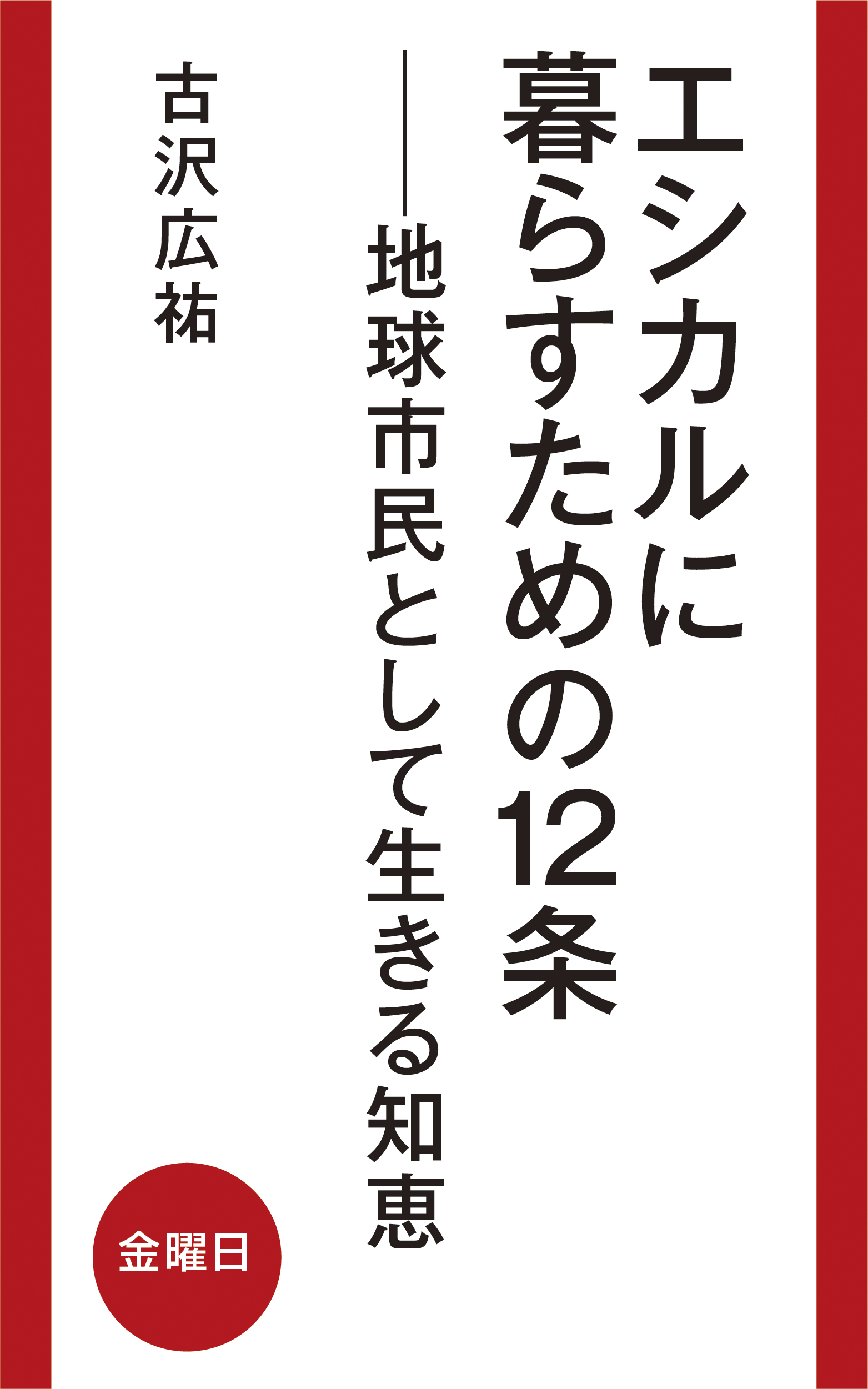【タグ】東電
東電株主代表訴訟控訴審結審 約13兆円の支払い命じた地裁判決は維持されるのか
脱原発弁護団全国連絡会|2025年2月6日7:06PM
2022年7月13日に元東電取締役の被告勝俣恒久、清水正孝、武黒一郎、武藤栄の各氏4人に13兆3210億円を東電に支払うことを東京地裁が命じた東電株主代表訴訟の控訴審が、24年11月27日に東京高裁で結審した。

原判決は、原発過酷事故が起きれば国土の広範な地域と国民全体に甚大な被害を及ぼし、わが国の崩壊にもつながりかねないと指摘し、原子力事業者には最新の知見に基づき、過酷事故を万が一にも防止すべき社会的・公益的義務があることを明示。02年に地震本部が公表した「長期評価」やその見解に基づき東電設計が08年に計算した最大15.7メートルの津波予測(明治三陸試計算結果)の信頼性も認定したうえで、福島第一原発が、ドライサイトはもはや維持されておらず、ウェットサイト(津波が敷地の高さを大きく超えて到来することが科学的に想定される状況)に陥っている以上、何らの津波対策を講じず放置した被告らの「不作為」は津波対策の先送りであり、著しく不合理で許されないと指摘し、主要建屋や重要機器室の水密化措置によって事故を防げたと認定した。もっとも、10年に取締役に就任した被告小森明生氏については請求を棄却した。
敗訴した被告らが控訴し、原告株主側も被告小森氏の責任と金額について争うとして控訴した。
控訴審が結審したこの日、当事者双方が2時間ずつプレゼン資料を用いて説明。
一審被告ら・東電から、長期評価や明治三陸試計算結果に信頼性がないこと、本件津波は極めて巨大で明治三陸試計算とは全く規模が異なる、本件事故前はドライサイトコンセプトによって行なわれており、水密化措置は一般的ではなく、「後知恵」による判断は許されない等を6.17最高裁判決や刑事控訴審判決、今村文彦意見書、佐竹健治意見書に全面的に依拠して説明した。
この点に対して、一審原告らは(A)本件と最高裁判決では証拠関係が異なる、(B)本件は民事事件であり無罪が推定される刑事事件とは異なる、(C)今村氏は原発事業者の代弁者ともいえるからその内容は信用できない、(D)佐竹氏は原審で提出されている意見書でも同じことを述べていること等を指摘し、一審被告らの説明は根本的に間違っていると指摘した。
長期評価の見解は、予防の観点から津波対策すべきであるという相当数の専門家の考え方が表れたものであったこと。事故前から福島原発の敷地高プラス1メートルの津波発生により過酷事故に至ることが示されていたこと。東電はことさら3.11大津波が巨大であったと主張しているが、福島沖ではそれほどの違いはなく、福島原発の10メートル盤上の浸水の高さは、明治三陸試計算結果も3.11大津波も変わらないこと。事故前の保安院や原子力安全委員会、東電、その他の事業者のさまざまな資料において、水密化が基本であったことを示し、津波対策の基本は防潮堤だったとの6.17最高裁の判示の誤りを指摘した。
一審被告らや東電は、武藤決定と本件不作為について、社会通念上一つの指示を土木学会・津波評価部会に検討を委託し、このような方針について専門家の意見を確認するとした「武藤決定」と「本件不作為」とに不自然に分離している等と論難するが、①武藤決定と、これらが済むまでの間②―1何も対策はしないのか、②―2過酷事故が生じないための津波対策を検討させ、速やかに行なうよう指示するのかは、論理必然の関係にはなく、どちらの対応もあり得たことであると断じた。
小森氏は取締役就任後、直ちに津波対策を命じれば間に合ったこと。勝俣氏らは、原発の安全対策は専門的技術的事項であり、津波対策の指示はおよそ不可能というが、実際には御前会議での議論等から過酷事故に至ることを容易に認識でき、津波対策をせよと指示するだけで足りたと批判。
最後に、本件損害額23兆4000億円は原発事故被害の大きさを示しており、一審被告らには、高度な注意義務があることを再度確認。原審の立証過程を説明し、原判決は維持されるべきであると締めくくった。
木納敏和裁判長は、判決言い渡しは、2025年6月6日(金)11時と指定した。
(『週刊金曜日』2024年12月20日号)
【タグ】東電