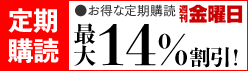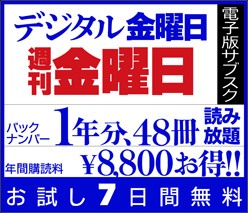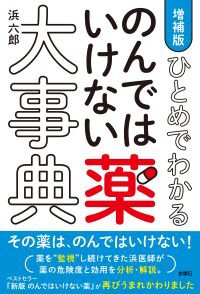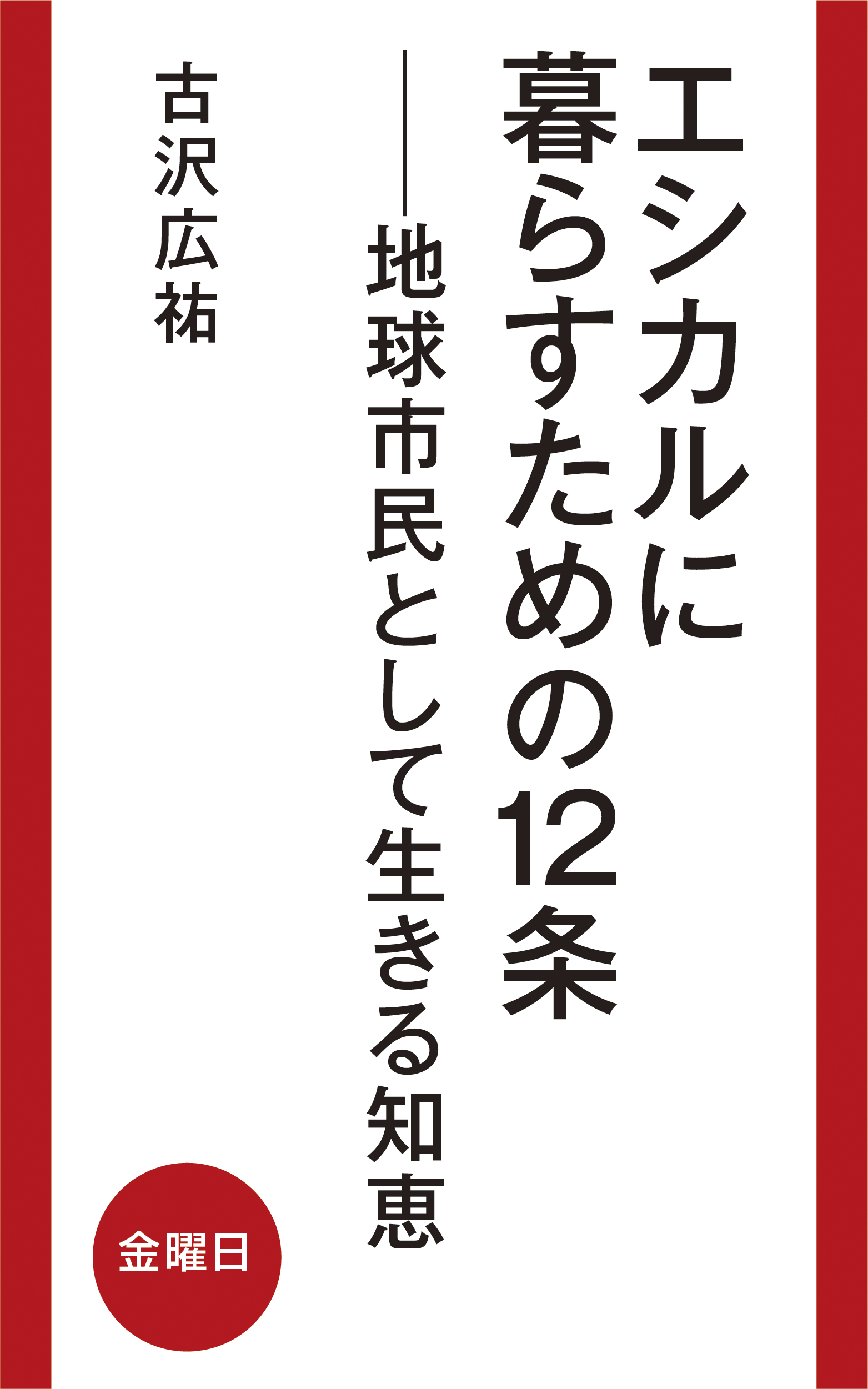【タグ】AI
〈芸術の原点〉想田和弘
想田和弘・『週刊金曜日』編集委員|2025年4月1日10:31PM

牛窓にある瀬戸内市立美術館(岡山県)で、木村セツさんの展覧会を見た。「96歳 セツの新聞ちぎり絵原画展」である。
タイトルにあるように、セツさんは現在96歳。夫が亡くなり、何もすることがなくなって、90歳でちぎり絵を始めたという。
制作に使用するのは和紙や色紙ではなく、新聞紙だ。自宅でとっている新聞に掲載されたカラー写真をちぎって、ブロッコリーやら、鯛やら、焼き芋やら、卵かけご飯やら、牛乳パックやら、飼っている猫のフクちゃんやら、色彩豊かに描く。細部にいたる色合いや陰影が実に見事で、一枚一枚、見入ってしまう。新聞紙を使うので、ときどき文字が混じっているのも面白い。
セツさんが日常で接するどこにでもありそうな事物を、何のてらいもなく、シンプルに描いているだけなのに、なぜか胸を打つ。それはたぶん、セツさんがちぎり絵を純粋に楽しんでいて、彼女の喜びが直に伝わってくるからだ。絵を描くのは嫌いだったというセツさんだが、今ではちぎり絵が一番の楽しみであり、生きがいだという。
「やり始めたらどんどん興味わいてしまって、一心になってしもて、娘に『おかあさん、飲み物も冷たなってたで』って言われた。次の日にまたがるのは嫌や。その日に仕上げてしまって最後まで見届けたい」(木村セツ著『90歳セツの新聞ちぎり絵』)
セツさんの作品を鑑賞しながら、昨今の生成AI(人工知能)流行りに抱いていた違和感の正体がわかった。生成AIで簡単に絵や映像や音楽が作れるなどといっても、そこで人々が誇るのは使用価値やコストのことばかりで、「誰が何を表現したいのか」という視点がすっぽりと抜け落ちているのだ。そもそもAIに「表現したい」という意思も欲求もないのだから、当然である。
だが、人類はそもそも、踊りたいから踊ってきたし、歌いたいから歌ってきたし、絵を描きたいから描いてきたのではなかったか。何かの役に立つとか、お金が儲かるとか、有名になれるとか、そういうものは副次的についてくることもあるだろうが、芸術の根源には作り手の何かを表現したいという欲求があったはずだ。そして鑑賞者は表現者の世界や心の内側に触れられたように感じられたとき、感動するのである。
気取りも野心も下心も感じられないセツさんのちぎり絵は、芸術の原点を思い出させてくれる。AIは空虚である。
(『週刊金曜日』2025年2月28日号)
【タグ】AI