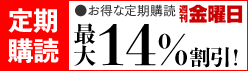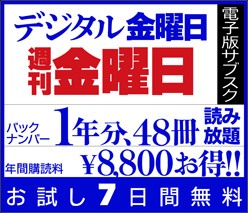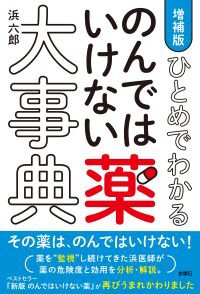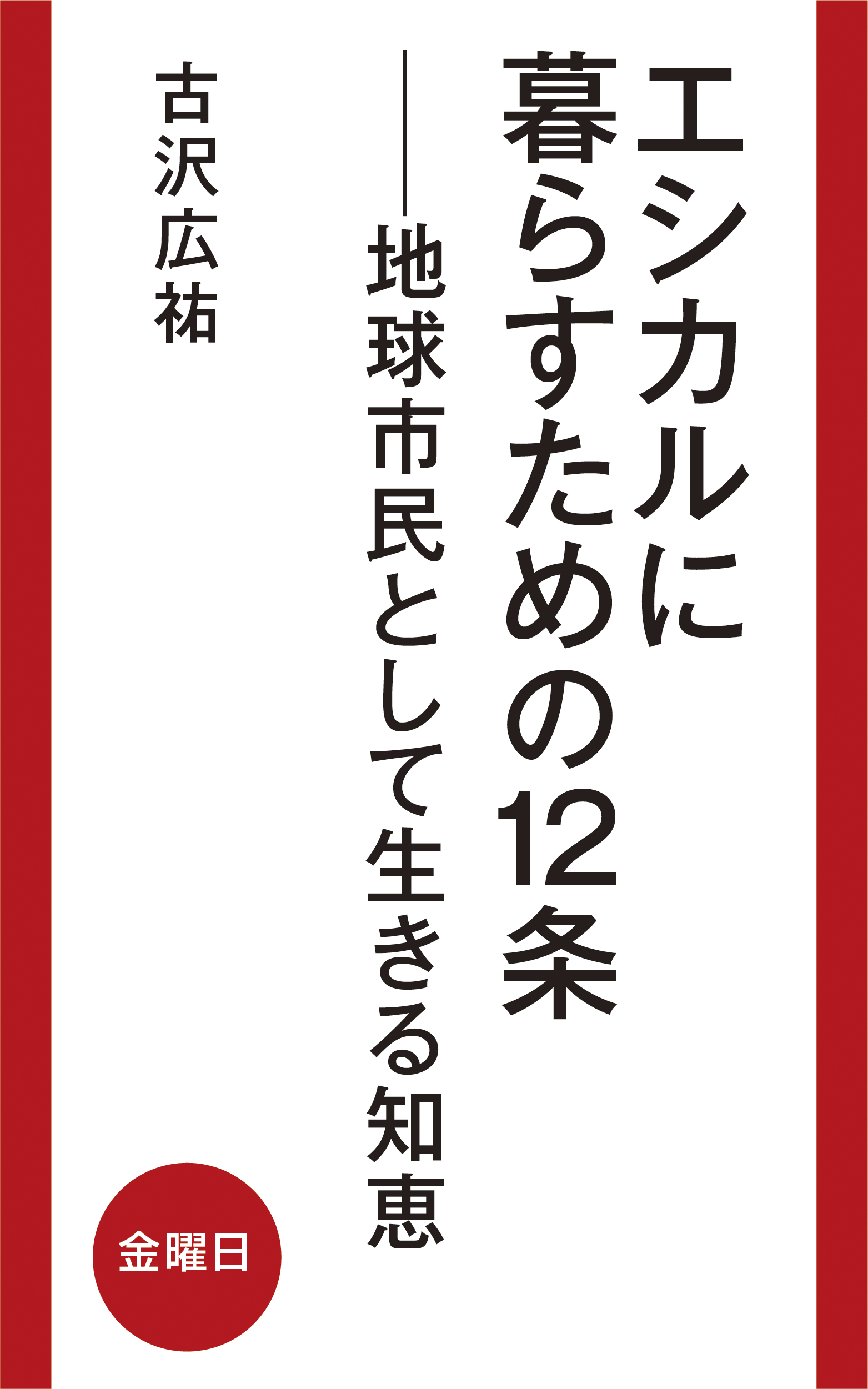CEDAWへの拠出金制限 勧告への「報復的対応」NGOら早期撤回を要求
古川晶子・ライター|2025年4月1日8:35PM
「委員会の勧告内容が日本政府の意に沿わないからといって、国連機関への拠出金使用を制限するなどという報復的な対応は、とても人権先進国がなすべき行ないとはいえません」
1月30日、女性差別撤廃条約実現アクションと日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(JNNC)は、連名で外務省に対し申し入れを行なった。この前日に同省が明らかにした、国連人権高等弁務官事務所への拠出金の使途から女性差別撤廃委員会(CEDAW)を除外する、との決定を撤回するよう求めるものだ。

同省はこの決定について、昨年10月に出されたCEDAW勧告への「対抗措置」であると説明している。CEDAWは同月、日本社会のジェンダー平等の推進状況について、政府報告と市民レポート等に基づき、政府代表団との間で「建設的対話」を実施。その中で日本の皇位継承が男系男子に限ると法律で定められていることを問われ、内閣官房の担当者が「委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではない」と回答拒否に等しい発言をして、議長から注意を受ける場面があった。
その後に出された勧告には「男女の平等を確保するために継承法を改正した他の締約国の好事例を参考にし、王位継承における男女の平等を保障するために皇室典範を改正すること」と記された。 日本政府はこれに対して同12月、「皇位につく資格は、基本的人権に含まれているものではない」として、皇位継承を男系男子に限定することは差別には当たらず、またCEDAWで取り扱うべき問題ではないという意見書を出している。条約にかかわる本来の手続きを進めることに加えて、拠出金を手段とする「対抗措置」をとろうとしている形だ。今年1月27日、国連に拠出金の制限について通告したという。
しかし、そもそも「対抗措置」とは、他国による国際法に反した行為に対する制裁措置を指す。違法行為の被害国が加害国に対して科すことができる制裁であり、CEDAWを対象とすることはあり得ない。しかもこの場合、違法行為が存在しないのである。
また拠出金とは、構成員が相互扶助に役立てるために出し合う金銭である。構成員の合意により特定の目的に注力することはあっても、個々の拠出者の恣意的な判断で制限をかけることは、本来の趣旨からしてあってはならない。
再び孤立しないために
国連の相互扶助とは、国連憲章第1条にいう「経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語または宗教による差別なく、すべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること」だ。その目標を具体的に規定するものの一つが女性差別撤廃条約であり、CEDAWはその実施機関。条約を批准する国の拠出金がその運営に使われるのは当然のことだ。
拠出金制限の決定は、どのようにしてなされたのか。取材に対し、同省女性参画推進室は「必要な検討を必要なレベルで行なった。それ以上は答えられない」と回答。制限が勧告への「対抗措置」という意図であることは認めた。
女性差別撤廃条約実現アクションの浅倉むつ子共同代表は「このようなことが認められれば、国際人権規約の他の勧告にも同様の対応が取られる可能性がある」として早期撤回を求める。意見書の手交に立ち会ったNGOからも「今回のようなやり方は、対話を拒否する行為とみなされる」「女性差別撤廃条約を守らなくてもいいという誤ったメッセージを伝えることになる」と、日本政府の人権感覚や国際感覚の欠如を表すとも取れる、今回の事態を危惧する発言が相次いだ。
NGO側は、この件について「市民社会やメディアに開かれた説明会ないしは意見交換会」の開催を求めている。同省が開催しない場合は関心ある市民で主催し、同省には出席を要請する意向だ。
日本政府は1933年、「満州国」が承認されなかったことを機に国際連盟を脱退し、国際社会から孤立した負の歴史を持つ。再び国際基準に背を向けて孤立しないために、今こそ市民の言葉に真摯に耳を傾けるべきだろう。
(『週刊金曜日』2025年2月14日号)