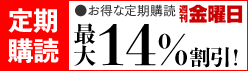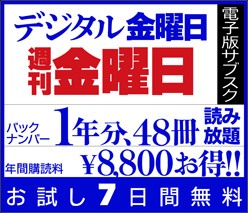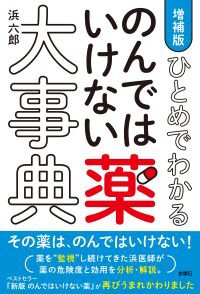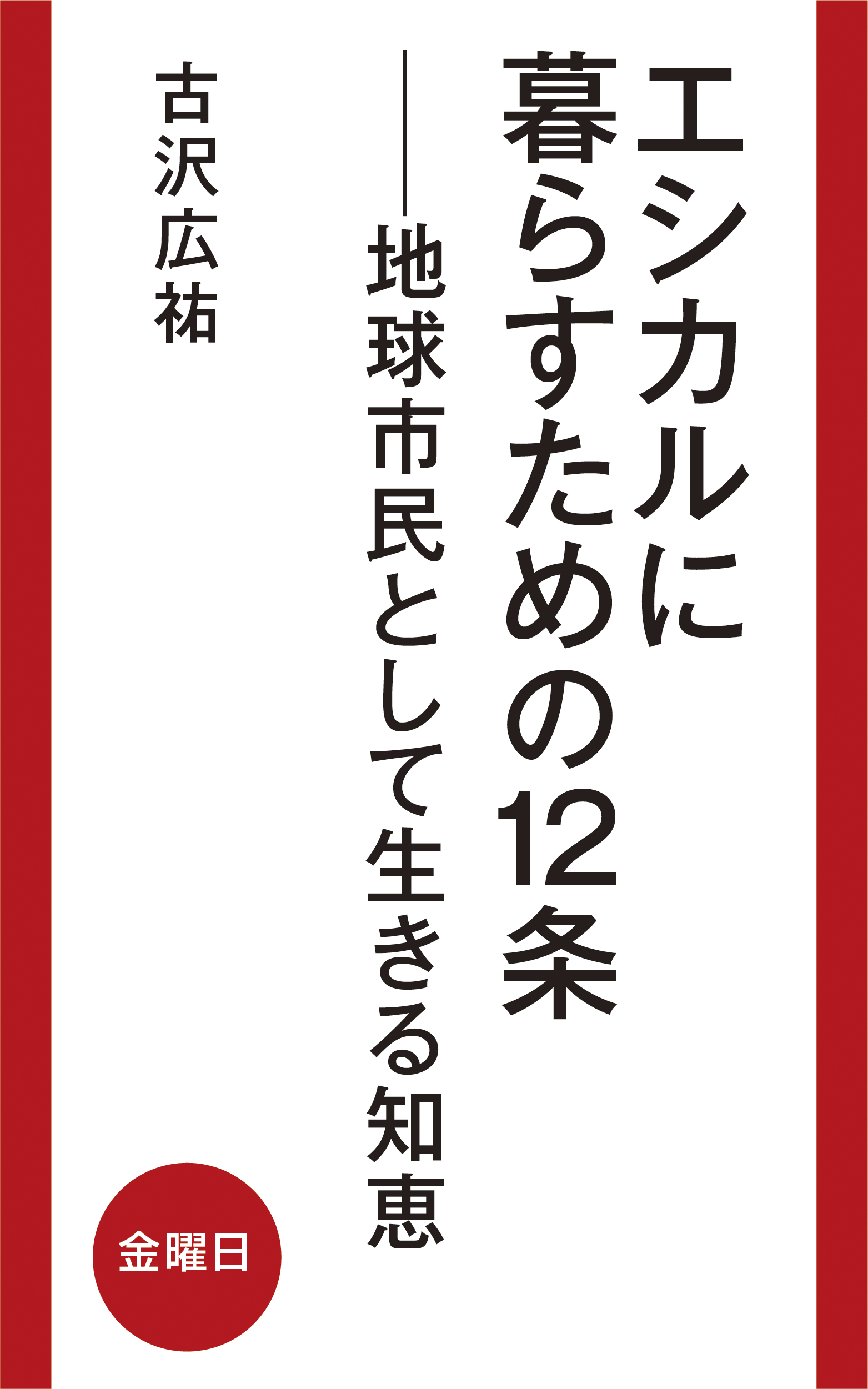災害復興・平和構築に女性の参画 女性や若者など多様な参画のある自治組織へ
山田道子・ライター|2025年4月1日10:22PM
災害復興や平和構築のプロセスに女性が参画することで持続可能な社会を達成する取り組みを「女性・平和・安全保障(Women,Peace and Security:WPS)」という。
国連安全保障理事会で「国際的な平和や紛争解決にジェンダー平等が必要だ」と明記したWPSに関する決議が採択されたのは2000年。それから25年となる今年、WPSの視点から災害・紛争地で支援活動をするNGOの報告会「災害、紛争下の女性たちの声、その尊厳のために」が2月7日、東京都内で開かれた。主催は、国内外で緊急人道支援を展開する特定非営利活動法人「ジャパン・プラットフォーム」。会合では、成果を踏まえて今後の課題とヒントについて話し合われた。

災害が続く日本で被災地の復興まちづくり支援に携わる「SEEDS Asia」事務局長の大津山光子氏は、国内外の被災地の現地再建に携わった。その体験から共通の課題として挙げたのが、従来の住民アンケートでは世帯主である中高齢男性の意見に偏りがちで、そのため住民の合意形成が難しいということ。
そこで、女性や若者、子どもの意見も集めて可視化していく事例を示した。それにより「多様な主体が参加することの価値が広く認識された」として「多様な主体が参画する自治組織への変革につなげること」の重要性を指摘。「さらに多様な女性の意見に配慮することが課題だ」と述べた。
「ピースボート災害支援センター」現地コーディネーターの辛嶋友香里氏は、地震・豪雨の二重災害に襲われた石川県輪島市で支援を続けている。自身のおむつをもらいに来た女性の窮状を例に「被災者は多様で、一人ひとりの困難をさまざまな角度から複合的にみていく必要がある。特に女性の声は多様な背景を含んでいるのでとても重要だ」と語った。
ビルマ(ミャンマー)からバングラデシュに逃れたロヒンギャ難民キャンプで、ジェンダーに基づく暴力への対策事業をする「ワールド・ビジョン・ジャパン」支援事業部プログラム・コーディネーターの池内千草氏は、「ジェンダー不平等については日本国内と基本的には同じ」と言う。
「役に立ちたい」人を発掘
事業の一環で、女性に対する啓発セッションやスキル研修などを実施し、「娘のしつけについて夫の意見を聞くだけだったが、自分の意見を言えるようになった」などの現地の女性の声を紹介。「地域社会に積極的に参加する女性が現れ、女性のコミュニティリーダーも増えた」と話した。一方、「女性は家父長制的な価値観が強い文化の中に住んでおり、活動参加に家長の許可が必要だったり、出ていくことに女性が気おくれをしたりという状況がある。二重三重の障害に同時進行で介入しないと物事が進まない」と指摘した。
「Reach Alternatives(リアルズ)」理事長の瀬谷ルミ子氏は、中東・アジア・アフリカで紛争やテロの予防事業や女性や若者を紛争解決の担い手として育成する事業などを行なう。南スーダンに行った時、育成事業に参加した女性が瀬谷氏に「私を差別しないでくれてありがとう」と語りかけてきたという。
その女性は、家族や地域の平和のために何かしたい気持ちをずっと持っていたが、学校に行っておらず読み書きができないので、村の情報にもアクセスできなかった。外国機関の人材育成プロジェクトで選ばれるのは教育を受けた男性ばかり。だが、リアルズは読み書きができなくても能力がある人を選ぶので、その女性も志願でき、後に続く女性のロールモデルになれたと感謝したのだ。
瀬谷氏は「現場では、何か役に立ちたいと考える女性がいても、気おくれして言わないなど潜在能力が見えないことがある。これを『見える化』して参画につなげなければならない。しかし参画といってもただ女性の数を増やすという数合わせだけではだめで、意識・意欲のある人材を選ばなければ逆効果のこともある。WPSでは『意味ある参画』を担保することが非常に重要だ。これは日本でも同じだ」と強調した。
非常時には平時の社会が反映されるもの。つまり日頃からWPSが反映される社会を作っておかなければならないということだ。
(『週刊金曜日』2025年2月28日号)