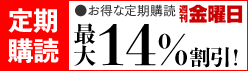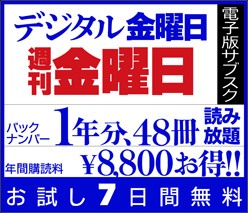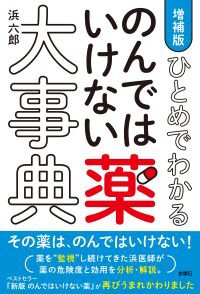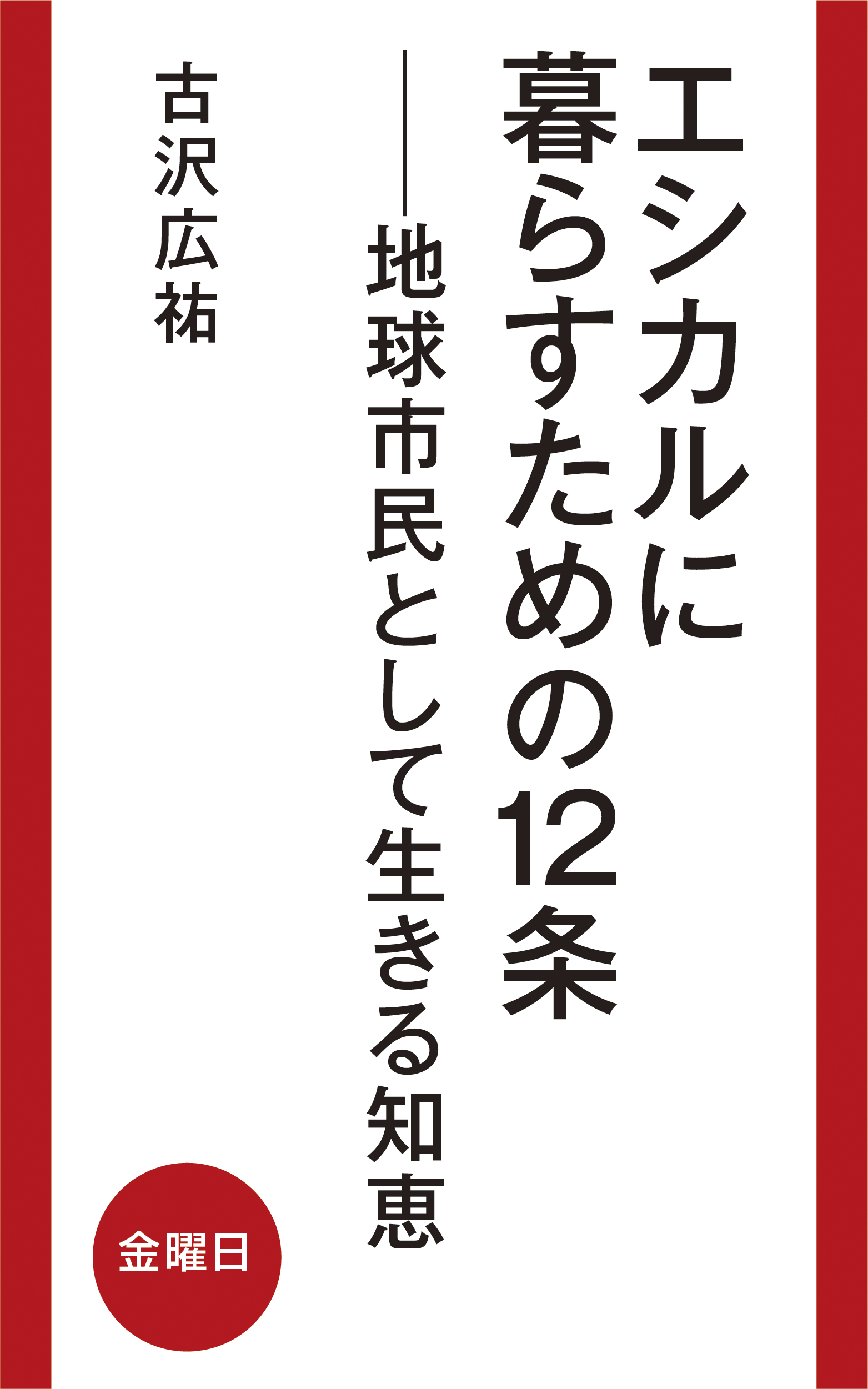【タグ】スクールカウンセラー|雇い止め
東京都のスクールカウンセラー大量解雇撤回訴訟 「更新4回限りの雇い止めはおかしい」
岩本太郎・編集部|2025年4月3日3:50PM
東京都の公立学校で働いてきたスクールカウンセラー(SC)が不当な雇い止めを受けたとして、都に対し職員としての地位確認と損害賠償などを求めた訴訟が東京地裁で進行中だ。2月15日夕刻、裁判を支援する労組の主催による「原告を励ます会」が東京・文京区内で開かれた。

問題が表面化したのは昨年1月のことだ。都内では2023年度末の時点で約1700人のSCが勤務しており、雇用形態は非正規の「会計年度任用職員」。かつては特別職非常勤という、基本的に1年ごとの任用ながらも本人が希望すれば更新される形だったが、20年4月の地方公務員法改正以降にこれが改められ、都が定める更新の上限(4回、5年まで)を迎えるSCが任用の継続を希望する場合は公募手続きへの参加が求められることになった。これを受けて1096人が5年目の公募に応じたが、結果は約4分の1にあたる250人が不合格になるという大量雇い止めが発生した。
東京公務公共一般労働組合心理職一般支部(豊島区、通称「心理職ユニオン」)には昨年1月以降、雇い止めされたSC約80人が労働相談。事態を重く見た同ユニオンは学校現場にも採用状況を調査のうえ、東京都教育委員会との交渉や折衝を重ねたが、都側の担当者からの回答は「会計年度任用職員の制度がそうなっているから」の一点張り。選考は履歴書や面接の結果のみで「これまでの業績評価などは一切考慮していない、との答えでした」(東京公務公共一般労働組合の原田仁希さん)。昨年10月には雇い止めに遭ったSC10人を原告とする訴訟が同ユニオンも支援する形で起こされた。
SCには心理に関する高い専門性が求められるほか、学校現場の教師や児童、保護者との信頼関係にその業務がよる部分も大きい。そうした職種を1年単位の短期で雇用する会計年度任用職員制度の矛盾がここでも露呈した格好だ。任用年限については国や各自治体で撤廃の動きも出ている(後述)中で、都が前記「4回、5年」の上限を根拠に現職応募者の約4分の1を、実績も顧みずクビにすることの理不尽さも指摘されよう。
「原告を励ます会」当日、冒頭で説明に立った前出の原田さんによれば、公募を受けて行なわれた採用試験では、いわゆる“圧迫面接”の例があったとの相談もあったとか。試験を経た24年度のSCの採用状況を見ても従来からの経験者より、むしろ教員などの未経験者のほうがよく採用されたのではとの節も感じられるという。
訴訟については第1回口頭弁論が昨年12月24日に終了。第2回は3月4日午前10時より東京地裁の611号法廷で予定されている。
原告弁護団長の平和元弁護士は「そもそも4回限りという上限に法的根拠がどこにもない」と指摘。過去の参考事例として、再任用が10回前後の非常勤保育士らの大量解雇をめぐり争われた東京都の中野区立保育園事件(07年に東京高裁で中野区に賠償を命じる判決。翌年都労委で和解が成立して保育士らが職場復帰)を挙げた。同事件以降、非常勤職員の更新については労組との団体交渉事項になっていたのが、その後の制度の変更によって奪われたのだ、と。
同弁護団事務局長を務める笹山尚人弁護士は、民間の場合は有期雇用労働者を期間満了で雇い止めとするのを禁じた労働契約法19条(いわゆる雇い止め法理)があるのに対し、公務員に関しては同様の法理が存在しないという歪んだ実態も問題の背景にあると説明。
続いて講演で登壇した立教大学コミュニティ福祉学部特任教授の上林陽治さんは、昨年名古屋市で表面化した保育士(会計年度任用職員)約1200人の雇い止め問題(※)など他の分野でも同様の事例が生じている一方、国が昨年6月、公募よりもすでに職場内で職務経験を有する者を任用した方が適当との理由で期間業務職員の「3年公募制」を廃止したほか、全国的に見ても会見年度任用職員の3~5年の公募を廃止する自治体が増えている現状を紹介した。
※本誌2024年10月18日号でも詳報。
【タグ】スクールカウンセラー|雇い止め