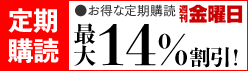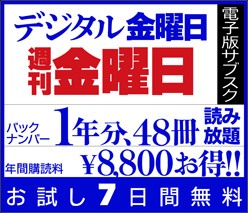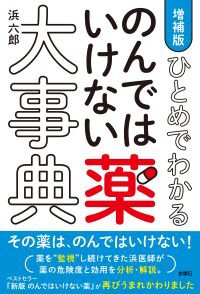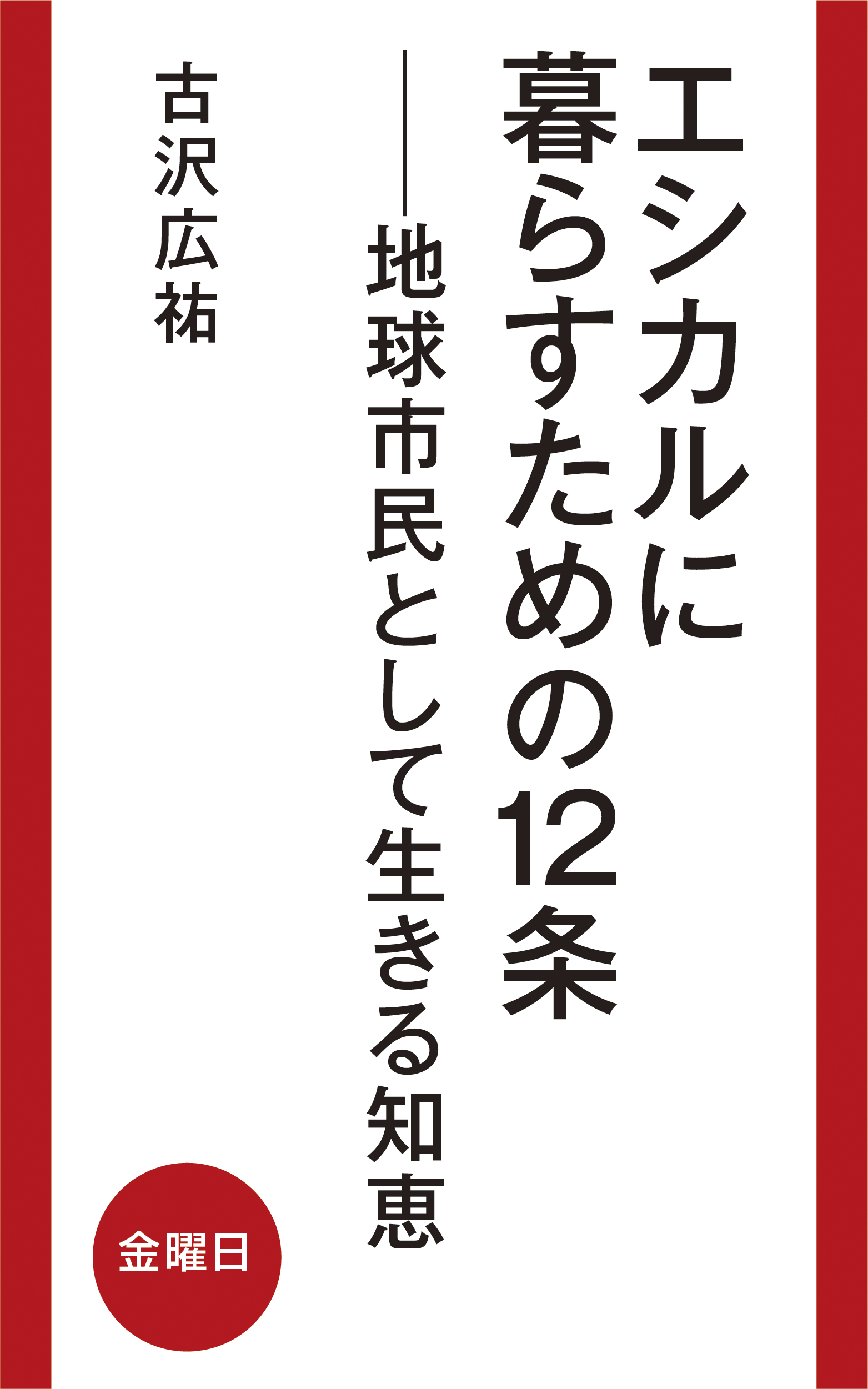【タグ】Black Box Diaries|伊藤詩織|想田和弘
ドキュメンタリー映画と倫理的責任 性被害サバイバーでも映画監督として免責されない
想田和弘・映画作家、『週刊金曜日』編集委員|2025年4月3日5:53PM
ドキュメンタリー作家であり、本年度ベルリン国際映画祭ドキュメンタリー賞の審査員も務めた想田監督は、映画が持つ力の大きさゆえに、作り手には高い倫理、誠実さ、透明性が必要だと語る。
映画界、とくにドキュメンタリーの世界は狭い。
伊藤詩織氏とは、シドニー映画祭とロンドン映画祭で遭遇した。拙作『五香宮の猫』と伊藤氏監督の『Black Box Diaries』が、両映画祭に招待されていたからである。

ロンドン映画祭では『Black Box Diaries』のチケットが売り切れていたため、僕は伊藤氏からチケットをもらって鑑賞した。その翌朝、伊藤氏とプロデューサーのハンナ・アクヴィリン氏とホテルの朝食会場でばったり会ったので、作品について質問をしたり、意見交換をしたりもした。
僕はニューヨークに住んでいたころ、プロデューサーのエリック・ニアリ氏や編集の山崎エマ氏とも同席したことがある。本作は、その許諾を巡る法的・倫理的問題について、映画監督やジャーナリストを中心に、さまざまな論者が激しい論争、時には感情的とも言える応酬を繰り広げている。そのメンバーのほとんどは友人である。
だから僕にとって本作について何かを語ることは、そもそも難しい。僕が男性であることも、ハードルを上げている。
ドキュメンタリー映画は本来、それぞれの作り手がそれぞれの手法で自由に作って公開すればよいものだ。したがって僕が他人の作品の作り方についてあれこれ論評すること自体、差し出がましいような気もしている。
しかし、本作はドキュメンタリー制作の手法や倫理について、図らずも重要な問題を提起している。いくら他人の作品といえども、ドキュメンタリーの作り手として看過できない問題を含んでいる。また、作品の手法や倫理について賛否両論が噴出し、問題が一作品の領域を超えてパブリックなものとなりつつある今、ドキュメンタリー界に身を置く者として、この問題を論じることから逃げるわけにはいかないとも感じている。
ただし、僕は裁判官ではない。誰かを断罪するためではなく、あくまでもドキュメンタリーの世界をより豊かでフェアなものとすることを願い、本稿を書く。
被写体に対する責任
まず、本件の議論を複雑にしているのは、性被害サバイバーである伊藤氏が映画の作り手となり、自らの事件について調査し告発していくという、前代未聞の作品の構造にある。伊藤氏も、時にはサバイバーとして、時には映画監督ないしジャーナリストとして、状況に応じて立場を使い分けているので、議論が混乱しているように見える。
だが、サバイバーとしての伊藤氏と、映画監督としての伊藤氏は、明確に分けて考える必要がある。
たとえば、本作では部分的に隠し撮りや隠し録音という手法が使われている。
性被害のサバイバーが、自分を守ったり、記録のために隠し撮りや録音をする分には、無断で撮(録)られる方は心外かもしれないが、それ以上の問題はないのかもしれない。
だが、その撮影素材や録音素材を映画の一部として使う、つまり映画監督として隠し撮りや隠し録音をするとなれば、とたんに問題になる。というより、基本的にはアウトである。少なくとも、大きな責任や倫理的問題が生じる。
ここで言う作り手の責任には、大きく分けて2種類ある。
一つは、被写体に対する責任である。ドキュメンタリーの作り手は、被写体のイメージを預かる立場である。カメラワークや編集の匙加減一つで、作り手は被写体を悪人にも、善人にも描くことができる。しかもそれを世界中に公表できてしまう。それほど強大な力、権力を持っている。下手をすると被写体を深く傷つけ、人生を台無しにしかねない。しかも経済的利得や名声を得るのはたいてい、被写体ではなく作り手の方である。こういう不均衡な権力関係をドキュメンタリー研究者のブライアン・ウィンストン氏は「ドキュメンタリーの原罪」と呼んだ。
だからこそ、作り手は被写体のイメージを可能な限りフェアに描くよう、そしてなるべく傷つけないよう、細心の注意を払わなければならない。
ドキュメンタリーは、鋭い刃物のようなものだ。有益なことにも使えるが、人を傷つけることもある。ある意味で、政治家などの権力者と同様、高い倫理や誠実さ、透明性が求められるのである。
隠し撮りや隠し録音は、被写体の立場からすれば、騙し討ちのように感じられる禁断の手法である。なぜなら人間は、映画を撮られていると思えば、それなりに振る舞うものだ。撮られているとは思わず、大きな声では言えない、ざっくばらんな話をしていたのに、それが知らない間に映画になって公表されてしまったら、大きなショックを受け、深く傷つきかねない。実際、自分が隠し録音をされていた事実を試写会で初めて知った西廣陽子弁護士は、大変なダメージを受けたように見える。
伊藤氏は性被害のサバイバーとして、隠し撮りや録音をし始めたのかもしれない。しかし、それを映画に使うかもしれないというアイデアが湧いた瞬間に、相手にはそのことを開示し、撮影や録音の了承を得る必要があったのではないだろうか。
もちろん、相手が何かを隠している権力者であったり、犯罪を隠している人であったなら、隠し撮りや隠し録音が許される場合もあるだろう。そういう意味では、伊藤氏の事件の捜査に携わった警察官の盗撮・録音の正当性については、議論の余地はあるだろう。ただし、それはあくまでも最後の手段として、である。しかも今回の警察官は、内部通報者としての性格も帯びているので複雑だ。
いずれにせよ、本作で伊藤氏が隠し撮りや録音をした相手の数名は、タクシー運転手や訴訟の伴走をする弁護士など、彼女の協力者である。したがって、撮影や録音をしている事実を開示し、許諾を得ることも可能だったのではないかと想像する。むしろ、なぜ許諾を得なかったのか、僕にはよくわからない。
観客に対する責任
ドキュメンタリーの作り手が負う責任の二つ目は、観客に対する責任である。
作品がドキュメンタリーであると明示されている場合、観客は暗黙のうちに、いくつかの前提を想定するものだ。一つは、その映画の内容が基本的には事実に基づいていて、被写体も実在しているということである。そして二つ目は、被写体からは撮影や録音の承諾を得ているだろうということだ。
僕自身、本作をロンドンで観た際に、さまざまな場面について「どうやって許諾を取ったのだろう?」と不思議に思った。このときに「許諾を取ったのだろうか?」と疑問に思わなかったのは、許諾を取ることがドキュメンタリーの当然の前提になっているからである。
この映画は世界中の映画祭で称賛され、米国のアカデミー賞にもノミネートされ、ロンドン映画祭では上映後にスタンディング・オベーションが起きた。その観客のほとんどは、伊藤氏が被写体から許諾を得ているとの前提で映画を観て、感銘を受けたのだと思う。
しかし、自分たちが観ている映像や音声が、隠し撮りや隠し録音によって得られたものだということが開示されていたら、どうだろうか。反応や評価も違っていたのではないだろうか。なぜならそこには倫理的な疑義が生じるからである。
伊藤氏は海外でのインタビューなどで、本作が日本で公開されていない事実を強調している。そしてその際、隠し撮りと隠し録音の事実や、元弁護団などから法的・倫理的問題が提起されていることにはほとんど触れず、性被害者が声を上げにくい日本の文化・社会構造が公開を阻む理由であると説明している。
たしかに日本社会は、男尊女卑で性被害について語りにくい社会である。だが、今回この映画が公開されないのは、隠し撮りや隠し録音という手法が使われ、法的・倫理的問題が懸念されているからであり、文化的・社会的な問題ではない。むしろ法的・倫理的問題がクリアされていれば、上映したい配給会社や映画館はいくらでも見つかることであろう。
ドキュメンタリーの映画監督として、作品の状況について事実と異なる説明を行なうのは、観客に対する責任を全うしていないように思える。また、伊藤氏が隠し撮りや隠し録音について海外で触れようとしないことは、彼女がそのことに後ろめたさを感じていることを示しているようにも思われる。