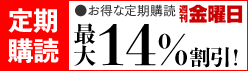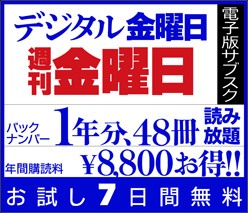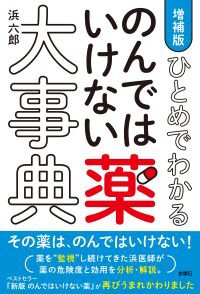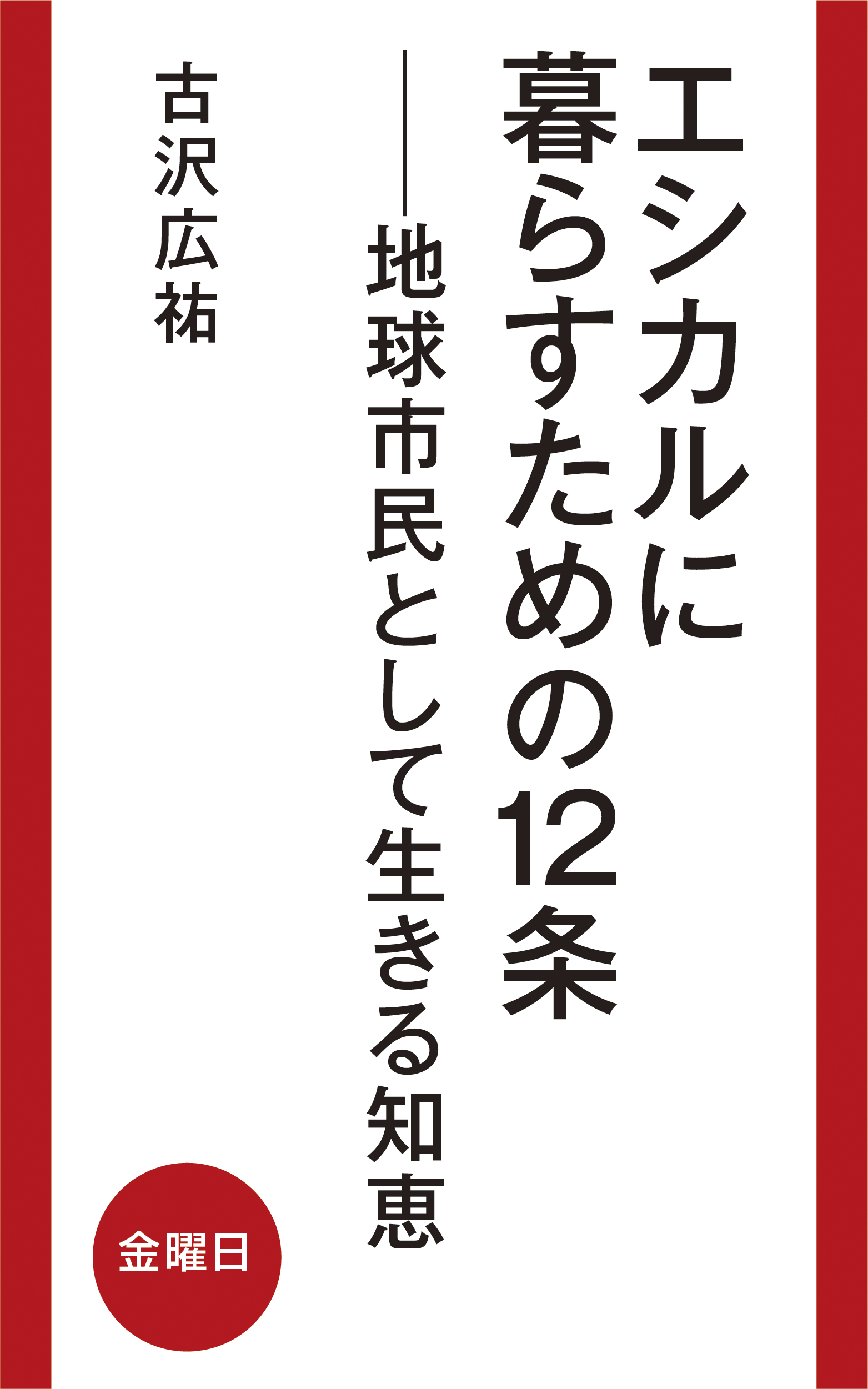映画『Black Box Diaries』伊藤詩織監督に聞く 「日本へのラブレター」届くと信じて
石橋 学・『神奈川新聞』川崎総局編集委員|2025年4月3日6:10PM
国内では未公開ながら、その手法も含めてさまざまな議論の只中にある『Black Box Diaries』。事件のあった2015年4月のあの日からもうすぐ10年──。パリからリモートでいまの思いを語ってもらった。
伊藤詩織・1989年生まれ。映像ジャーナリスト。BBC、アルジャジーラ、エコノミストなど、主に海外メディアで映像ニュースやドキュメンタリーを発信している。2020年米『TIME』誌の世界で最も影響力のある100人に選出される。著書に『裸で泳ぐ』(岩波書店)、『Black Box』(文藝春秋)など。『Black Box』は10カ国語/地域で翻訳されている。19年『ニューズウィーク』日本版の「世界が尊敬する日本人100」に選ばれる。22年には「One Young World」世界若手ジャーナリスト賞を受賞。

──アカデミー賞の授賞式はどうでしたか。
10年間一緒に映画を作ってきた友人たちとあの場に立てて、誇らしい思いでした。想像より会場がこぢんまりとしていて、みんなとの距離を近く感じられたのもうれしくて。撮影や編集で助け合った仲間でお祝いし、ねぎらい合いました。本当によく生き抜いてきたね、と。
──上映も57の国と地域で行なわれています。
ここまで共感が広がり、多くの人とつながれるとは思っていませんでした。性暴力や権力による抑圧は、残念ながら普遍的な問題として世界に蔓延っているのだと理解しています。
──400時間超のテープを4年がかりで編集したそうですね。
ドキュメンタリー監督でもある山崎エマさんと共同で行ないましたが、私はつらくなるとスイッチが切れたように突然寝てしまうことを繰り返していました。トラウマから心と体を守るすべだったのだと思います。いつ意識を失ってもいいように寝るスペースが作業部屋に設けられましたが、次第に寝落ちすることもなくなっていきました。
──傷が癒やされた、と。
思い出したくない記憶、消されていた記憶と向き合い続け、自分に何が起きたのかを整理できたのだと理解しています。米国の精神科医、ジュディス・ハーマンのバイブル的名著『心的外傷と回復』には、回復とは自分のストーリーを再構築して社会と個人をつなげていくことだと記されています。映画づくりはまさにそのプロセスでした。
「完璧なる被害者像」を壊したかった
──心がけたことは。
性暴力の被害当事者で、監督であり、ジャーナリストでもあるという三つのバランスをずっと考えていました。映画づくりでは客観的な見方が求められますが、サバイバーとしての視点も入れたかった。これまでサバイバーの視点で描かれた性暴力に関するドキュメンタリーを見たことがなかったからです。
日本社会に限らず、求められている被害者像があると感じています。警察からは泣かないと信じられないと言われ、記者会見ではリクルートスーツを着るべきだとアドバイスされました。取材に応じても思いが伝わらない、言葉が変えられるという経験もしてきました。そんな「完璧なる被害者像」を壊したかった。一人一人感じ方は違うし、人は被害者としてだけ生きていくわけではありません。
──『Black Box Diaries』のテーマも「その後」ですね。
はい、被害そのものではなく、その後に起きたことです。性暴力事件の捜査の仕方や逮捕状が止まってしまったこと、当時の刑法の不十分さ、それらを取り囲む社会、それをどう報道したか、しなかったのか、です。
──被害を公表したのは事件から2年後の2017年でした。
被害者として求めた捜査が尽くされ、逮捕状も執行され、刑事司法で裁かれていたら私は記者会見をしなかったでしょう。会見を開いて、なぜ捜査が止まったのかという質問を日本のメディアや記者にバトンとして手渡したかったのです。でも、誰が逮捕を止めたのかは分かっても、なぜ止めたのかというところには至らなかった。そうであれば、同じようなことがもう一度起きてしまうかもしれない。そのことを重く考えました。