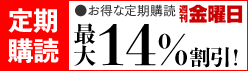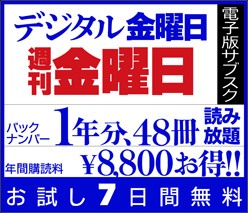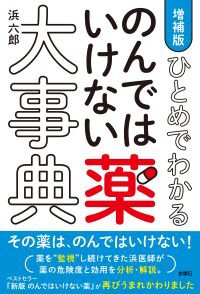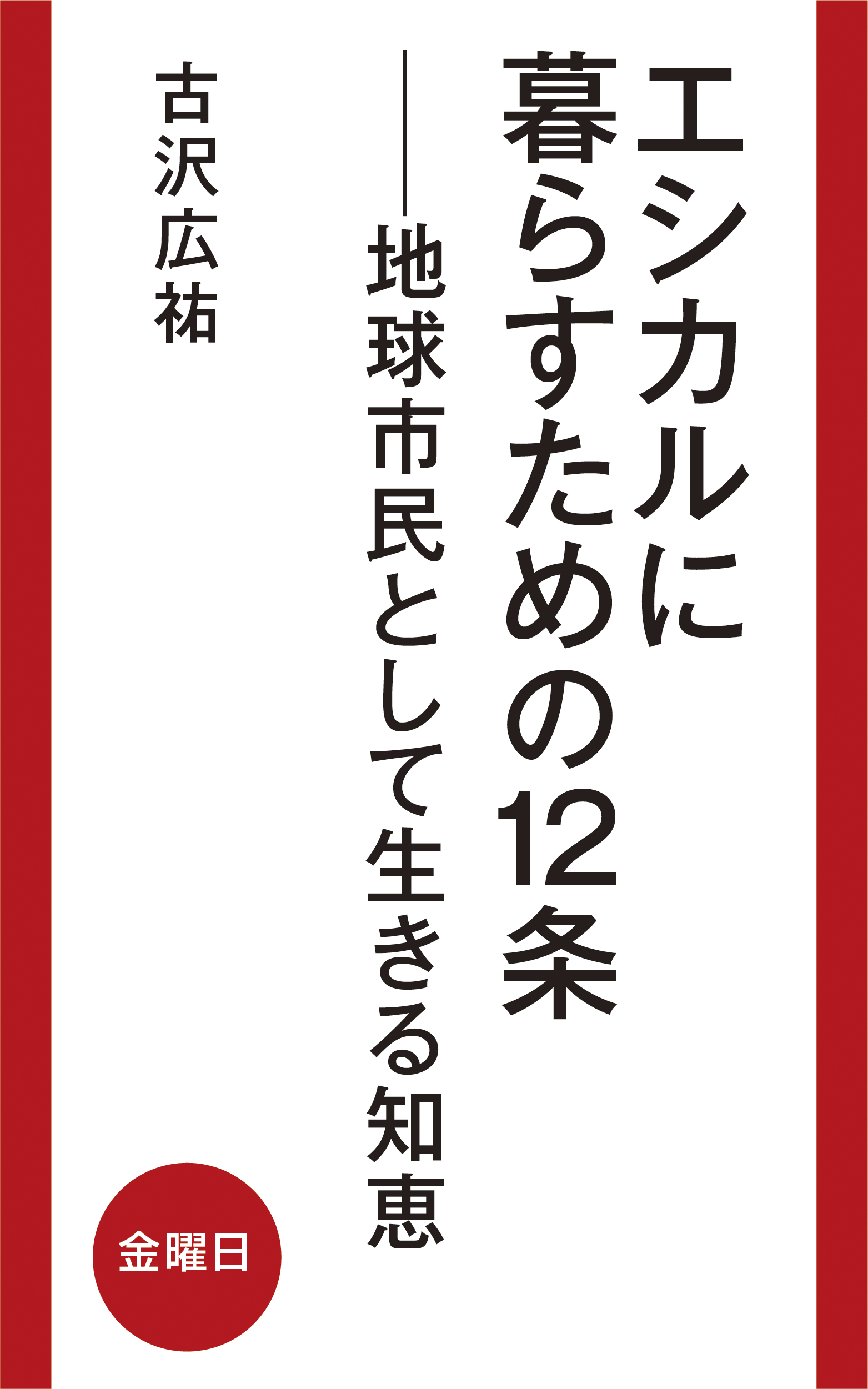ウクライナ侵攻から3年、戦場ジャーナリストが報告 ある「音楽家」の死から見えてきたもの
五十嵐哲郎・戦場ジャーナリスト。元NHK報道番組ディレクター|2025年4月3日6:56PM
家族に1年間会えぬまま
そのまま一晩、宿営地で過ごすことが許可され、翌日までの滞在となった。指揮官と通訳兵が本部に引き揚げた後は、翻訳アプリを介しての会話となった。
武器の整備や食事などを終えた自由時間、ヴァシールは家族のことを話してくれた。妻も音楽教員をしていて、20歳の息子と14歳の娘も楽器に親しんだ音楽一家なのだという。こちらも日本に妻と2人の子どもがいることを伝えると、まるで同志を得たかのような雰囲気になり、互いにスマートフォンに保存されている家族の写真を見せ合った。しまいには、ヴァシールがビデオ通話アプリで妻のテティアナと連絡を取り、画面越しに紹介されてしまった。
聞けば、ヴァシールは開戦直後の動員に応召し、丸1年間、家族と会っていないという。まとまった休暇を取れず、西部リビウ州の自宅から次第に離れる形で転戦を重ねていた。兵員不足に悩まされ、交代要員を十分に確保できていないウクライナ軍ではよく耳にする話だ。戦争が長引くことを予想できなかった兵士たちにとって今も深刻な悩みとなっている。
何を一番望んでいるのかを彼に聞いてみた。
「多くの若者が死んでいるこの戦争を、なるべく早く終わらせたい。若者たちが、人生の豊かさを経験する間もなく亡くなっている。もっと生きて、人生の醍醐味を味わってほしい。妻と2人の子どもたちが待っているから早く家に帰りたい気持ちもある」
出会った明くる日の昼すぎ、再び任務へ戻ろうとしていたヴァシールと別れを告げた。「戦争が終結したあかつきには必ずや再会してうんと酒でも飲もう」と約束を交わし、筆者は日本へと帰国した。

戦争に対する意識の変化
訃報に触れてから、ヴァシールがバヤンを演奏したときの映像を何度も見返した。コサックを讃(たた)えた民謡を口ずさんでいるうちに、彼が話した「人生の豊かさ」が何だったのか、その真意を探りたいと思うようになった。そして取材資金に目途が立った昨年10月、再びウクライナへと向かった。ヴァシールの死からすでに3カ月が経とうとしていた。
久しぶりに足を運んだ現地は、様相がだいぶ変わっていた。夜間の外出禁止令がかなり緩くなっていた首都キーウには日常生活が戻っているように見えた。空襲警報が鳴って初めて戦時下であることを思い出すくらいで、警報音を気に留める人はまったくといっていいほどいない。前線取材のために東部へと移動してからも同じで、緊張感が漂うのは前線にごく近い限られた地域だけとなっていた。
深刻な兵員不足のせいか、かつては各地に張り巡らされていた検問所もだいぶ減った。ウクライナ側の最終検問所でもノーチェックで出入りできてしまう場所があり、ロシア兵が紛れ込んでこないか不安を覚えるほどだった。
しかし、一番の変化は市民たちの戦争に対する意識だろう。これまで三度の渡航で親しくなった何人かに話を聞いて回ったところ、「早期の戦争終結」を望む人が確実に増えていた。これはロシアに占領されている領土の喪失を容認する意味を含むものだ。
キーウ国際社会学研究所が24年11月当時に発表した世論調査でも、「一部領土の喪失を容認してもよい」と答えた人は32%と前年同月比より18ポイント増えていた。「全領土の奪還まで戦い続けるべきだ」と考える人は58%で22ポイント減だった。今年1月発表の最新調査では、それぞれ38%と51%で、全体として「領土喪失の容認」が少しずつ増えている。
街場からは戦争の臭いが薄まり、ウクライナ国内でも戦争が局地的なものと捉えられるようになっていた。表立っては言わないにしても、「一握りの兵士たちが戦うもの」という認識が市民の間で広がっているのを感じた。
最も驚いたのは、ある青年の意識の変化だ。「非国民扱いをされるので公に話すことはできない」としながら、「戦争を支持する気持ちを失ってしまった」と明かしてくれた。年齢は30代半ば、学生運動でマイダン革命に参加した経歴の持ち主だ。以前は「国境線が14年時点に戻るまでどんな犠牲を払ってでも戦い続けるべきだ」と主張していた。筆者が領土を諦めての即時停戦はどうかと聞いただけで「ウクライナの心を理解していない」と叱るような青年だった。
「国を守るために国民が消費し尽くされるのは本末転倒だ」「腐敗と汚職が蔓(まん)延(えん)している現政権にはほとほと失望した」。考えが変わった要因をいろいろと教えてくれた。が、さらに聞いていくと、徴兵制の強化が心変わりの大きな理由ではないかと感じられた。
ウクライナ政府はこれまで、徴兵対象を18歳以上65歳未満としつつ、運用上は25歳以上の一部国民に限定してきた。しかし、兵力不足が深刻となった昨年の半ばから、運用を厳格化する形での徴兵強化が加速した。
青年は「自分は兵士として使い物にならないし、兵士になる覚悟もない。ましてやこんな国のために塹(ざん)壕(ごう)で死ぬのはまっぴらごめんだ」とまで言い切った。もっとも、「自分が徴兵される不安から停戦を望むようになったわけではない」と言葉を足したが、本心とも思えなかった。
「人生の豊かさ」とは何か
ウクライナの変化を肌で感じつつ、ヴァシールの遺した言葉について取材を進めた。共に戦っていた兵士たちは、彼の言葉をどう解釈するのか。その答えを求めて分隊の戦友を捜した。しかし12人いた兵士はみな、すでに散り散りとなっていた。原隊に残っていたのは2人だけ。しかもロシアへの越境攻撃へと転戦していたため、取材は叶わなかった。負傷による戦線離脱が1人、部隊転属が2人、家庭事情での除隊が1人、それに脱走したと噂された兵士が1人。残りの4人は消息を掴めなかった。
そのうち負傷して部隊を離れていたイヴァンが取材に応じてくれた。宿営地で会ったときにはまだ23歳で分隊の最若手だった。その後、戦闘中に砲弾の破片に当たり、大怪我をしていた。8カ月に及ぶリハビリを経てようやく杖なしで歩けるほどに回復したものの、ひどい抑鬱状態が続いていた。
イヴァンがヴァシールと出会ったのは、開戦直後の練兵所だったという。軍歴のあったヴァシールが、大学を出てまだ間もない志願兵のイヴァンに、武器の扱いから車の運転、兵士としての心得などさまざまなことを教えた。折に触れて音楽に触れる機会も作ってくれた。2人きりで話すときには決まって早く家庭を築くよう諭し、イヴァンの結婚式でバヤンを演奏するのを楽しみにしていたという。
ヴァシールは自分の帰りを故郷で待つ息子に重ねていたのではないかとイヴァンは推測する。早くに父親を失っていたイヴァンも、ヴァシールを実の親のように慕い、いつしか家族のように思うほどになっていた。
ひとしきり思い出話を聞かせてもらった後、ヴァシールの言う「人生の豊かさ」が何を意味していたと思うかイヴァンに尋ねた。しばらく考え込んだイヴァンは「音楽だろう」と答えた。
「音楽そのものもそうだし、音楽で作り出す幸せな時間を友人や家族と楽しむことなんじゃないか。しんどい任務から戻ったときには励まされ、救われることがあった。兵士でいることを忘れられるくらい良い時間だった。そんな僕らを見て、ヴァシールはすごくうれしそうにしていたんだ」
ヴァシールの故郷を訪ねて取材を続けた。出身地はポーランド国境にほど近い、小さな町だった。穀倉地帯が広がる一帯はウクライナ国内でも経済的に豊かな場所とはいえず、ヨーロッパ各国への出稼ぎで生計を立てる家庭が多い。
ヴァシールが兵士になる直前まで勤めていたのは、国立の音楽学校だった。ウクライナでは小学生から高校生まで音楽を学べる学校が各地に整備され、専門の教員も配置されている。一般科目を通常の学校で学び、放課後に専門教育を受けられるシステムだ。ヴァシールが務めた学校は、彼の欠員分を埋めることができず、本格侵攻直後に閉校してしまった。
元同僚たちは近くの学校にそれぞれ転勤していた。一緒に子どもたちに民族楽器を教えていた女性教師は、ヴァシールの死をまだ受け入れられない様子だった。ヴァシールは、戦地に赴いてからもオンラインで教員としての役割を果たしていた。地域のイベントや発表会の前、そして軍への寄付を呼びかける演奏会の開催にあたって画面越しではあるものの、かつてと変わらぬ優しさで、子どもたちを励ましながら熱心に指導していたという。それだけに、いまでもパソコン越しにヴァシールと会えるのではないかと錯覚するのだという。
「ヴァシールは音楽、子どもたち、そして教員という仕事を愛していました。『人生の豊かさ』ですか……。なんでしょうね。いろいろあると思いますが、同僚として言えるのは、教え子が何かを達成したときの喜びが必ずそこには入っていたでしょう」