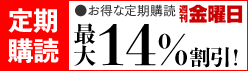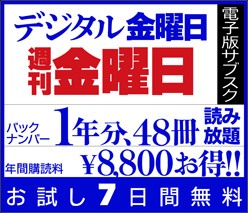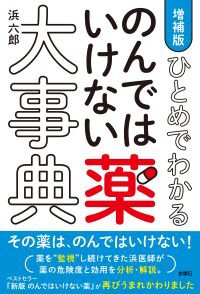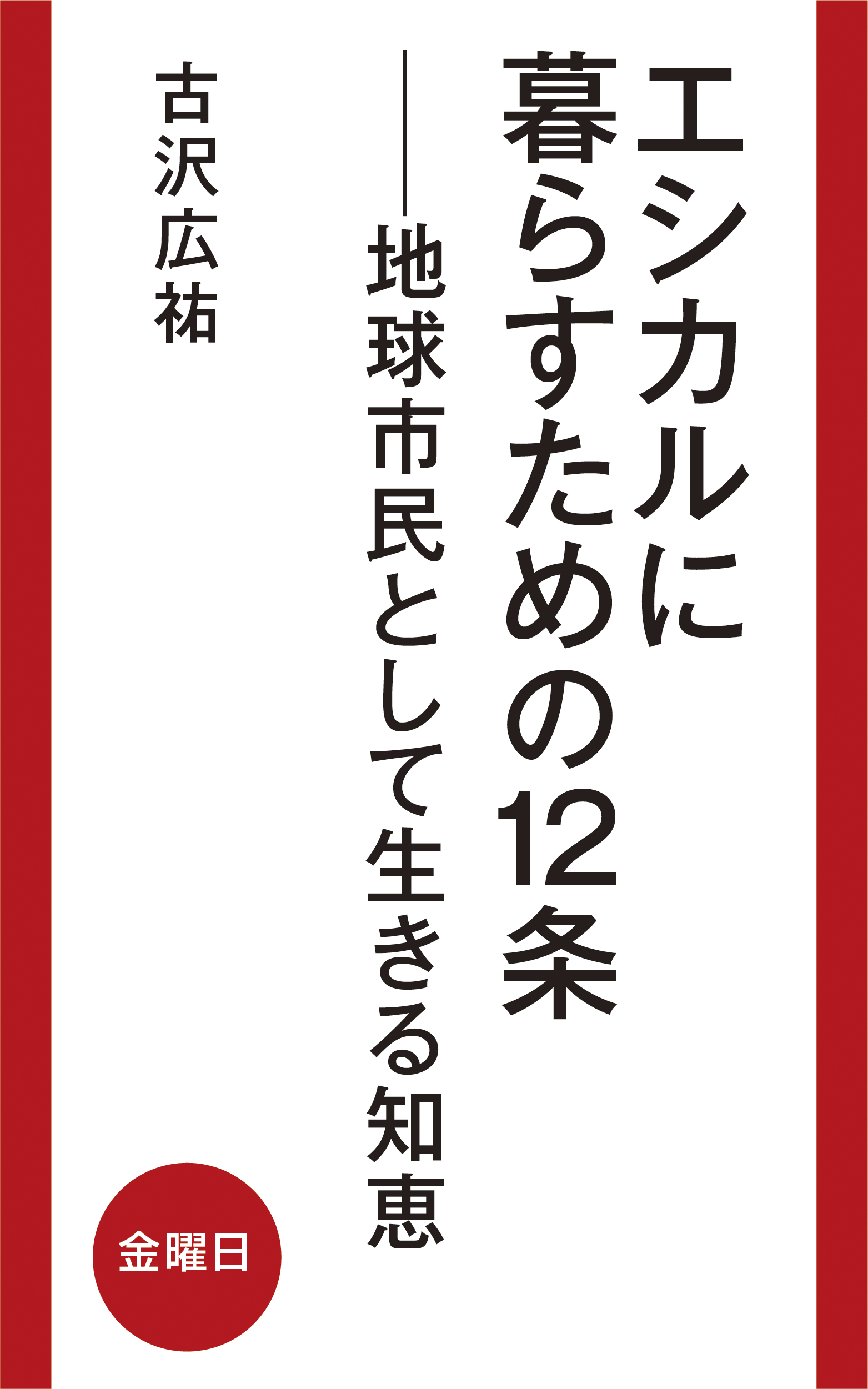国籍の壁で将来を閉ざされる外国籍教員 戦後の始まりに埋め込まれたレイシズム「当然の法理」
中村一成・ジャーナリスト|2025年4月14日6:21PM
「定額働かせ放題」と揶揄される給与制度見直しや事務負担軽減など、公立学校教員の処遇改善が語られる中で、捨て置かれた問題がある。外国籍教員の任用差別だ。
「公務員に関する当然の法理として、公権力の行使又は国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とするものと解すべき」。1953年の内閣法制局、高辻正巳氏のこの見解(高辻回答)を基に、外国籍教員について文部科学省は、管理職になり得る「教諭」採用を認めず、国に従属する大半の教育委員会は「任用の期限を附さない常勤講師」として遇してきた。
昇進のない「二級教員」の存在は、人事編成にも悪影響を及ぼしているが、文科省は「当然の法理」に固執し、外国籍教員を等しく扱うことを拒み続ける。そこからは、「戦後」のスタートにレイシズムを埋め込んだこの社会の病理、克服すべき宿痾が浮かび上がる。

主任任命に「待った」
和歌山県海南市の小学校で英語を教えるルーク・ザレブスキーさん(78年生まれ)が、「当然の法理」に直面したのは4年前だ。
オーストラリア南東部で生まれ育った。大阪外国語大学(現・大阪大学)での留学を経て、和歌山大学に学んで教員免状を得た。
「自分の学びを日本に還したい。何よりも子どもが好きなので」
2003年、中学の英語教師として採用された。県内初の外国籍教員のひとりだった。「まだ若かったし、教諭採用でないことの意味は深く考えていなかった」
多忙だが充実していた。ルークさんとの出会いを通じて世界に目を向ける生徒も多かった。「北京大学に入学した子もいました。『米国に行く』と言った子の保護者から、『あなたの影響だ』と怒られたこともありましたね(笑)」
いつの間にか指導的立場になった。そんな21年の秋のこと、校長に言われた。来年も主任の仕事をしてもらいたいが、任命できない、と。この年の春、学年主任に就いたのだが、教育委員会が「待った」をかけた。「教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる」とした学校教育法施行規則が根拠だった。年度途中で人事はできないと校長が抗い、解任の屈辱は避けられたが、翌年は降りてほしいというのである。
「主任になりたいわけじゃない。免状を持って採用試験に受かって同じように働いてきたのに、私は制度上、培ってきた経験を若い人たちに伝えることが許されない」
それでも職場では頼りにされる。そのギャップも苦しかった。「悔しいし切ないですよ。子どもの最適な環境を思って練った校内人事が、官僚の見解で妨げられてしまう。この先20年間も『これは駄目』『あれは駄目』ですよ……。もう別の道を行こうと思った」
組合仲間の説得で翻意し、小学校の専科になった。市域にある複数の小学校で英語を教える。最低、週24時間がノルマの日々だが、他者/他言語と出会った子どもの笑顔が疲れを打ち消す。一方であの悔しさは燻り続けている。
「英語教育と言って外国人を迎えるけど、この制度設計で外国人は働けない。授業はやってもらうけど後は……それでいいのですか」
和歌山で家庭も築いた。故郷での生活は考えられない。だからこそこの地で「対等に、共に生きる社会」に向けた発信をする。「日本国籍を取ろうと思ったこともありますよ。でもそれは問題の解決にはならないです。私は外国人であっても教師という職業を十全にさせてもらいたいのです」
短兵急の制度設計
「当然の法理」、それは植民地主義の遺制である。後発帝国主義国として対外侵略を重ねた日本は1945年9月、敗戦を迎える。「西欧列強の欺瞞」と訣別し、世界に新たな価値を発信する契機だったが、やったことは「継続」だった。
一つは朝鮮人対策である。政府が最初に強行したのは、旧植民地出身者の参政権停止だった。47年、天皇裕仁最後の勅令「外国人登録令」で、在日を監視・管理、追放の対象とした。翌年に朝鮮人学校を否定する通達を出し、51年には出入国管理令を施行。翌年の占領終結と同時に、在日の日本国籍は一方的に喪失とされた。外登・入管体制の完成である。差別の根拠の大半は、これら議会を経ない勅令や通知・通達だ。この国は「戦後」という時空の始まりにレイシズムを埋め込んだのだった。
「封じ込めありき」の短兵急な制度設計は、現実との齟齬をもたらした。当時は一定数、朝鮮人の国家公務員がいたのだ。自治体から内閣官房に寄せられた質問への答えが先の「高辻回答」だった。
一方で在日二世を中心に、「二級市民」扱いへの「否」は高揚していく。契機は70年代の日立就職差別裁判闘争である。その流れの中で国籍条項への闘いも取り組まれた。大阪市の民間保育園の公立移管に際し、中国籍の職員が解雇されたことを巡る運動である。当事者の徐翠珍さんと支援者の闘いで、大阪市は73年に徐さんを採用した。翌年には大阪府市、東京を皮切りに教員採用の国籍条項撤廃が広がっていくが、国は差別の上塗りに出る。73年、高辻回答の対象を地方公務員にまで拡大したのだ。
82年8月には国公立大学教員の国籍条項撤廃が実現するが、ここでも政府は差別を強化してきた。直後の文部次官通達「同法の施行について」である。そこにはこう記されていた。「なお、国、公立の小、中、高の教諭等については、従来どおり外国人を任用することは認められないものであることを念のため、申し添えます」