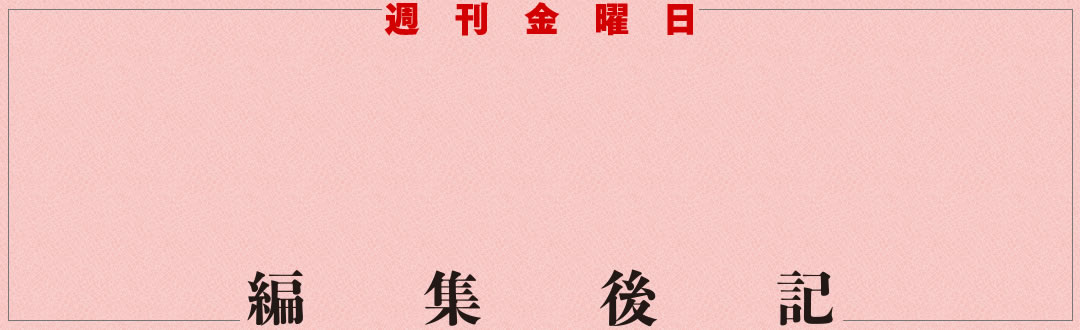982号
2014年03月07日
▼世の中には、どう贔屓目に見ても適任とは思えぬ人物がそれなりの社会的ポジションを占めてしまう事例が珍しくない。福島県の「県民健康管理調査」検討委員会の山下俊一前座長は、その典型だろう。3年前の3月20日から数日間、「甲状腺が影響を受けるということはまったくありません」だの「(ヨウ素剤を服用しなくとも)まったく心配ありません」、「(子どもは)どんどん外で遊んでいい」等の繰り返された数々の放言を振り返ると、絶句するほかない。以前、山下氏を県の公職から罷免するよう求める住民の記者会見が開かれた際、発言中の一人が「この男のためにどれだけの親が子どもを被曝させて後悔していることか」と、泣き始めた。当人はきれいさっぱり忘れた風だが、言葉の異様な軽さはともかく、これほど「良心の呵責」というものの存在を微塵も感じさせない人間は希だ。「3・11」は忘却の一途にあるが、忘れていいことと悪いことがある。県で小児甲状腺がんが増大しながら、山下氏が何ごともなかったように今も振る舞えるほど、この国の子どもの命は軽いのか。(成澤宗男)
▼今週号の座談会で野田聖子氏も述べているが、「男社会で女性の数が少ないと女性性を強調するか男性化するか両極端に走りやすい」という傾向は研究者や政治記者たちも指摘する。「女に何ができるか」という敵対意識の中で生き残るには、反感を買わないよう「愛されキャラ」になるか「強面キャラ」でねじ伏せるかどちらかになりがちということ。英国のサッチャー元首相が「鉄の女」になったのは後者の例だろう。韓国大統領もそうかもしれない。日本の政治家にも思い当たる人はいる。
実施が近いフランスのパリ市長選では、主要候補5人がすべて女性。だから「女性」ではなく「一政治家」として判断される。フランスも女性差別の強い国だが、制度を整えてここまできた。日本も実現できないはずはない。そのためには女性たちの努力と党派を超えた連携も必要だ。
「女の敵は女」という垢にまみれた言葉は分断を願う男性の発想。そんなものに惑わされず「女が女の味方をしないでどうしますか」(長谷川時雨)の気持ちで手を組みましょう。(宮本有紀)
▼2014年版角川『俳句年鑑』(昨年12月発行)の合評鼎談は3・11への言及が多い。西山睦さんは〈季語の陰影が濃くなっている〉〈思いが深く広がって作者の内面に入っている〉と指摘。仁平勝さんは、筑紫磐井さんの句「権力の心地よき風君にも吹く」を引き、〈権力というのは、強権を前面に出すかたちでは現れてこない〉〈放射能汚染問題でも、政治家が「心地よき」言葉を語る時は用心しろということですね〉と述べた。さらには、権力の補完装置を果たす心地よさへの警戒も必要だろう。
あの日から3年近く経ったが、復旧や復興は進んだとは言えない。追悼や祈りの式典がさまざまな場所で開かれるのを機に今後のあり方に思いをはせたい。その一つを紹介する。「日本の司法を正す会」を小誌と共同主宰する村上正邦さんが世話人代表を務める「祈りの日」式典は、3月11日午後2時?5時、東京・憲政記念館で開かれる。佐藤栄佐久・前福島県知事らが講演、参加費は無料。事前申し込みは同事務局=TEL 03・3500・2200。(伊田浩之)
▼私のような捻くれ者は本屋に行っても新刊や話題書の類のものはほとんど手に取らない。自分が選んでいるのか、選ばされているのかわからなくなるからだ。最近は、どこの本屋に行っても画一的で、同じような出版社の同じような商品が同じように陳列されている。この“小さな”括りの中で、面白い本だとか、売れ筋本だとかを宣伝されてもピンとこないし、到底納得は出来ない。もう少し個々の本屋で独自性があっても良いのではないか。小社の営業力不足は棚に上げるが、右向け右の本屋の品揃えに違和感を覚える今日この頃。
政治の世界もそうだ。いつの時代も時の権力者は、民衆の選択肢を狭めては思考力を低下させてきた。選んでいるつもりが選ばされているのだが、巧みにそれに気づかせないようシステムを構築する。
さて、3月1日からジュンク堂池袋本店にて面白いブックフェアが始まった。昨年末、小誌で特集した「食を哲学する」本99冊を中心に集めた催し。多くの選択肢から選びに選んで、この春、食を哲学してもらいたい。(尹史承)