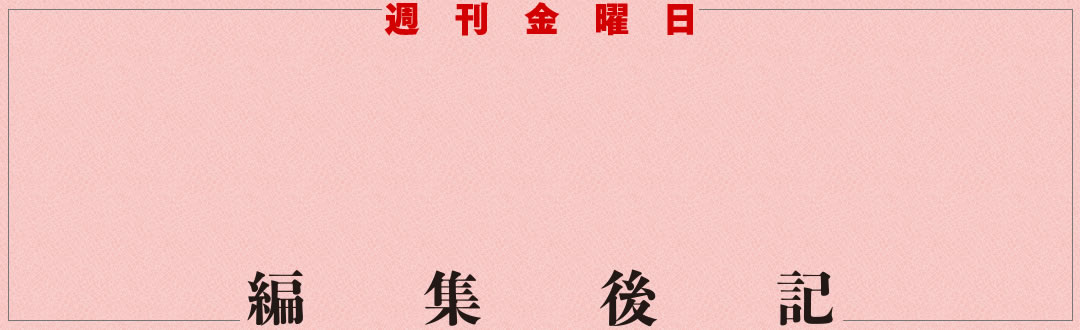984号
2014年03月21日
▼ついに消費税率8%です。家計に与える影響は深刻ですが、これがゴールではありません。消費税率10%、今号特集で浦野広明先生が指摘する各種控除の縮小、アベノミクスによる物価上昇、稲毛由佳さんが指摘する労働環境の悪化、社会保険料の値上げ、年金額引き下げなどが重なれば、「庶民いじめ」が本格的にスタートするということに尽きると思います。
浦野先生はじめ多くの税理士さんが集まって、「消費税の増税に反対する税理士の集い」が、3月28日(金)午後6時?8時、東京税理士会館(JR千駄ヶ谷、代々木駅)で開かれます。記念講演は、やはり今号の特集に登場した岩本沙弓さん。専門家による集会ですが、一般の方々もちろん参加大歓迎だそうです。ぜひどうぞ。
そしてもうひとつ。エコへの切り札とされ、国土強靱化の名の下に進められている「スマート化」。でも国や企業の目的は、エコや脱原発とは違うところにある気がします。「スマート日本見聞録」は3回の短期集中連載。スマート化を考えるきっかけにしていただければと思います。(渡辺妙子)
▼被災地の夜は寒く、暗いのだが、まちに時折ほのかな明かりも見える。そのひとつ、仮設の飲み屋で、地元の人や支援者らと話し込んでいたとき、こんな話がでた。
「絆っていわれていたけど、あれはちょっと違うと思うんだよね。いうなら縁じゃないか」
飲み屋をでると次は仮設のカラオケ店。昼間、底抜けに明るかった人は、中島みゆき「命のリレー」をなんども熱唱していた。
複雑な現実を、ときに単純化して眺めてみたり、ときにかっこいい物語に自分を落とし込んでみたりすることもある、と、その人はいう。バネが必要なのだ。
でもそれは「絆」なのか。マスメディアがさんざん叫んだこの言葉の先に、いま目の前に広がっているのは「戦後レジームからの脱却」と、近隣諸国との際限のない不穏な応酬だ。
どこか硬直的な「絆」というキャッチより、自然体で支援してくれる人のほうがよっぽどありがたいし、今もつながり続けているのはこういう人たちだ。
絆よりも縁。この言葉を、最近よく思い出している。(野中大樹)
▼先日レンタルビデオ店で『天国から来たチャンピオン』を(もう3回見ているけれど)1週間借りようと、会員カードと500円をカウンターに出したら店員が「500円の方からでよろしかったでしょうか」と質問(?)するのでつい「よろしかったと思います」と応えたら変な顔をされた。
「変なのはあなたの方とちゃいまっか?」と突っこみたくなったが我慢した。500円の他にどっちの「方」があるのかわからないし、なにが「よろしかった」(過去形である)のかもわからない。
最近、この手の言葉に対するガマンが増えてきた。たとえば「全然」には否定形が伴うと思うのだが、「全然問題だ」などと言われると全然わからない。「鳥肌が立つほど感動した」とテレビでおっしゃるが「鳥肌が立つ」のは恐怖か寒気である。
「ヤバイ」はさらに使い方が広い。まずいときだけでなく最近は感激したときにも使う。元凶は憲法9条への利己的拡大解釈の影響と秘かに思っている。これが話し言葉まで横着にした。(土井伸一郎)
▼うちの会社の最寄り駅からは武道館が近いので、最近は袴姿やスーツ姿の卒業生たちをよく見かける。わが家にも一人卒業生がおり、先日卒業アルバムを持って帰ってきた。集合写真で彼を探すのは比較的簡単である。端もしくは最後列がいつの頃からか指定席。かならず写真を外側から探す癖がついてしまった。
どこでもそうだと聞きはするが、学校の出来事などまったく話さず、毎日家を出かける背中だけで学校の様子を想像する毎日。通った日数に比べれば、少なすぎる枚数の写真から、過ごした3年間を想像してみる。このスナップはなかなかにいい表情ではないかなどと悦に入ってみる。アルバム委員の生徒に感謝感謝。
写真を撮るときは必ずセンター、世の中一歩前に出る(出たがる?)方々が仕切っているような気がするのは、やっかみだけではないだろう。世の中の端っこでも全然構わない。そこで幸せな生活を送って欲しいとささやかで大それた願いを込めてページを閉じた。(志水邦江)