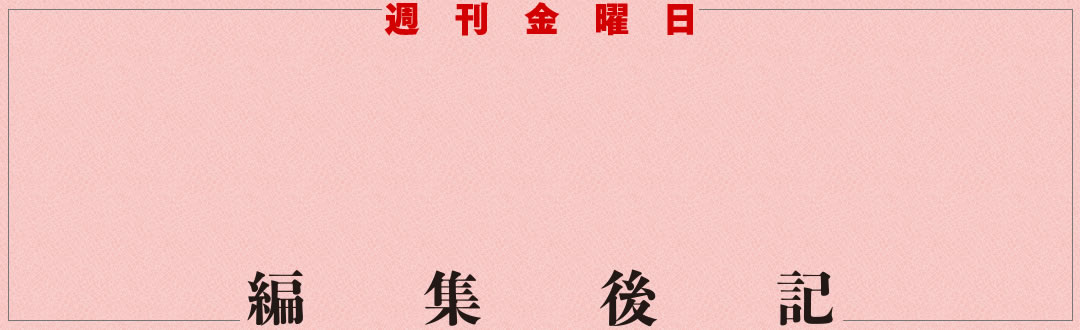1507号
2025年02月07日
▼アフガニスタン、イラク、パレスチナなどの戦地で兵士の銃口や空爆から逃げ惑いながら取材してきた体験から、自らを守るには非武装・逃亡が最も効果的と考えてきた。憲法9条は真実を突いているが、功利主義者である私は理念から非武装を主張してきたのではない。近刊の拙著『ベトナム戦争 匿されし50年の検証』(風媒社)にも書いたが、侵略され、愛する人を殺された者が武装蜂起するのは当然の権利とも考える。
しかし、ベトナム人民による抗米戦の戦い方や生き方、先週号での在日朝鮮人らの指紋押捺拒否闘争を学ぶ中、9条を本当に必要としているのは日本に侵略され、植民地化されたアジアの人々なんだと確信した。パレスチナ人同様、生まれ育った土地から退去させられる理由もないし、「自由」に根ざした移住先もない人々だ。
韓国大統領の非常戒厳宣言の法的根拠は憲法にある「国家非常事態」条項や戒厳軍に対する統帥権だ。「日本国憲法にも緊急事態条項の導入を」などと改憲を主張画策するトランプ的日本人には「9条」は「ブタに真珠」だ。もったいないだけだろう。(本田雅和)
▼経済アナリストの森永卓郎さんが亡くなった。一昨年末にがんを公表し、以来、闘病しながら執筆活動やラジオ出演にがんばっていた。毎朝、通勤中に森永さんがレギュラー出演しているラジオ番組を聴くのが楽しみだったので、残念でならない。
本誌でも昨年の7月12日号でインタビューをお願いし、オンライン取材ではあったが、内容の濃い話を聞くことができた。「岸田政権とは何だったのか」の連載記事で、政権延命を狙った所得減税や国民感覚とズレた少子化対策の問題点など鋭く指摘してもらった。
森永さんは著書『ザイム真理教』などで、一貫して財務省の増税路線を批判し、国民の負担増、格差拡大などに憤りを見せていた。ラジオで時に厳しい言葉を使うことはあっても、リスナーに不快な印象を残さないのは、森永さんがもつユーモアや温かさゆえだった。
67歳で逝ったのは早い。それでもたくさんの本を世に出し、多くの人を楽しませ、大学で経済を学ぶ若者の指導もした。「フルスイング」を貫いた、あっぱれな人生だったと思う。ありがとう! モリタクさん。(小川直樹)
▼1月28日の未明まで続いた会見を中継で見ながら既視感を覚えていた。1996年のTBSビデオ問題、97年のテレビ朝日ペルー取材問題、2003年の日本テレビの視聴率操作事件......いずれの時にもこんな場面があったっけ、と。
そういえば03年の時も記者会見をめぐる攻防があった。会見開催の噂を聞きつけて問い合わせても同社広報は否定。構わず開始時刻前に同社会見場前の受付まで押し掛けたが、すいすい入場していく新聞記者らの横で私は止められ、横から「まあまあ」と現れた幹部社員氏に後日、あらためて取材に赴き「どういうことですか!?」と怒りの質問をぶつけると「録音を止めて」との条件のもとに返ってきた答えが「うーん、ひとことで言えば大手町方面の意向だな」。
思えばあれも週刊誌のスクープから始まった話だったんだよなと思い出した。今回は最終的に雑誌やネットメディアも会見に参加できたけど、底流にあるものは昔とそんなに変わってないのかなと、当夜は会見場での知り合いの記者さんたちの活躍ぶりを画面越しに眺めつつ感じた次第。(岩本太郎)
▼フジの「やり直し」会見で気になった経営陣の発言が3点ある。
一つは女性社員を接待に同伴させることについて「女性を一人で差し出すケースは少ない」「男性もしくは年寄りの女性を同伴させるケースが多い」と発言したこと。差し出すという表現でもうアウトなのだが、そもそも自社社員を取引先の「接待」要員として連れていくこと自体がハラスメントの温床となり得ることに彼らはどこまで自覚的だったのか。そしてこれは人数や年齢、性別の問題ではない。
二つ目はCМ取り下げ対応に奔走する営業部門のセールスを「その下の売り子たち」と称したことだ。咄嗟に出たであろう彼らの言葉にこそ、人権を軽視する企業風土が端的に現れていたのではないか。
最後は日枝久取締役相談役に対する呼称だ。彼らは会見で自社の人間である日枝氏に対し、呼び捨てではなく、敬称を付けた。今回、港浩一前社長は被害者を「刺激したくなかったため」に中居正広氏の番組を継続したと述べたが、本当に刺激したくなかったのはこの企業風土を作ったとされる日枝氏だったのではないのか。(尹史承)