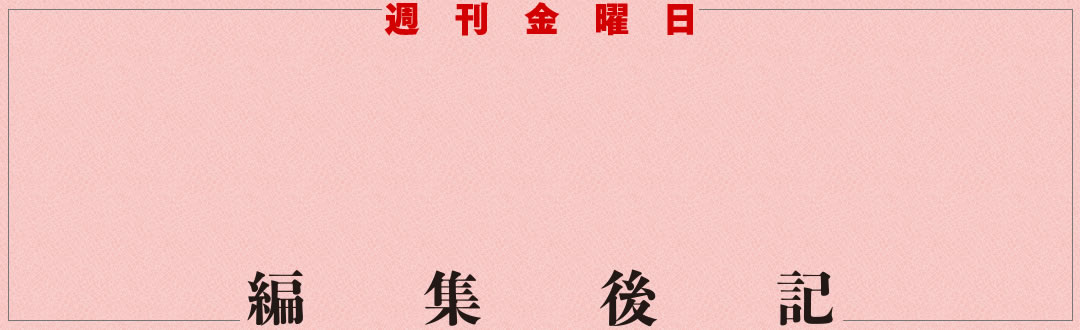1517号
2025年04月18日
▼今度こそ選択的夫婦別姓の実現なるか、という国会情勢で、野党間及び与野党間の調整が進んでいる。政党の面子の問題がクリアできれば多数派形成は可能なところまできており、成立が強く望まれている。しかし、当事者がまったく成立を望んでいない特定生殖補助医療法案のほうが動きが早く、今国会で成立する可能性もあるという。今週号で問題点を指摘する記事を掲載しているが、医療の問題だと狭く捉えないでほしい。
問題の本質は、「この法案は、子どもを守るのでも親を守るのでもなく、家父長制を守りたいだけ」という指摘に集約されている。以前、当事者の方たちに話を聞いた時に言われたものだ。国が「望ましい家族」を決めてそれ以外を排除する考え方は、障害などを理由に不妊手術を強制した旧優生保護法を思わせると言う人もいる。
そして、問題だという声があっても修正せず、参院で主導している議員らが成立を急ぐのは、今夏の参院選で法成立を「手柄」として訴えたいからだろうと当事者らは察している。差別的な内容で憲法違反も指摘されている法案を、改選議員のために通すことなど、あってはならない。(宮本有紀)
▼ノンフィクション作家の堀川惠子さんが書いた『透析を止めた日』(講談社。2024年11月20日)を読み始めました。本来は、読了してから紹介すべきでしょうが、序章から重要な問題提起があふれています。
透析をしていたのは、堀川さんのパートナー、林新さんです。堀川さんは彼と出会った時、12年にわたる透析の8年が過ぎていたと言います。それから4年たち、腎臓移植をして透析の鎖から解き放たれた9年、そして再び透析に戻った1年余りの人生を歩みました。
日本では現在、約35万人が透析を受けていますが、堀川さんは〈透析をめぐる医療システムの問題があった〉と断言します。
〈本書は透析患者の、ことに終末期に生じる問題について、患者の家族の立場から思索を深め、国の医療政策に小さな一石を投じようとするものである〉〈終末期の透析患者をめぐる諸問題について重ねた取材をもって、今後のあるべき医療のかたちを展望したい〉とする堀川さんの問題提起を受け止めながら熟読し、弊誌として何ができるかをしっかりと考えたいと思います。(伊田浩之)
▼誤変換には和む。以前の夕刻、疲れた頭で編集部のPCに向かい執筆作業をする中「岩本町駅」と書こうとしたところ「岩本懲役」と変換しやがったのには「何だとこのやろー!!」と逆上して思わず喚き散らしそうになったが、それを例外とすれば、たとえば「汚職事件」と書こうとして「お食事券」になったり「大阪都構想」と書くはずが「大阪と抗争」になったりというのは、よくネタとして私的なSNS投稿の場などで使わせていただいております。でも今のところ「サイパン歓楽」を超える凄絶なものにはお目にかかっていないな。
......などと書きつつも普段からお世話になっている、そしてこの駄文もゲラでチェックされているはずの校正スタッフの方々が腹を抱えず頭を抱えておられるのではないかと気がひけるわけですけど(汗)。単なる誤変換ならともかくそのまま誌面に掲載されて誤字となり、この頁の「訂正とお詫び」の案件となってしまわないように(今回も「玄海町」を「現会長」とやりかけて焦ったもんな)重々注意を払い、岩本懲役になったりせぬよう気をつけますので今回はご容赦をば。引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。(岩本太郎)