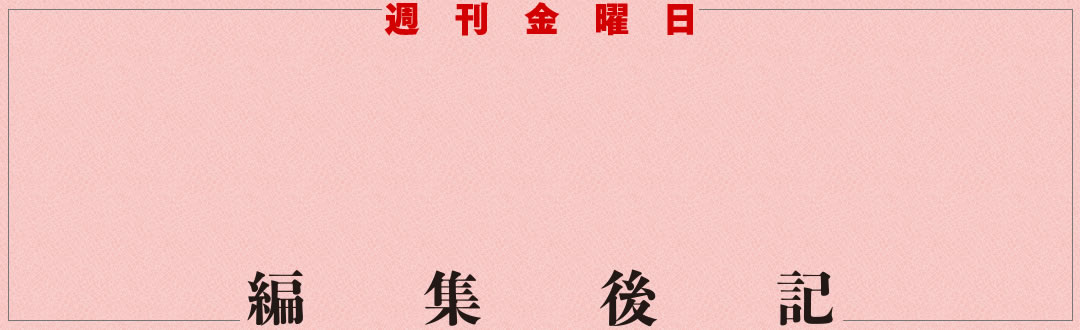1518号
2025年04月25日
▼通勤途中、海外からの旅行者とおぼしき人たちを本当によく見かける。バックパックを担ぎキャリーバッグを引き、もう片方の手でスマホを握りしめている。時には子連れの家族で、時にはパートナー同士で。微笑ましく思う一方で、きょうは胸に苦い。住居を破壊され、生計手段を断たれ、逃げ惑っている人たちの報に接しているからだろう。
2年前の10・7以降のパレスチナ・ガザにおける死者はガザ保健省の調べによると5万人を超えたという。報道は少ないが、ヨルダン川西岸でも破壊・虐殺が続いている。今週号でその状況を報告してくれた小田切拓さんによると、かつてのガザのような「収容所」化が進んでいるという。いのちとともに生活の自由が奪われているのだ。記事の後半には、にわかには信じがたい証言もある。
現地にいる小田切さんからテレビ電話がかかってきた。記事の相談だが、小田切さんはカメラをぐるっと回して町の様子を見せてくれた。青い空に古い建物。不思議と、なんだか懐かしい光景に思えた。(小林和子)
▼石破茂政権は、長引く物価高や米国の高関税措置への対策を名目に、市民への一律3万~5万円程度の現金給付を検討したが、世論の激しい批判を受けて見送った。
夏の参院選に向けた露骨な「バラマキ」だと見透かされたわけだが、そもそもその給付額では、石破首相の金銭感覚に照らすとハンカチすら買えない。自民党新人議員への商品券配布問題のときに「(10万円は)お菓子やハンカチを買ってもらう」ためと苦しい弁明をしている。だいたい給付金の財源はどこにあるのか。
「年収103万円の壁」を引き上げるための減税議論では、「その財政状況にない」ことを理由に一蹴している。その場しのぎの経済政策による赤字国債の増発は、若い世代にツケを押し付けるだけだ。またコロナ禍の持続化給付金では、電通などの「中抜き」が大きく問題になったが、今回もその懸念は拭えない。「マイナポイント」配布案も同様だ。
石破首相は今回のトランプ大統領の関税措置を「国難」と表現したが、このまま自民党が政権与党にいることのほうがよほど「国難」であろう。(尹史承)
▼近頃ファミレスに行くと、注文はテーブルの上のタブレットや自分のスマホを使ってのモバイルオーダー、出来上がった料理は配膳ロボットが運んで来、会計はセルフレジ、あるいはテーブルでキャッシュレス決済。店には学生アルバイトとおぼしき店員さんもいるのですが、彼ら・彼女らの出番は、客が帰った後のテーブルの片付け。
考えてしまいましたねー。
タブレット注文とかセルフレジとかキャッシュレス決済とか、会社側は効率が上がった、経費が節約できたと評価するのでしょう。でも働く側は? お客さんに「今日のランチ何? どんな料理?」と聞かれたり、会計が終わって帰りしなに「ごちそうさま」とか「ありがとう」とか言われたり、ミスをしたときにお客さんにフォローされたり。労働の喜びというのはこういう小さな積み重ねだと思うのですが(私自身、学生時代のバイトで学んだことは多かった)、今の学生さんたちは、働く喜びを実感したり、何かを学んだりすることはできるのでしょうか。
ということを感じたのでした。
(渡辺妙子)