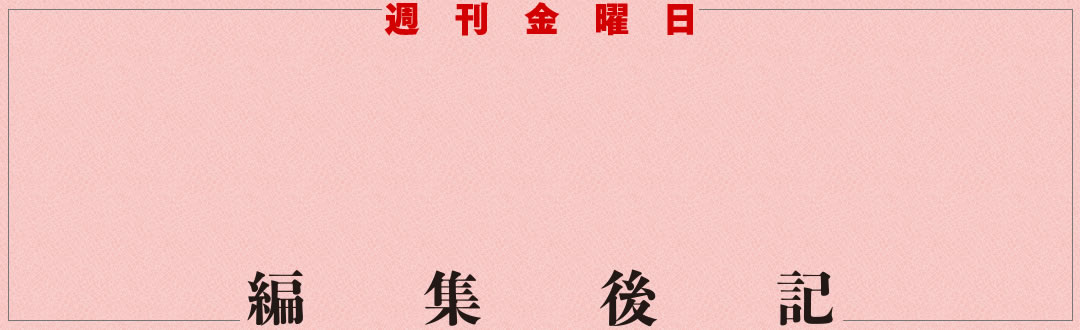1513号
2025年03月21日
▼「後ろから鉄砲玉を撃つ男」の異名をもつ石破茂首相。今回は自身が撃たれたか。参院選に向けて石破降ろしの動きが本格化している。
国会で政治資金改革を議論しているさなか、石破氏の商品券贈与が明らかになった。発覚の経緯にはさまざまな臆測を呼ぶが、政治資金規正法に抵触する可能性があり、政治責任を問われるのは当然のことだ。舞立昇治参院議員は「歴代首相が慣例として普通にやっていた」と擁護したが、皮肉なことに歴代首相の慣例や党の古い体質を批判してきたのが石破氏である。その石破氏ですら悪しき金権政治に抗えない。未だに自民党は裏金事件の温床ともされる企業・団体献金について禁止ではなく、存続を訴えている。問題にすべきは、「政治とカネ」の不祥事を繰り返し、市民から厳しい視線を向けられてもなお、自浄能力が働くことがない自民党の体質そのものであろう。首をすげ替えたところで何ら変わることはない。(尹史承)
▼石破茂首相の商品券配布問題が現時点でトップニュースになっている。これをまずいと思わなかった石破氏については「やはり自民党政治家だな」と思うだけで驚きはしない。ただこのニュースに関連して驚いたのは、橋下徹、堀江貴文、ひろゆき各氏の考えが「識者コメント」扱いでスマホの上位ニューストピックにあがっていたことだ。それぞれが1本ずつのニュース記事として報じられていた。
彼らをフォローしていないので、AIが私の好みとして選択したわけではない。一般的によく読まれるから上位にあるのだろう。この人たちの意見が尊重される社会になっているということだ。テレビのコメンテーターも、先の3人や石丸伸二氏、成田悠輔氏など社会批判を冷笑するタイプの人が多く、彼らをもてはやす空気になっている。無力感にさいなまれる日々だが、この勢力に抗い、包摂的社会を構築するためには「微力だが無力ではない」を信じて市民がつながるしかない。(宮本有紀)
▼「ラジオ」を観てきた。12年前にNHK総合テレビで放送されたドラマだ。「3・11」後に被災地の宮城県女川町に設立された臨時災害放送局「女川さいがいFM」をめぐる実話を基に一色伸幸さんが脚本を担当。そこに活写された世界が、目下の能登半島の地震・豪雨被災地の現状にも重なるなど歳月を経ても古びていないことに上映会で観ながら感じ入った。
「女川さいがいFM」は2016年3月に閉局した。最終日の放送終了前、最後にかけられた楽曲はサザンオールスターズの「TSUNAMI」。震災後は放送電波に乗ることがほぼなくなったこの曲が普通に聴ける日常を願い、同局スタッフの総意で決めたという。
局自体は消えてしまったけど、そこからラジオの波に乗せて発せられた想いを私たちはこれからも語り継いでいく。来たる5月には能登半島の地震・豪雨被災地でも臨時災害放送局「まちのラジオ」が開局の見込みだ。(岩本太郎)
▼編集部で働き出して4年半。自称ジャーナリストやライター、市民活動家の原稿を拝読する中、無礼ながら言論の劣化を実感することが多くなった。本誌創刊者の本多勝一著『事実とは何か』を引くまでもなく、何を書くかという選択自体が「主観」ゆえ、罵詈雑言も含めて権力者や他者への批判がジャーナリズムや表現の本質なのは理解する。が、そこで展開される論理も極めて乱暴粗雑なのだ。
右翼の看板だったヘイトスピーチが左翼にも罹患したのか、井戸端会議や床屋談義で使う水準の言葉が横行する。部落差別・民族差別・性差別も複合差別が現代形態なのに、差別認識の説明に未だに「士農工商」の比喩を使ったり、売春の根本が家父長制による買春構造にあることさえ無視したり、論敵を「毛虫の好悪」に例えたり「無能」呼ばわりで済ませる著名人も。「米帝国主義者どもが......」と書くよりも、説得力ある事実の指摘を! 本多がベトナムから教えてくれている。(本田雅和)